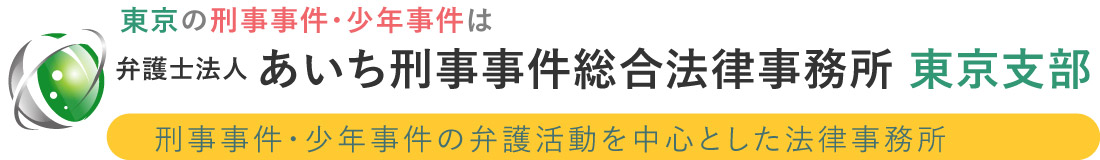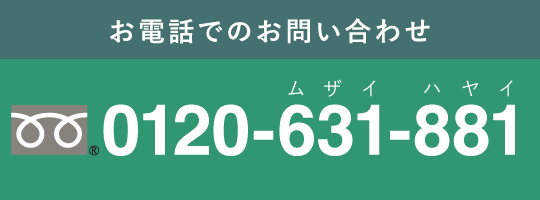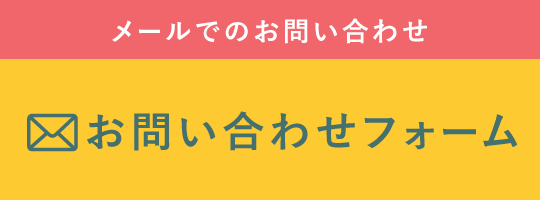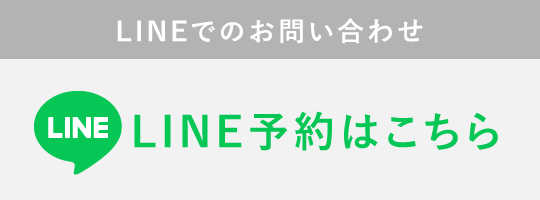暴行した相手が死亡してしまった同時傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇暴行の相手が死亡◇
土木作業員のAさんは、同じ工事現場で作業をしている同僚と仲が悪く、普段からトラブルを繰り返しています。
その同僚と、先日偶然、豊島区にある行きつけの居酒屋で出くわしてしまい、口論になった後に、Aさんは同僚の顔面を複数回殴りつけてしまいました。
そして同僚は、Aさんに殴られて転倒する際に、偶然、そばにいた酔っ払いの服を掴んでしまい、酔っ払いの服を血で汚してしまいました。
服に血が付いたことに怒った酔っ払いは、Aさんに殴られて転倒した同僚の顔面を足で踏みつける暴行を加えました。
Aさんと、酔っ払いの暴行によって傷害を負った同僚は、救急搬送されましたが、頭部に重傷を負っており、その後死亡が確認されました。
通報によって駆け付けた警視庁池袋警察署の警察官によって傷害罪で現行犯逮捕されていたAさんは、その後、傷害致死罪で取調べを受ける事になりましたが、Aさんは、同僚が死亡した原因は、酔っ払いによる暴行が原因だと思っており、この罪名に納得ができません。
(フィクションです。)
~傷害致死罪と同時傷害の特例(刑法207条)~
本件では、Aさんに同時傷害の特例が適用され、傷害致死罪が適用されています。
同時傷害の特例とは、耳慣れない方も多いかもしれませんが、刑法207条によって規定されています。
刑法207条は、
・「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において」
・「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは」
・「共同して実行した者でなくても、共犯の例による」
という、非常に特殊な規定になります。
刑法60条は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と、共犯の中でも共同正犯について定めていますが、本来本条が適用されるには、2人以上の間に共謀が必要とされています。
刑法207条はこのような共謀がない場合にも、共同正犯が成立することを認める特殊な規定なのです。
さらに、本条は本来は検察官が負うはずの挙証責任を、被告人側に転換する(行為と結果の因果関係の不存在を被告人側に負わせる)点においても、特異な規定であり、学説上も批判が根強く主張されているところでもあります。
このような特例が置かれた趣旨については、傷害の結果が明らかであるにもかかわらず、当該傷害について誰も刑事責任を負う者がいなくなってしまう事態を回避するための特例との考え方が通説とされています。
この点、近年の判は、本条の適用に関し、まず「共犯関係にない2人以上」の「各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するもの」であり、「同一の機会に行われたものである」場合には「各行為者において、自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない」としました。
さらに上記判例は、「共犯関係にない2人以上の暴行による……刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には、いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、各行為者について同条の適用は妨げられない」としています。
これは、207条は暴行と死亡結果の因果関係を問題とするものではなく、あくまで暴行と「傷害」結果の因果関係が不明な場合に適用される規定であることを示したものと考えられます(上述のとおり207条では、「その傷害を生じさせた者を知ることができないとき」という文言が使われています。)。
したがって、本件Aさんが「当該傷害を惹起する危険性」を有する暴行を、「同一の機会」に行ったと認められば、207条の適用を介して、傷害致死罪(刑法205条)の罪責を負う可能性が生じることになるのです。
~同時傷害の特例における弁護活動~
弁護士としては、本条の適用について、Aさんの暴行が本当に「同一の機会」によるものであるのかを検討する必要があるでしょう。
さらに、刑法第207条が因果関係の挙証責任を被告人側に転換している規定である以上、Aさんによる暴行と、同僚の傷害との結果の間に因果関係がないということを積極的に立証するという特殊な立証活動が求められることになります。
仮に、因果関係がないことが証明されれば、Aさんが負う刑事責任は傷害罪の程度にとどまることになり、その法定刑に大きな差が生じることになるため、弁護士の立証活動が重要になることは言うまでもありません。