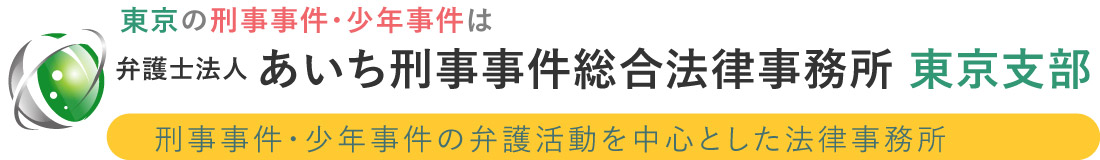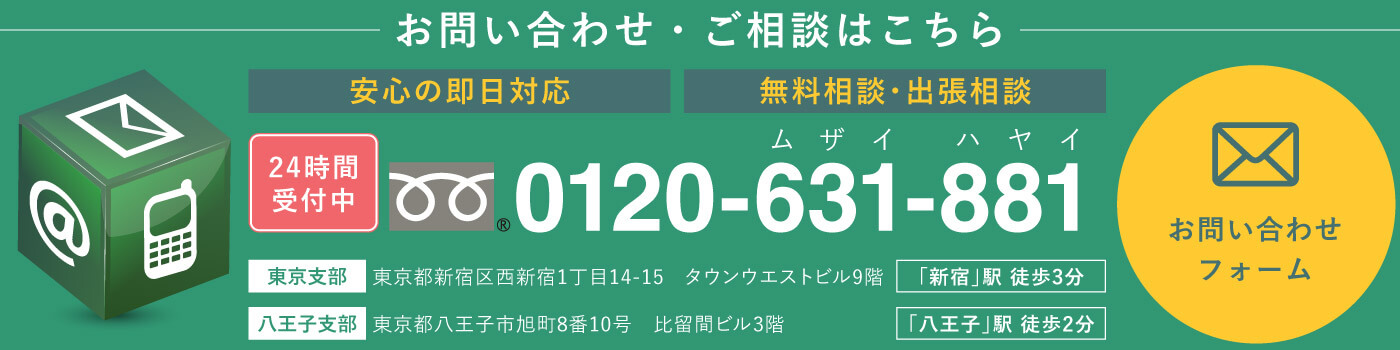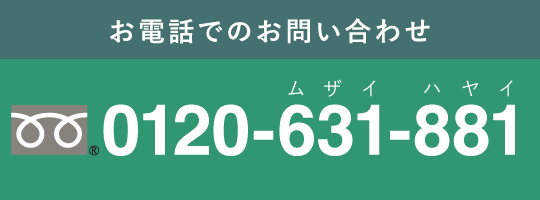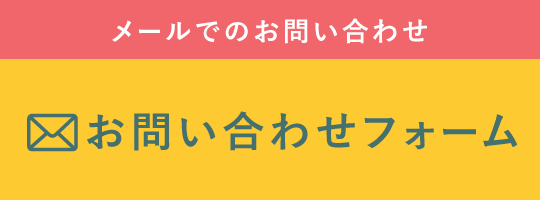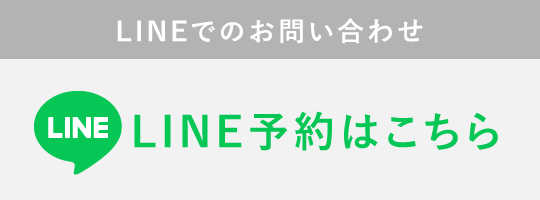Author Archive
覚せい剤所持事件で逮捕 早期の釈放と執行猶予の獲得に強い弁護士
覚せい剤所持事件で逮捕された方の、早期の釈放と執行猶予の獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~覚せい剤の所持容疑で逮捕~
東京都八王子市在住のAさんは、ある日警視庁八王子警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際に、任意で所持品検査に応じたところ、鞄の中から小分けにされた覚せい剤のパケが見つかってしまいました。
Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたようです。
(フィクションです)
~覚せい剤事件~
覚せい剤の所持は覚せい剤取締法によって禁止されています。
罰則は単純所持・使用は10年以下の懲役と定められています(41条の2第1項、41条の3第1項3号)。
覚せい剤の所持や使用で逮捕された場合、ほとんどの場合、検察官による勾留請求がなされます。
勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性となっています(刑事訴訟法207条1項、60条)。
勾留の理由とは刑事訴訟法60条1項各号所定の事由をいい、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれをいいます。
覚せい剤などの薬物事件の場合、本人が製造したという場合は格別、薬物を提供した共犯的人間が存在することが通常です。
逮捕されてしまった場合、提供した人間と何らかの口裏合わせなどをする可能性が高く、罪証隠滅のおそれは高いとみなされてしまいます。
勾留請求が認められた場合、逮捕に加えて10日間、やむを得ない事由がある場合にはさらに10日間延長され、最長で20日間勾留されてしまいます。
また、覚せい剤などの薬物事件の場合、接見禁止処分が付される場合もあります。
接見禁止処分が付されてしまうと、弁護人以外はたとえご家族であっても面会することはできません。
これは、自宅などに隠し持っている残りの薬物を廃棄してもらうなどの罪証隠滅を防ぐためです。
勾留された場合、検察官は勾留期間中に事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。
覚せい剤などの薬物事件の場合、違法な証拠収集であった場合など特殊な場合を除き、ほとんど起訴されてしまいます。
起訴された場合には勾留に引き続き被告人として身柄拘束されてしまいます。
~弁護活動~
◇起訴前◇
弁護士はまず身柄解放に向けて活動します。
勾留決定がされてしまった場合には勾留決定に対する準抗告の申立をします。
また、接見禁止処分が付されている場合には、接見禁止の一部解除を申立ます。
接見禁止の一部解除が認められれば、ご家族などが面会することが可能となります。
仮に接見禁止の一部解除が認められないような場合には弁護士による接見の際にご家族への伝言などをお伝えします。
◇起訴後◇
検察官によって起訴された場合、通常、被告人として引き続き勾留されてしまいます。
身柄解放のため、勾留に対する抗告や保釈申請を行います。
覚せい剤等の薬物事件では起訴前の勾留の段階で証拠などの捜査が終わっていることが多いため、保釈請求が認められるケースが多いです。
保釈が認められれば、身柄解放となり、普段通りの生活を送ることが可能です。
しかし、裁判所などからの出頭要請には応じる義務があり、特段の理由もなく応じないような場合には保釈が取り消され、再び身柄拘束をされてしまいます。
起訴された場合には刑事裁判を受けることになります。
覚せい剤の単純所持や使用の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決となることがほとんどです。
しかし、必ずしも執行猶予が付くというわけではありません。
実刑となり刑務所に収監されることよりも執行猶予として社会内での更生を図るべきであると裁判官に納得させる必要があります。
具体的には、再犯防止に向けて専門医の治療やカウンセリングを受ける、ご家族による監督があることなどを示す必要があります。
どのような取り組みをすべきかは薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤などの薬物事件の弁護経験な弁護士が多数所属しています。
覚せい剤など薬物事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
SNSトラブル 匿名の書き込みが刑事事件に
SNSへの匿名の書き込みが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇SNSトラブル◇
大学生のAさんは、芸能人や有名スポーツ選手のSNSを閲覧することが趣味で、世間を騒がせている時事問題や、ニュースに関することには積極的に書き込みや投稿をしています。
ある日、某芸能人がテレビで発言したことに腹が立ったAさんは、この芸能人の、ツイッターやインスタグラムなどのSNSに、匿名で過激な内容の書き込みをしました。
Aさんは、これまで何度も同様の書き込みや投稿をしていたので、何も気にせずにしていませんでしたが、先日、警視庁麹町警察署の捜査員から「芸能人のSNSに匿名で書き込んだ投稿で被害届が出ている。警察署に出頭してくれ。」といった出頭要請の電話がかかってきました。
匿名で投稿していたから大丈夫だと思っていたAさんは不安になり、自分の投稿内容がどのような犯罪に該当するのか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
※フィクションです。
◇匿名の投稿が社会問題に◇
インターネットツールが発展し、子供からお年寄りまで誰もが手軽にSNSを利用できる便利な世の中になりました。
そんな便利な世の中だからこそ、インターネット上の事件も頻発しており、これが大きな社会問題となっています。
特に最近は、SNSに匿名で投稿した内容が問題視されるケースも多く見受けられています。
匿名であるが故に、投稿者が特定されないだろうという油断と安心から、投稿内容が過激になり、刑事事件に発展するケースも少なくなりません。
そこで本日は、匿名によるSNSへの投稿が刑事事件に発展したケースについて紹介します。
◇脅迫罪◇
あるアイドルのファンが、アイドルのSNSに「殺す」等の過激な投稿をしたことから、アイドルの所属事務所が警察に相談し、投稿者が逮捕された事件。
「脅迫罪」とは、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫することです。(刑法第222条から抜粋)
脅迫罪で起訴されて裁判で有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
数年前には、実際にアイドルがファンに襲撃されて重傷を負う事件が発生しており、警察は、このような書き込みには厳重に対処しているようです。
◇業務妨害罪◇
特定のお店(飲食店)のホームページの掲示板に「お店に爆弾を仕掛けた。」等の書き込みをして、お店を休業させた事件。
投稿や書き込んだ内容によって、お店の業務に支障をきたせた場合は、業務妨害罪が成立することがあります。
業務妨罪には、偽計業務妨害罪と、威力業務妨害罪があり、共に起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
ここ数年、インターネット上への、書き込みや投稿に「業務妨害罪」が適用される事件が増えており、お店や企業は積極的に被害届を提出して刑事事件化を望んでいるようです。
◇名誉棄損や侮辱罪◇
ある会社のホームページ上の掲示板に「●●(この会社の役員実名)は同僚の▲▲と不倫している。」と書き込んだ事件。
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける事で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられます。
名誉棄損罪が適用されなかったとしても、いわゆる悪口に該当するような内容を投稿、書き込みをしたら侮辱罪となる可能性もあります。
侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いものですが、刑事手続きが進めば取調べ等が大きな負担となることは間違いありません。
◇インターネット上の犯罪に強い◇
インターネット上の書き込みや、投稿は匿名であることがほとんどで、裏アカウントを作成すれば、自身にまで捜査の手が及ぶことがないと考えている方もいるかもしれませんが、プロパイダー等への捜査で、投稿者は容易に特定されてしまうようです。
東京都内で、SNSトラブルや、自身の匿名での投稿、書き込みが刑事事件化されてお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕
暴力行為等の処罰に関する法律違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都大田区に住むAさんは、大田区内の国道を車で走行中に割り込まれたことに腹を立て、割り込んできた車を停め、運転していた男性に対して、サバイバルナイフをちらつかせ、「お前殺すぞ。」などと脅しました。
その後、Aさんは、警視庁蒲田警察署に暴力行為等処罰法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
◇暴力行為等処罰に関する法律について◇
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。「暴力行為処罰法」や「暴処法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律ですが、過去に学生運動の取り締まりに使われていました。
~暴力行為等の処罰に関する法律~
法1条は、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を定めています。
法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、「1年以上15年以下の懲役」を定めています。
法1条の3は、常習的に人を傷害したについて、「1年以上15年以下の懲役」を定め、常習的に人を暴行・脅迫したり、器物損壊をしたりした場合について、「3月以上5年以下の懲役」を定めています。
法2条は、財産上不正な利益を得る目的で、集団による威迫を手段として強談威迫等をした者について「1年以下の懲役ないし10万円以下の罰金」を定めています。
法3条は、集団的に殺人・傷害・暴行・脅迫・強要・威力業務妨害・建造物損壊・器物損壊を犯させる目的で財産上の利益や職務を供与、申込や約束、情を知って供与を受け、若しくは要求や約束をした者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」を定めています。
1条にいう「仮装」とは、一般に相手方を誤信させるような行為をいい、実際に相手を誤信させる必要はありません。
また、「兇器」については、鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか、用法によっては、人の生命、身体又は財産に害を加えるに足りる器物で、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
1条の3にいう常習性とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として、さらに同種の犯罪を犯した場合をいいます。
単に前科前歴があることだけをもって常習性があるとはいえません。
今回の事件において、Aさんは被害者に対して、サバイバルナイフを示したうえで「お前殺すぞ。」と申し向けています。
このような行為は法1条に違反し、Aさんには「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるため、凶器を用いた暴処法違反が適用された方がより重く処罰されるのです。
◇暴処法の弁護活動◇
暴処法で取調べを受けた場合や、逮捕された場合で、事実に争いがない場合、できる限り速やかに、弁護士を通じて、被害者への被害弁償または示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で、被害弁償または示談を成立させることで、警察が介入する前に事件を終了させたり、不起訴処分を獲得したりすることによって前科をつけずに事件を解決し、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。
暴処法で起訴された場合、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めていくことを目指します。
また、犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付きの判決を目指します。
◇東京都大田区の刑事事件に強い弁護士◇
東京都大田区で暴処法に関する相談を含め暴力事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【羽村市の少年事件】拾った財布を届けずに刑事事件に発展
高校生の占有離脱物横領、詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
高校1年生で、16歳のAくんは、東京都羽村市内で道に落ちている財布を拾ったところ、中からクレジットカード、現金1万円を見つけたので、自分のものにしてしまいました。
1万円はそのまま飲食店で使い、クレジットカードはコンビニでの買い物で使用しました。
後日、Aくんの自宅に警視庁福生警察署から連絡があり、「お尋ねしたいことがあるので、Aくんに出頭してほしい」とのことでした。
Aくんの親は不安になり、弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
◇少年事件の手続き◇
Aくんの行った行為のうち、道に落ちている財布を拾い、中からクレジットカードや現金を自分のものにしてしまった行為は、「占有離脱物横領罪」(刑法第254条)または「窃盗罪」(刑法第235条)、クレジットカードで買い物をした行為は、「詐欺罪」(刑法第246条)に問われる可能性があります。
Aくんが成人の場合は、警察で取調べを受けた後、逮捕されるか在宅で事件が進行するかを問わず、最終的に検察官がAくんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
起訴され、有罪判決を受けると、刑罰を言い渡されることになります。
しかし、Aくんは20歳に満たない「少年」なので、成人の場合と異なり、原則として少年法の定める「少年保護事件」として手続が進行することになります。
Aくんの性格や環境に応じて、必要な「保護処分」を行うことが、この手続の目的です。
捜査機関による取調べが行われる点、逮捕・勾留されうる点では成人と同じですが、①犯罪の嫌疑がある場合、また、②犯罪の嫌疑はないものの、審判に付すべき事由が認められる場合には、原則として家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、少年の性格や家庭環境の調査が行われます。
調査の結果、審判が開かれると、保護観察処分などの保護処分や不処分等の決定がなされます。
◇保護処分にはどのような種類があるか?◇
保護処分は、家庭裁判所の審判によって言い渡されます。
保護処分には、
①保護観察処分
②少年院送致
③児童自立支援施設又は児童養護施設送致
があります。
(保護観察処分)
保護観察処分は、少年を保護観察所の指導・監督に委ね、改善更正を目指す保護処分です。
この処分が言い渡された場合は、在宅で処分を受けることができるので、少年本人の負担が少ないということができます。
(少年院送致)
少年院送致は、その名の通り、少年を少年院に送致し、規律ある生活になじませて指導・訓練を行うことを内容としています。
少年院送致では少年院での生活を余儀なくされ、特別の場合を除いて外出することはできません。
(児童自立支援施設又は児童養護施設送致)
児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童や生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
児童養護施設は、保護者のない児童(乳児は除かれます。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含みます)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
◇審判に向けてどうするか?◇
紹介した保護処分のうち、児童自立支援施設又は児童養護施設送致は、その性質上Aくんになされる可能性はあまり高くないと思われます。
したがって、Aくんになされる可能性の高い保護処分は「保護観察処分」、「少年院送致」ということになります。
Aくんの学業や生活を考慮すると、本来の生活環境を離れることになる「少年院送致」は回避したいところです。
保護観察処分を受けることにより事件を解決するには、家庭裁判所の裁判官に、Aくんが在宅であっても改善更正しうる、ということに納得してもらう必要があります。
そのためには、Aくんに真摯な内省を促し、家庭での指導環境を充実させる必要があります。
弁護士のアドバイスを受けながら、環境調整を行い、より有利な事件解決を目指していきましょう。
◇少年事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が占有離脱物横領・詐欺事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
交際相手に頼まれて覚せい剤を使用
覚せい剤の使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、覚せい剤取締法違反の前科があり、最近は覚せい剤を使用していません。
しかし、かつて覚せい剤を使用していた時に知り合った人たちとの関係を絶ち切れておらず、今でも一緒に食事に行く等の付き合いを続けています。
そしてAさんは、その中の一人の女性と交際を始めたのですが、交際相手の女性は、覚せい剤の常習使用者で、これまで覚せい剤取締法で何度か警察に逮捕された歴があるようでした。
Aさんは交際している女性にこれまで何度も覚せい剤を止めるように言っていますが聞き入れてもらうことができていません。
それどころか、2日ほど前には、「覚せい剤を打ってくれ。」と頼まれたので、指示に従って女性の足の甲の血管に、水で溶かした覚せい剤の溶液を、注射器で注入したのです。
そして今朝、女性と歩いているところを、警視庁練馬警察署の警察官に職務質問され、任意採尿の後、女性は覚せい剤を使用した容疑で逮捕されてしまいました。
女性が覚せい剤を使用したのは、2日前にAさんが注射して上げて使用したのが最後です。
(フィクションです。)
◇覚せい剤の使用◇
覚せい剤を使用することは、覚せい剤取締法によって禁止されており、覚せい剤の使用で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
~「使用」とは?~
覚せい剤取締法でいうところの「使用」とは、覚せい剤等を用法に従って用いる、すなわち「薬品」として消費する一切の行為をいいます。
使用方法に制限はなく、水に溶かした覚せい剤を注射器によって血管に注入する方法や、覚せい剤結晶を火に炙って、気化した覚せい剤を吸引する方法、覚せい剤を飲み物に溶かすなどして経口摂取する方法などがあります。
~「使用」の客体は?~
使用の客体は、人体に用いる場合が最も普通の使用例ですが、使用対象は、人体に限られず、動物に使用した場合も、覚せい剤の使用に該当します。
※他人に使用した場合もアウト※
今回の事件でAさんは、恋人に対して覚せい剤を使用していますが、この行為も覚せい剤の使用となり、刑事罰の対象です。
当然、覚せい剤の使用を依頼した恋人も覚せい剤の使用となり、Aさんと恋人は同じ覚せい剤の使用事件の共犯関係になるのです。
◇逮捕されるの?◇
上記したように、Aさんのように、人に対して覚せい剤を使用した場合も、覚せい剤の使用罪になりますし、すでに逮捕された恋人とは共犯関係に当たるので、口裏を合わせる等して証拠隠滅を図る可能性があることから、逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
◇量刑は◇
もしAさんに、彼女に注射したのが覚せい剤だという認識がない場合などは、覚せい剤使用の故意が認められず不起訴となる可能性が出てきますが、Aさんに覚せい剤の前科があることから、そのようなかたちで故意を否認するのは難しいと考えられます。
単純な覚せい剤使用事件の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決を得ることができるでしょうが、短期間の再犯の場合は2回目からは実刑判決が言い渡されることもあります。
今回の事件でAさんが起訴された場合、執行猶予付きの判決を得れるかどうかは、前科の数と、前刑との期間によるでしょう。
東京都内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまった方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
触法少年による刑事事件
触法少年の犯罪行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都台東区の小学校に通う6年生のA君(12歳)は,学校の女子トイレを盗撮するために、スマートフォンを持って女子トイレに隠れていました。
異変に気付いた女子生徒が先生に助けを求めて事件が発覚したのですが、A君の持っていたスマートフォンには、多くの盗撮画像が保存されており、小学校で対処できないと判断した先生は、警察に通報し、A君は警視庁蔵前警察署に補導されました。
警察署から連絡を受けた母親は、今後のことが心配になって少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
◇刑事責任能力◇
本来なら犯罪行為をしたと認められた場合、その犯罪行為に当たる罪、刑に処せられます。
A君の行為は
①女子トイレに忍び込んだ行為・・・(刑法第130条)建造物侵入罪
②盗撮行為・・・東京都の迷惑防止条例違反
に該当し、それぞれに法定刑が定められています。
そして、有罪が確定すれば、その法定刑内の刑事処分が確定するのですが、14歳未満の少年は、触法少年と言われ、刑事手続きの対象外となります。
(刑法第41条)
14歳に満たない者の行為は、罰しない
つまり、14歳に満たない者は、刑事未成年者といわれ、その具体的な精神・知能的発育の発達の如何を問わず、常に責任無能者として扱われ、犯罪に当たる行為をしたとしても罰せられることはありません。
◇少年法上はどうか◇
しかし、少年法上は、14歳に満たないで刑罰法規に触れる行為をした少年(これを触法少年といいます)も少年審判を受ける可能性があることを規定しています(少年法第3条2項)。
ここで、「どうして犯罪としては罰せられないのに、少年審判を受ける必要があるのか?」と疑問を持たれる方もおられるかと思います。
それは少年法は、少年の健全な育成を目的としている(少年法1条)からだと考えられています。
少年事件の場合、犯罪の嫌疑がある場合はもちろん、犯罪の嫌疑がない場合であっても、そう疑われるに至った経緯・背景には様々あると思います。
そうした経緯・背景には、少年自身の性格、少年の取り巻く環境(家庭、学校、交友関係など)などに関する問題が影響しているのです。
そこで、そうした問題を一つ一つ丁寧に調査し、少年の性格を矯正し、少年を取り巻く環境を整備することで健全な大人へと育っていってもらうことを少年法は期待しているのです。
少年のうちから、犯罪の目を積んでおこうというのが少年法の目的ともいえます。
◇触法少年の流れ◇
まず、警察官に調査の必要があると認められた場合は警察官の調査を受けます。
調査では、触法事件の対象となる事実やその動機,少年の生活環境などについて聴かれることになるでしょう(少年法6条の2第1項)。
その後、盗撮事件では、警察官が少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めたときは、盗撮事件が児童相談所長のもとへ送致されます(少年法6条の6第1項第2号)。
児童相談所に送致された後は、児童相談所の職員が少年や保護者などから話を聴かれるなどされ、事件について都道府県知事に報告され、かつ、都道府県により家庭裁判所の審判に付することが適当であると認められたときは、盗撮事件は家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所へ送致された後の流れは、その他の年齢の少年の場合と同様です。
すなわち、家庭裁判所調査官の調査などを受けることになります。
その後、調査の結果を総合して、事件を少年審判に付すかどうか決められます。
(少年法3条2項)
家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年(触法少年)及び同項3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付すことができる。
触法少年であっても、警察官の調査を受けたり、一時保護といって身柄拘束を受けたり、少年審判を受ける可能性はあります。調査の段階から付添人(弁護人)を付けることは可能ですから、お困りの方は少年事件に強い弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました。
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年9月24日(木)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士は、経済通産省が広告大手電通が設立した一般社団法人に委託した事業のほとんどで、委託先を決める公募に他の事業者が参加せずに無競争で決まっている問題について朝日新聞DIGITALの取材を受けました。
経済産業省が国会議員に示した資料で、事業は全て電通に再委託されていることが判明し、経済産業省は、競争が確保されるように、公募方法の改善を進めようとしています。
本来であれば、公的事業で一者応募となるケースは、競争性に欠け事業費が割高になる可能性あるとの指摘があり、省庁や自治体によっては参加者が一者の場合は、中止してやり直したり、新規の事業者が参加しやすいように公募期間の延長や、事業の分割、業務の情報開示を勧めたりしています。
~星野弁護士のコメント~
当事務所の星野弁護士は、「実質的に競争がないのなら事実上の随意契約で、公募の意味が失われる。これだけ一者応募が繰り返されているのは極めて不自然。経済産業省が競争性確保の努力を十分にしていたのか検証が不可欠だ。」と指摘しています
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都台東区の準詐欺事件
東京都台東区の準詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
準詐欺容疑で取調べ
東京都台東区にある認知症対応型グループホームの職員であったAさんは、入居者のVさん(当時72歳)が認知症で事物の判断をするのに十分な普通人の知能を欠く状態であることに乗じて、Vさんから現金の交付を受けようと考えました。
Aさんは東京都台東区内の郵便局においてVさんに対し、Vさん名義の通常貯金口座から現金1000万円を払い戻させた上、その頃、同所において、郵便局員を介し、Vさんから前記現金1000万円の交付を受け、もって人の心神耗弱に乗じて財物を交付させました。
後日、事態を知ったVさんの家族から通報を受けた警視庁下谷警察署の警察官によってAさんは取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
準詐欺罪
準詐欺罪は刑法第248条に規定されている犯罪で、判断能力が十分でない等の人に対して、その判断能力が十分でない等の事情に乗じて財物を交付させるという犯罪です。
刑法第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
10年以下の懲役という法定刑は、詐欺罪(刑法第246条)や恐喝罪(刑法第249条)などと同じです。
しかし、詐欺罪がその成立に欺罔行為(人を欺く行為)を求めているのに対し、準詐欺罪では詐欺罪にいう欺罔行為がなくとも処罰可能となる点が重要です。
通常の詐欺罪にいう欺罔行為とは、財産を処分させる手段として、財産についての処分権限をもつ相手方において、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関し、錯誤(思い違いや勘違い)を生じさせる行為です。
準詐欺罪では、相手方が知慮浅薄な未成年者や心神耗弱者である場合に限って、欺罔行為がなくとも未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱を利用して財物の交付や財産上の利益を取得することを処罰可能にしています。
準詐欺罪にいう「知慮浅薄」とは、知識が乏しく、思慮の足りないことをいいます。
そして「心神耗弱」とは、一時的・継続的な精神状態の不十分さにより一般通常人程度の知識・物事の判断力を備えていないことをいい、刑法第39条第2項の心神耗弱とは同一でないことに注意してください。
今回の被害者であるVさんは認知症ですが、相手方が認知症患者であることが直ちに準詐欺罪における心神耗弱であることの認定につながるわけではなく、心神耗弱やさらには未成年者の知慮浅薄はその症状の程度などを総合考慮してなされます。
また、相手方が知慮浅薄な未成年者や心神耗弱者であっても、欺罔行為を手段として財産の処分を行わせた場合は準詐欺罪ではなく詐欺罪に問われます。
加えて、意思能力がない者から財物を取得するときは相手方が財産処分の判断をしているとはいえないため窃盗罪(刑法第235条)となり、同じく相手方が知慮浅薄な未成年者や心神耗弱者であっても、欺罔行為や欺罔行為に至らない程度の偽り・誘惑を手段とせずに財物を取得した場合も窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
量刑判断の考慮事項としては、計画性の高さ、被害額の多さ、犯行の動機、初犯であるかどうか、十分に反省しているといえるかどうか、被害補償をしているかどうかなどがあります。
いずれにしても、刑事事件の知識・経験のある弁護士に相談し、自身のケースではどういった見通しが考えられるか、どういった活動が可能か詳しく聞いておくことが大切といえるでしょう。
準詐欺事件の弁護活動
Aさんは今回、警視庁下谷警察署で取調べを受けることになっています。
取調べを受けるにあたり、弁護士は黙秘権などの法的なアドバイスや、予想される質問内容に対する答え方などを提供することで依頼者様に不当に不利にはたらく内容の調書の作成を阻止します。
取調べを受ける前にご依頼いただくことによりその効果は最大に発揮されますが、時機が遅くなればなるほど、当初期待された結果につながりにくくなってしまいますので、お早めにご相談いただくことが何より重要です。
また、準詐欺事件では、被害者との示談交渉を行うことも重要な活動内容の一つです。
当事者間で直接交渉することは時間も労力もかかってしまい、その間に刑事手続きが進むことが懸念されます。
刑事事件に強い弁護士が間に入ることにより、円滑に交渉を進めることができ、なおかつ依頼者様にとってより利益となる内容での示談成立が期待できます。
これらの活動などにより、不起訴や執行猶予の獲得を目指すことができます。
刑事事件専門の弁護士
詐欺罪や準詐欺罪の被疑者となってしまった方、警視庁下谷警察署で取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、初回の法律相談を無料で承っておりますので、ご安心してフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
葛飾区の民家に窃盗目的で不法侵入 家人に見つかり逮捕
窃盗目的で民家に不法侵入し家人に現行逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
窃盗目的で民家に不法侵入
仕事をクビになって生活費に困ったAさんは、他人の家に盗みに入ることを企て、留守の多い葛飾区の民家に忍び込んで金品を窃取する計画を立てました。
そしてある日、家人が出かけたのを確認したAさんは、リビングの掃き出し窓を割って開錠して、民家に不法侵入し計画を実行にうつしたのです。
留守の家のリビングに不法侵入したAさんは、金目の物がありそうなタンス等を見つけ、その中を物色していたところ、忘れ物を取りに帰ってきた家人に見つかり、その場で取り押さえられてしまったのです。
家人によって取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた警視庁葛飾警察署の警察に引き渡されて、警察署に連行されました。
警察官の取調べを受けているAさんは、どのような刑事罰が科せられるのか不安でたまりません。
(フィクションです。)
不法侵入
窃盗の目的で留守の家に不法侵入すれば住居侵入罪となります。
住居侵入罪は、刑法第130条に定めらている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回の事件でAさんは、リビングの掃き出し窓を割って、閉まっていた鍵を開錠して家内に不法侵入しているので、この住居侵入罪の適用を受けるのは間違いないでしょう。
窃盗目的
Aさんは、家内から金品を窃取する目的で留守の民家に不法侵入しています。
この場合、まだ何も盗っていないAさんですが、「窃盗罪」の適用を受けるのでしょうか?
~窃盗罪~
まず「窃盗罪」について解説します。
窃盗罪とは、刑法第235条に定められている法律で、その内容は「他人の財物を窃取する(刑法抜粋)」ことです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、窃盗罪で起訴されて有罪が確定すればその法定刑内の刑事処分を受けることになります。
~窃盗未遂罪~
窃盗罪は、未遂であっても処分の対象となります。(窃盗未遂罪)
窃盗未遂罪とは、窃盗の着手が認められるが、他人の財物を窃取するという結果まで発生しなかった場合を意味します。
例えば、歩いている被害者が持っているカバンをひったくろうと、そのカバンを掴んだが、被害者がカバンを放さなかったので、カバンを窃取できなかった場合や、コンビニのレジの中にある現金を盗もうと、店員がレジから離れたすきにレジを開けたが、レジの中にお金がなくて目的を遂げれなかった場合などが窃盗未遂罪となります。
窃盗未遂罪が成立するには、窃盗の着手行為がなければなりません。
窃盗罪でいうところの着手時期は、財物についての他人の占有を侵害する行為を開始したとき、又は、これに密着した行為を開始したときです。
~Aさんに窃盗未遂罪は適用されるのか?~
Aさんは、金目の物がありそうなタンスの中を物色していたところを、帰宅した家人に取り押さえられています。
タンスの中を物色する行為は、財物についての他人の占有を侵害する行為に該当するでしょうから、Aさんに窃盗未遂罪が適用されるでしょう。
住居侵入罪と窃盗未遂罪の関係(牽連犯)
これまで解説したように今回の事件でAさんは、「住居侵入罪」と「窃盗未遂罪」の2つの犯罪に抵触しています。
この2つの犯罪行為は、手段と目的の関係にあり、このように複数の犯罪が、手段と目的の関係にあることを「牽連犯」といいます。
牽連犯は、刑事罰を科せる上では一罪として扱われ、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
ですからAさんの場合ですと、窃盗未遂罪の法定刑の適用を受けることとなりますが、侵入窃盗事件では、単なる窃盗事件より厳罰化される傾向にあるので注意しなければなりません。
葛飾区の不法侵入事件でお困りの方、侵入窃盗事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
刑事事件に関する無料法律相談、逮捕、勾留されている被疑者、被告人に刑事事件専門の弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
実子に対する略取誘拐事件
離婚協議中に実子を連れ去った略取誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
事件の概要
東京都渋谷区に住む会社員男性のAさんは、妻と別居し、離婚裁判の係争中です。
ある日、Aさんは、子供となかなか面会させてくれない妻の態度に腹を立て、小学校から一人で帰宅する子供を見つけ、抵抗する子供の腕を引っ張って車の助手席に乗せ、自宅へ連れ去りました。
その後、妻の通報を受けた警視庁原宿警察署の警察官がAさん宅を訪れ、子供は保護されました。
そしてAさんは、警視庁原宿警察署に未成年者略取罪で逮捕されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
未成年者略取罪とは
まず、Aさんが逮捕された未成年者略取罪の内容から解説します。
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されている法律です。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
※未成年者=20歳未満の者
刑法229条
第224条の罪(略)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと、「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
なお今回の事件では、子供がAさんの連れ去りに抵抗しており同意していないものと思われますが、未成年者が連れ去り行為に同意していた場合は未成年者略取罪は成立するでしょうか?
この点については、未成年者略取罪が何を保護しよう(守ろう)としているのかと関係があります。
すなわち、未成年者略取罪は、未成年者の自由のほか、親権者など保護監督者の監護権をも保護しようとしていると考えるのが通説、判例です。
よって、未成年者を誘拐した場合には、未成年者の行動の自由・権利を侵害するだけでなく、保護監督者が未成年を保護監督する自由・権利をも侵害したということになるのです。
そのため、未成年者が同意をしていたとしても、その保護監督者が同意しない以上は未成年者誘拐罪が成立し得るということになります。
共同親権者の子供の連れ去りに対する判例の考え
判例は、今回と同じような事件で、被告人の行為は、未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかとして上で、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解されるとしています。
そして、違法性が阻却されるかどうかは、当該行為(連れ去り行為)が社会通念上許容されるものであるかどうかという観点から判断されるべきところ、判例での事案では、
・被告人の連れ去り行為が、子どもの監護上必要とされるような特段の事情は認められない
・行為態様が粗暴で強引なものである
・子どもが自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児である
・その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難い
ことなどから、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することはできず違法性を阻却する事情を認めることはできないとしています。
以上の判例の考え方からすれば、共同親権者の連れ去り行為が直ちに未成年者略取罪に結び付くものではなく、当該行為が社会通念上許容されるものである場合は違法性が阻却され本罪が成立しない場合もあります。
仮に、こうした主張をする場合は、その主張を基礎付ける事実を的確に挙げていかなければなりません。
だからこそ、弁護士に相談・依頼することが重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
未成年者略取事件などの刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。
弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見サービスのご予約を電話で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。