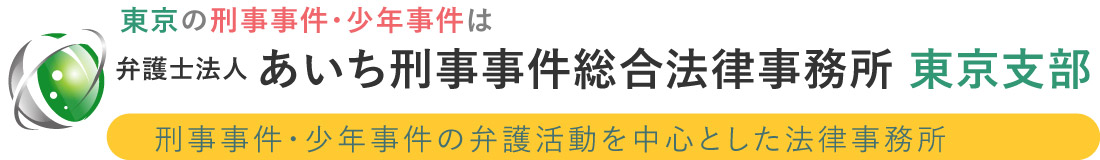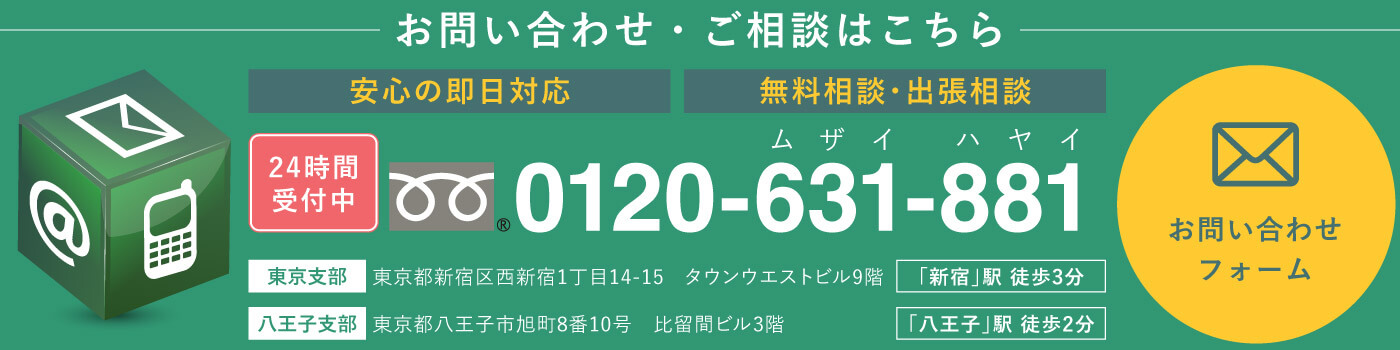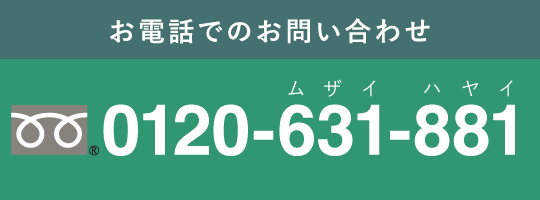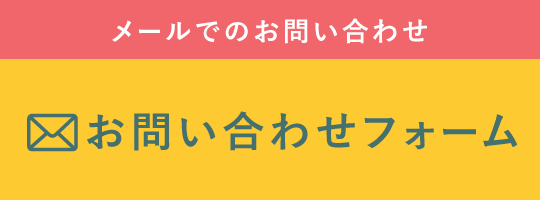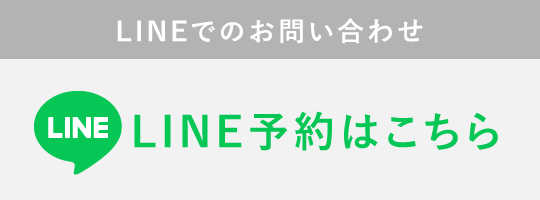Author Archive
警視庁高井戸警察署で弁護士接見
接見交通権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
あなたが逮捕された場合や任意取調べを受けた際、弁護士との面会を希望することがあると思います。弁護と面会などをする権利を接見交通権と言い、接見交通権は、憲法に由来する刑事手続上最も重要な基本的権利に属するとされています。
◇接見交通権について◇
接見交通権は、刑事訴訟法第1項に原則、同条第3項に例外が規定されています。
~刑事訴訟法第39条~
1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は~弁護人となろうとする者~と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員~は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
このように、刑事訴訟法第39条第1項は接見交通権の原則を規定し、第3項は捜査のため必要があるときは、接見等の日時・場所及び時間を指定することができる「接見指定」を規定しています。
この点について判例は、弁護人等から被疑者との接見等の申出があれば、
①原則としていつでも接見等の機会を与えなければならない。
②例外的に接見指定をできるのは、現に被疑者を取調べ中である場合などの「捜査に顕著な支障が生ずる場合」である。
③接見指定をする場合も、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見ができるような措置を採らなければならない。
としています。
◇具体的な事例◇
~接見に関する対応が違法となるケース~
―事例―
逮捕勾留中の被疑者に対する取調べの最中に、弁護人が警察署に行き、被疑者との接見を申し出た際に、捜査主任官は、捜査に顕著な支障を生ずる場合とは認められず、接見指定はしないこととしましたが、取調官は、供述調書の作成中であったことからその作成等を続け、接見の申出の連絡を受けてから取調べを終わらせるまで約10分間経過しました。
上記事例と同様の事例で、取調官の対応を違法とした裁判例があります。
この裁判例のポイントは、接見の申出を受けたならば接見指定をしない限りは捜査手続を中止るべきとの判断を明確にしています。
なお、被疑者を任意で取調べている最中に、弁護人となろうとする者が来署して被疑者との面会を求めた際に、捜査主任官が、面会の段取りをしているなどと曖昧な対応に終始した事案で、弁護人の面会希望を速やかに被疑者に伝えず、取調べを継続するなどした対応を違法とした裁判例があり、任意取調べでは、身体拘束中の場合と異なり接見指定の規定もありません。
ですから、あなたがもし任意取調べを受けた際に、弁護士との面会を希望しているにも関わらず、取調官がその面会を遅らせるため、様々な理由をつけてその機会を遅らせることは接見交通権の妨害になり、違法となり得るのです。
~接見に関する対応が適法とされるケース~
―事例―
留置場に勾留中の被疑者について、弁護人が休日に事前連絡なく来署して接見を申し出ました。検察官から接見指定がなされる場合があるとの連絡を受けていた看守が検察官に問い合わせしましたがなかなか連絡を取れませんでした。その後、検察官から接見指定をしない旨の連絡があり、それを弁護人に伝えて接見するまで、約40~45分を要して弁護人の接見開始が遅れました。
上記事例と同様の事例で、看守と検察官の対応が適法とされた判例があります。
この判例では、「接見等の申出を受けた者が、…指定の要件の存否を判断できないときは、権限のある捜査機関に対して申出のあったことを連絡し、その具体的措置について指示を受ける等の手続を採る必要があり、こうした手続を要することにより…接見等が遅れることがあったとしても、それが合理的な範囲内にとどまる限り、許容されているものと解する」としています。
事例では看守がすぐに検察官に問い合わせ、検察官は可能な限り速やかに回答しているので適法とされています。
なお、この事例においては、休日で当直の検察官を経由するなどの事情を加味して約40~45分間の遅延が「合理的な範囲内」と判断されたと思われますし、「通常の勤務時間内であるのに、担当検察官の不在を理由として接見指定を拒むことはできず、合理的時間が経過すれば、指定がなされなくても接見指定の行使がなかったものとして接見させなければならない。」、「合理的時間としては、せいぜい30~40分程度であろう。」などとの指摘があります。
東京で弁護人との接見に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁高井戸警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料 警視庁高井戸警察署までの初回接見費用:36,800円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁杉並警察署の選挙違反事件
公職選挙法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都杉並区に住むAさんは、工場で食品加工の仕事をしています。
昨夜は夜勤で徹夜仕事だったため、今日は朝方に帰宅して寝ていますが、寝始めてすぐに近所で街頭演説が始まり、その声で目が覚めてしまいました。
街頭演説は、来週に行われる杉並区議会議員選挙の候補者が行っているものでした。
最初は我慢していましたが、街頭演説が一時間以上にも及び、全く寝付けないことに苛立ったAさんは、演説会場に行き、そこで演説していた候補者に対して空き缶を投げつけたのです。
Aさんは、公職選挙法違反で現行犯逮捕され、事件はニュースで報道されてしまいました。
(この事件の内容はフィクションです)
◇公職選挙法違反◇
日本国内で行われる選挙を取り締まるための法律です。
この法律で規制される選挙(公職選挙)は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長(都道府県知事や市町村長)を選出するための選挙です。
公職選挙法では、選挙制度や、公正に選挙が行われるための様々な決まりが定められれています。
◇選挙活動とは◇
公職選挙法では、選挙活動に対して様々なルールが定められていますが、そもそも公職選挙法で規制されている選挙活動(運動)とは、どのような活動なのでしょうか。
公職選挙法では、選挙については定義されていますが、その活動(運動)には定義がありません。
そのため最高裁で、確定した
1.特定の選挙において
2.特定の候補者を当選させるために
3.有権者に働きかける行為
が、選挙活動(運動)と定義付けられており、選挙活動が許される期間は、公示日(告示日)から選挙が行われる日の前日までです。
よく街角で見かける街頭演説でも、選挙活動(運動)と、そうでない政治活動がありますが、選挙期間中に「●月●日に選挙では●●党の●●に清き一票をお願いします。」といった内容を演説していた場合は選挙活動となります。
◇選挙の自由妨害違反◇
選挙の候補者や、選挙運動に従事する者等の選挙活動に対して、暴行若しくは威力を加えて妨害した場合は、選挙の自由妨害となります。
Aさんのように、街頭演説を行っている候補者に対して空き缶を投げつける行為は当然のこと、街中の掲示板(候補者掲示板)に掲示されている候補者の選挙ポスターを破ったりして損壊した場合も、公職選挙法の自由妨害違反となります。
最近では、候補者の選挙ポスターにシールを貼った男が公職選挙法違反で警察に逮捕されています。
選挙の自由妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
Aさんの様に、人に向かって空き缶を投げつけた場合、もし人に当たって怪我をすれば傷害罪が適用されますが、当たらなかった場合、暴行罪の適用にとどまります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですので、同じ行為であっても、公職選挙法違反が適用された場合は厳罰化されます。
更に、選挙前になると、選挙区を管轄する警察署には捜査本部が設立されます。
その期間中、選挙違反に対する取り締まりが強化されますので、自由妨害違反であっても警察に逮捕される可能性は、単純な暴行や、器物損壊事件よりも高くなるので、注意しなければなりません。
ご家族、ご友人が警視庁杉並警察署に逮捕されてしまった方、公職選挙法違反等の選挙違反事件のご相談は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁荻窪警察署の時効事件
公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
自動車整備工をしているAさんは、数日前に、お客さんから「10年以上前に盗んだバイクだから大丈夫。」と言われて、バイクを無償で譲り受けました。
このバイクを修理して使用していたAさんは、東京都杉並区の路上を走行中に、信号無視をしてしまい、警視庁荻窪警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんのバイクの車体番号が削られていたことを不審に思った警察官から、バイクについて追及を受けたAさんは「10年前の話なので、もう時効が成立しているので大丈夫だと思って、バイクをお客さんから無償で譲受けた」等と、これまでの経過を警察官に説明したのです。
Aさんは、警視庁荻窪警察署に連行されて取調べを受けました。
(フィクションです)
◇公訴時効◇
刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなる公訴時効が規定されています。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。
①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たります。(窃盗罪の公訴時効は7年)
ですからお客さんが言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになり、バイクを盗んだお客さんに刑事罰が科せられることはありません。
◇盗品等無償譲受罪◇
盗品等無償譲受罪とは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
◇事件を検討◇
Aさんにバイクを譲ったお客さんの窃盗事件について公訴時効が成立しています。
しかしAさんは、盗品としてバイクを譲り受けているので、Aさんの行為に盗品等無償譲受罪が適用されてしまうでしょう。
公訴時効など刑事事件に関してご不明な点は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回の法律相談を無料で承っておりますので、法律相談ご予約専用ダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁四谷警察署に逮捕されるか
警視庁四谷警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、新宿二丁目でバーを経営しています。
一ヶ月ほど前に、バーのお客さんが酔いつぶれて、閉店時間を過ぎてもカウンターに座ったままイビキをかいて寝ていたので、Aさんは、店を閉めて帰る際に、お客さんをお店の外に出して、道路上に寝かせて帰宅しました。
そしてこのお客さんは、翌日の早朝に路上で死亡しているのが発見されました。
現場を管轄する警視庁四谷警察署は、保護責任者遺棄致死罪で捜査しており、近くの防犯カメラには、Aさんが、死亡したお客さんを路上に放置している映像が撮影されていたようです。
Aさんは、警察に逮捕されるか不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
(フィクションです。)
◇保護責任者遺棄致死罪◇
幼児や高齢者、身体障害者、病人を保護する責任がある者が、放置したり、生存に必要な保護をしなかったりして、要保護者を死亡させると、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法第219条に規定されている法律ですが、ここで法的刑は規定されておらず、保護責任者遺棄致死罪で起訴されて有罪が確定した場合は、刑法第218条に規定されている保護責任者遺棄罪の法定刑(3年以上5年以下の懲役)と刑法第204条に規定されている傷害罪の法定刑(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比較して、重い刑が言い渡されるので、実質、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「3カ月以上15年以下の懲役」となります。
保護責任者遺棄致死罪で客体となる要保護者とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者です。ここでいう「病者」とは、刑法第217条に規定されている「遺棄罪」でいうところの疾病のために扶助を必要とする者と同じ意味です。病気や傷害等により、肉体的、精神的に疾患のあることを意味し、その原因のいかん、治癒の可能性の有無、疾病期間の長短は問われません。薬物等の影響や、泥酔により意識を失っている者もこれに含まれます。
ちなみに、扶助を必要とする者とは、他人の助けがなければ日常生活を営むための動作ができない者で、生活資力を自給し得るかどうかは問われません。
続いて保護責任者遺棄致死罪で主体となるのは、上記客体を保護する責任のある者に限られます。保護責任は、法令の規定、契約、慣習、事務管理、条理によって発生する法律上のものでなければなりません。幼児の保護者や、老人の介護者は当然のこと、病人を看護する看護師や、幼児の面倒をみるベビーシッターも保護責任者遺棄致死罪の主体となるでしょう。
◇事例を検討◇
今回の事件を検討します。
まず、保護責任者遺棄致死罪が成立するための要件を整理すると
①老年者、幼年者、身体障害者、病者など他人の扶助を必要とする者(客体)
②上記(客体)を保護する責任のある者(主体)
③上記(客体)を遺棄するか、その生存に必要な保護をしない(行為)
④上記(客体)が死亡する(結果)
となります。
まず①に、今回の事件で死亡した、バーのお客さんが該当するかについてですが、最高裁の判例で、泥酔して高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者も、保護責任者遺棄致死罪の「病者」に当たるとされているので、該当する可能性が高いでしょう。
続いて②にAさんが該当するかについてですが、泥酔者に対する保護責任がしばしば問題となっており、これまで泥酔者に対する保護責任が認められた例としては、一緒に飲んでいて泥酔した仲間を、いったんは介抱されていたものの、その後放置して死亡させた事件や、タクシーの運転手が、タクシーの中で泥酔して寝込んだ客を、タクシーから降ろして路上に放置して死亡させた事件等があります。
これら過去の事件を考えると、自分の店で泥酔して寝込んでいる客に対して、店主であるAさんには保護責任があると考えるのが妥当ではないでしょうか。
最後に、店外に連れ出す行為について検討します。
保護責任者遺棄致死罪でいう「遺棄」とは、要保護者を場所的に移動させるだけでなく、置き去りのように、要保護者を危険な場所に遺留して立ち去る行為も含まれます。
Aさんは、泥酔して店内で寝ているお客さんを店外に連れ出して、路上に放置している行為は「遺棄」に該当するでしょう。
◇逮捕されるか◇
保護責任者遺棄致死罪は、人の生命という重大な結果が生じている事件ですので、逮捕されるリスクは非常に高いと考えていいでしょう。
また今回の事件ですと、泥酔した客を放置した路上の環境によっては、未必の故意での殺人罪が適用される可能性があるので、警察等での取調べには十分に注意しなければなりません。
警視庁四谷警察署に逮捕されるか不安のある方、保護責任者遺棄致死罪のような刑事事件に強い弁護士を東京都内でお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁四谷警察署までの初回接見費用:34,900円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁牛込警察署の交通事件
新宿区の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事故◇
東京都新宿区に住む主婦Aさんの夫は、トラックで東京都内のドラッグストアに商品を配送する、ルート搬送のドライバーをしています。
昨日は、いつも通り朝6時ころに自宅を出て出勤しましたが、普段帰宅する時間になっても帰宅しません。
心配になったAさんは、これまで何度も夫の携帯電話に電話しましたが、通じませんでした。
そして、夫が事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、今朝になって、近所の警視庁牛込警察署に夫の捜索願に行ったのです。
するとそこで、対応した警察官から「交通事故を起こして逮捕している。」ことを聞かされました。
Aさんは、すぐに交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇人身事故◇
車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。
◇過失運転致死傷罪◇
過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
◇逮捕されるの?◇
単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。
◇人身事故の刑事弁護活動◇
~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。
~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
ご家族、ご友人が人身事故で、警視庁牛込警察署に逮捕されてしまった方は、こういった刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁牛込警察署までの初回接見費用:35,200円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁代々木警察署で任意採尿
覚せい剤事件の任意採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは覚せい剤の使用事件で、これまで前科が2回あります。
最初は約10年前に捕まり、その際は執行猶予判決となりました。そして2回目は、最初の逮捕の翌年で、最初の執行猶予判決の際の懲役と併せて4年間、刑務所に服役しています。
出所後、しばらくは覚せい剤を絶っていたAさんですが、1年ほど前に偶然立ち寄ったバーで、外国人の密売人から覚せい剤を購入し、使用を再開してしまいました。
現在も、仕事で疲れが貯まっている時などに、このバーに行って外国人の密売人から覚せい剤を購入し、一月に1回か2回ぐらい覚せい剤を使用しており、最後に使用したのは3日前です。
そして昨夜Aさんは、仕事帰りに、東京都渋谷区の路上において、警視庁代々木警察署の警察官から職務質問されてしまい、警察署で任意採尿されました。
今後逮捕されることを覚悟しているAさんは、執行猶予付きの判決を希望し、そのために薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇任意採尿は拒否できる?◇
任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。そこで覚せい剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚せい剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。
◇強制採尿◇
任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚せい剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし強制採尿された経験のある方から聞くところによると、帰宅する旨を警察官に告げても数名で周りを囲まれたり、場所を移動しようとしても複数の警察官が付いてくるようです。
この様な、警察官の行き過ぎた行為が任意の範囲を逸脱しているとして、違法と認められた判例もありますが、この様な警察官の行為全てが違法と認められるわけではありませんので、強制採尿されるまでの警察官の職務執行に疑問のある方は薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
強制採尿は、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を執行されると、その許可状の効力をもって、病院まで強制的に連行されてしまい、それを拒否しても、実力行使で連行されるので注意しなければなりません。
◇覚せい剤使用事件の量刑◇
覚せい剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚せい剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる場合がほとんどです。しかし、前刑との期間が長期間開いている場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚せい剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内で、薬物事件での減軽を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が、覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、即日、逮捕された方まで、薬物事件に強い弁護士を派遣いたします。
初回法律相談:無料
警視庁代々木警察署までの初回接見費用:35,000円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁戸塚警察署の冤罪事件
冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員Aさんは、一昨日の朝方突然、東京都新宿区の自宅に押し掛けてきた、警視庁戸塚警察署の警察官に窃盗事件で逮捕されました。
警察官から、自身の氏名が記載されている逮捕状を見せられたのですが、読み聞かされた窃盗の逮捕事実に全く身に覚えのないAさんは、「知らない。私ではありません。」と答えましたが、その場で手錠をかけられて警視庁戸塚警察署に連行されました。
警察署でも取調べを受けていますが、Aさんは冤罪を訴えています。
しかし昨日、10日間の勾留が決定してしまい、Aさんの妻は、冤罪を暴く刑事事件に強い弁護士にAさんの刑事弁護を依頼しました。
その弁護士の活動によってAさんの冤罪が証明されて、逮捕から5日後にAさんは釈放されました。(フィクションです。)
◇冤罪事件◇
冤罪とは、身に覚えのない事件で逮捕される等して不当な手続きや刑事罰を受けることです。
警察は、被害者、目撃者の証言や、被害現場に残っている指紋やDNA,防犯カメラの映像など客観的な証拠から刑事事件の犯人を割り出します。
被害者や目撃者が犯人の姿を見ているような事件であれば、その様な人たちが犯人を確認して「間違いありません」となるので、全く無関係の方が逮捕される可能性は非常に低いものですが、窃盗事件の場合は、誰も見ていないところで犯行が行われるケースがほとんどです。その様な場合は、被害者の証言や、警察等の捜査当局で収集された客観的な証拠によって犯人が特定され、それらの証拠を基に裁判官に逮捕状が請求されるので、警察等の捜査当局の主観に基づいた捜査が行われる可能性があり、捜査員の思い込みによって犯人が特定されてしまう事もあります。
そういった背景から、Aさんのように、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕されるような冤罪の被害にあわれる方がいるのです。
◇冤罪事件で逮捕された場合の注意点◇
身に覚えのない刑事事件で警察に逮捕され際は
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
②早期に弁護士を選任する。
に徹することです。
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
警察に逮捕された場合、まず逮捕時に言い分を聞かれます。
警察官から逮捕される旨を告げられた際に、犯行に関与しているかどうかについて警察官に尋ねられるのです。その場で書類が作成されるわけではありませんが、後に警察官が「逮捕手続書」という司法書類を作成する際に逮捕時の言動が明記され、その内容が後の裁判で証拠となる場合があるので、逮捕時の言動には十分に注意すべきです。
そして逮捕後は、警察署に連行されます(引致)。そしてその後、警察官によって弁解録取が行われます。
弁解録取は、刑事手続き上は、取調べではないので黙秘権等の告知は行われませんが、この場合も黙秘権はあります。ですので、色々と警察官から追及されますが、「やっていない。」という事実のみを告げて、無理にそれ以上のことを供述する必要はありません。
弁解録取が終了すれば取調べが開始されます。
取調べにおいても無理に供述する必要はありません。関与していない事件で「やっていません。」と供述しても、警察官は、やっていない理由を説明するように申し向けてくるでしょうが、無理にその様な説明をする必要はなく、逆に、憶測や想像で話した内容が、警察官が作成する調書では、経験した事実のように記載されることがあるので発言には十分な注意が必要です。
自身の発言が、後の刑事裁判において、有罪か無罪を判断するための重要な証拠となる可能性があるので、供述に自信のない場合は「黙秘」する事をお勧めします。
②早期に弁護士を選任する
逮捕された本人が冤罪や誤認逮捕を訴えても、警察等の捜査当局は、その方を犯人として特定して逮捕しているので、なかなか受け入れてもらうことはできませんし、逆に、否認しているとして厳しい取調べ、追及を受けてしまいます。
少しでも早く冤罪を証明するには、刑事事件に関する専門知識、経験を有している弁護士に頼るのが一番でしょう。
逮捕されて身体拘束を受ければ、自ら弁護士に連絡を取ることはできませんが、警察官を通じて弁護士に連絡することは可能です。
もし知り合い等の弁護士がいる場合は、取調べを担当する刑事、留置場の看守などの警察官に「●●法律事務所の●●弁護士を呼んでくれ」と依頼すれば、その弁護士のもとに警察から連絡が入ります。
もし知り合い等の弁護士がいない場合は、一度だけであれば当番弁護士を呼ぶことができます。
上記と同じ要領で、当番弁護士を要請すれば、その当日、若しくは翌日には当番弁護士が面会に来てくれます。
また勾留が決定した場合は、同じ要領で国選弁護人を要請することができますので、私選の弁護人を選任する資力がない方でも、国選弁護人であれば無料で刑事弁護を依頼することができます。
私選、国選に関わらず、身に覚えのない事件で警察に逮捕されてしまった方は早急に弁護人を選任し適切な弁護活動をしなければ、不当な身体拘束が続き、場合によっては起訴されて有罪が確定しまう可能性があるので注意してください。
ご家族、ご友人が、警視庁戸塚警察署に冤罪事件で逮捕されてしまった方は、早急に刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁戸塚警察署までの初回接見費用:34,900円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁原宿警察署で正当防衛を主張
正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、東京都渋谷区の居酒屋で同僚とお酒を呑んで帰宅途中に、渋谷駅構内を歩いている時に、酔払いと肩がぶつかり口論となりました。
口論の際に、酔払いに胸倉を掴まれたことに腹が立ったAさんは、酔払いの身体を突き飛ばし、その後殴り合いの喧嘩に発展しました。
通報で駆け付けた駅員によって制止されたAさんは、ケンカ相手の酔払いと共に、警視庁原宿警察署に連行されて、警察官の取調べを受けています。
Aさんは「先に胸倉を掴まれたので振りほどくために身体を押しただけで、その後に殴られそうになったので、それを制止するために相手を殴った。正当防衛だ。」と正当防衛を主張しました。
しかしその後、酔払いが傷害罪の被害届を提出したらしく、Aさんは傷害事件の被疑者として扱われています。
(フィクションです)
◇正当防衛◇
まず正当防衛について解説します。
正当防衛は、刑法第36条に規定されている法律で、急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
正当防衛でいう「脅迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は直前に迫っていることをいいます。
したがって、過去の侵害や、未来の侵害に対しての反撃行為は、正当防衛とはいえません。
ただし、威力のある防犯装置を設置する場合、同施設が、現に発生した不正な侵害に対して相当な効果を発揮するものであれば、未来の侵害に対して備えたものでも正当防衛が認められる場合があります。
ここでいう「不正」とは、違法であればよく、有責であることまで必要ありません。
したがって、刑事責任能力のない者による侵害行為に対しても、正当防衛が成立します。
また「侵害」とは、生命・身体に危険を生じさせる違法な行為を意味し、故意・過失や、作為・不作為を問いませんが、積極的な侵害行為でなければなりません。
続いて「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する防衛行為が、自己又は他人の権利を守るために必要最小限度でなければなりません。
ここでいう「必要最小限度」とは、防衛行為により生じた結果ではなく、その防衛行為が必要最小限度であることを意味するので、防衛行為によって相手が重傷を負った場合でも、その防衛行為が必要最小限度であると認められれば正当防衛が成立します。
今回のAさんの行為については、胸倉を捕まえれたことに対して、相手の身体を突き飛ばした行為に対しては正当防衛が認められる可能性はありますが、殴られそうになったので先に殴ってそれを阻止しようとしたという行為は、上記したように、未来の攻撃に対する反撃行為に対しては「急迫不正の侵害」には該当せず、正当防衛は認められないでしょう。
◇相被疑傷害事件◇
今回の事件でAさんが、相手の暴行によって傷害を負っていた場合、Aさんは傷害事件の被害者であり、傷害事件の被疑者でもあります。
この様な事件を相被疑事件といいます。
Aさんのように相被疑の傷害事件に巻き込まれた場合、まず大切なのは、事件後速やかに、病院で診察を受け医師の診断書を得ることです。
よく相被疑の傷害事件に巻き込まれた方で、相手が被害届を出したら、こちらも被害届を出すという方がおられますが、その様な場合でも、診断書を得ないまでも、少なくとも医師の診察を受けておくことをお勧めします。
もし事件からしばらく経過して相手が警察に被害届を提出した場合、それから医師の診察を受けても、相手からの暴行で傷害を負ったかどうかの因果関係の立証が難しくなるばかりか、怪我が完治して診断書を得れない場合があるからです。
その場合、自身の行為は傷害罪の適用を受けますが、相手は、傷害罪よりも軽い暴行罪までしか適用されない可能性があり、その後の刑事罰に差異が生じてしまいます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、相被疑の傷害事件ですと、怪我の程度にもよりますが、ほとんどの事件が、不起訴処分か、略式罰金刑となります。
東京都渋谷区の刑事事件でお困りの方、相被疑傷害事件で正当防衛を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁原宿警察署まで初回接見費用:34,700円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁渋谷警察署の痴漢事件
痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
痴漢事件で逮捕
東京都内に住むAは、東京都渋谷区の公立中学校で教員をしています。
先日、通勤で利用している電車内で痴漢したとして、周りの人間に取り押さえられて現行犯逮捕されて、警視庁渋谷警察署に連行されました。
その後、Aさんは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAさんは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢事件には弁護士を
痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。
国選弁護人について
痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAさんについては、検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。
公務員の刑事事件
Aさんのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選での刑事弁護人を選任される場合は刑事事件専門の弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁荏原警察署に告訴されたら
告訴事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都品川区内で、月極駐車場やコインパーキングを管理、運営しています。
Aさんの管理する駐車場に自転車を無断駐輪する駅の利用客が絶えず、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくなりません。
そこでAさんは、事前に、駐車場の目立つ部分に「平成31年3月22日以降、駐車場内に無断駐輪している自転車を施錠します。施錠の解除には10,000円を徴収いたします。」という張り紙をして、実際に平成31年3月22日に、駐車場内に無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
その結果、それ以降は無断駐輪する自転車が激減しましたが、先日、警視庁荏原警察署から、この件で話を聞きたいと電話がかかってきました。
Aさんが警視庁荏原警察署に出頭したところ、警察官から、Aさんの行為は器物損壊罪に当たると言われました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇器物損壊罪~刑法第261条~◇
他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、「毀棄」と同義で、物質的に物そのものの形を変更させたり滅失させる場合だけでなく、広くその物の効用を害する一切の行為が損壊に当たります。
これまで効用滅失行為として器物損壊罪が適用された例としては
・看板を取り外して数百メートル先に放棄した事件
・他人の物置場所を勝手に変更した事件
・食器へ放尿し、食器を再び本来の目的に供することのできない状態にした事件
等があります。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。
◇親告罪◇
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
ちなみに平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。
◇親告罪の刑事弁護活動◇
親告罪には
・告訴がなければ起訴できない
・一度取消した告訴は、同じ事実で再び告訴できない
という決まりがあります。
そのため器物損壊罪のような親告罪の刑事弁護活動は、被害者との示談が最優先されます。
未だ被害者が告訴していない場合は、示談書の中で告訴しないことを約束してもらい、既に告訴してしまっている場合は、告訴を取消すことを約束してもらうのです。
そういった内容の示談を、起訴されるまでに締結することができれば、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けていても、刑事罰が科せられることはありません。
東京都品川区内の刑事事件でお困りの方、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荏原警察署までの初回接見費用:36,800円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。