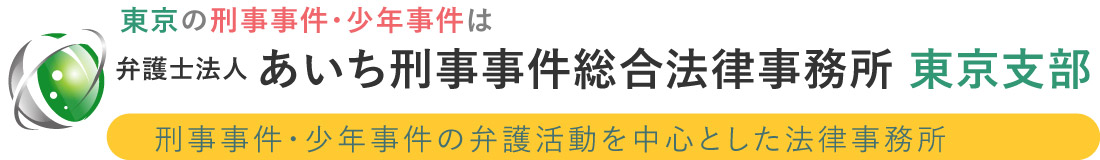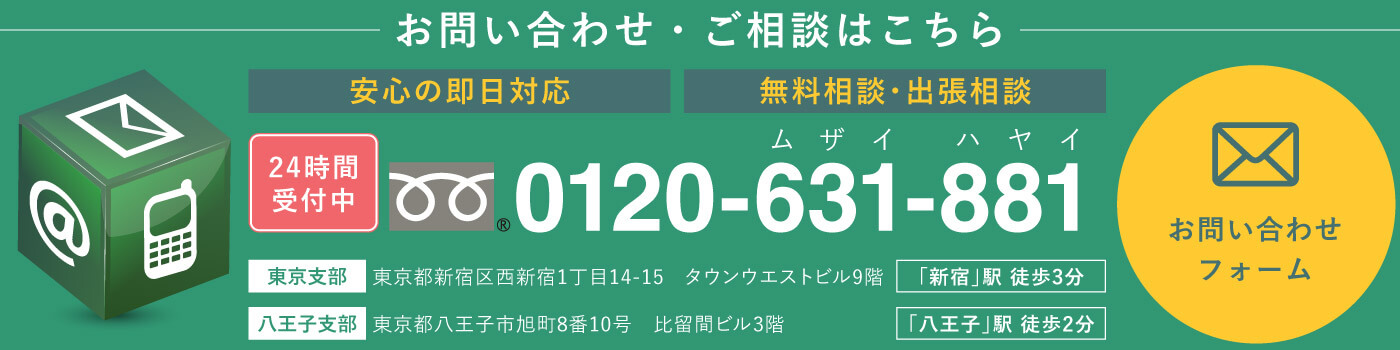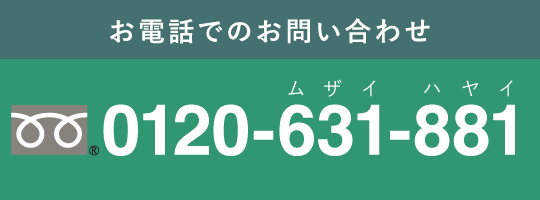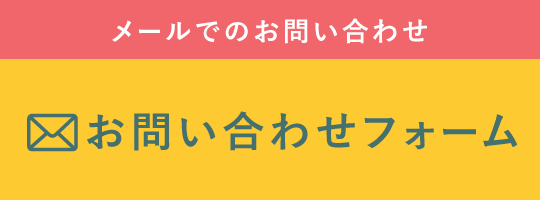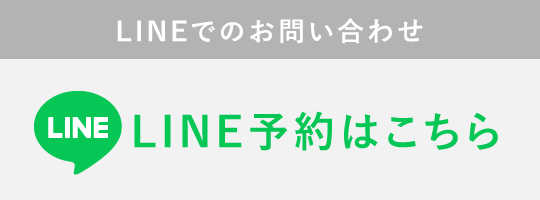本日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。
~刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)~
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。
~刑法第197条の2(第三者供賄)~
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。
~刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)~
第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。
~刑法第197条の4(あっせん収賄罪)~
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。