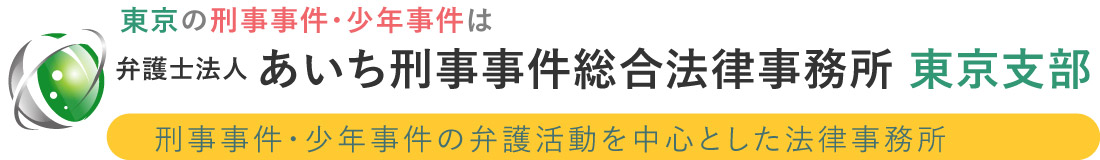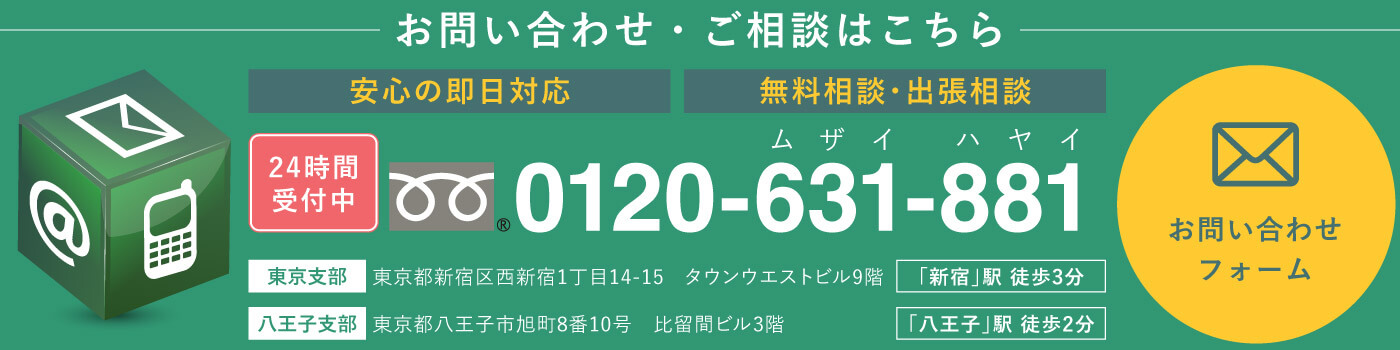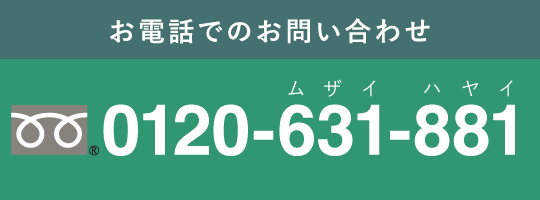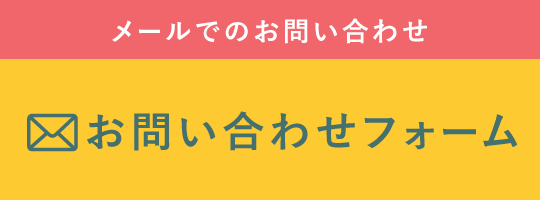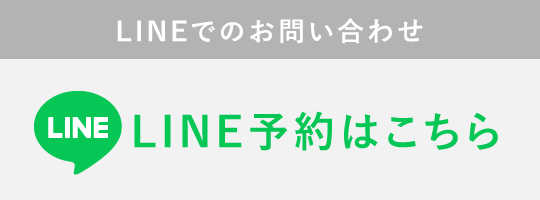Author Archive
お盆期間中の準強制性交事件で逮捕
お盆期間中に警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、お盆休みを利用して、卒業した大学のバスケットボール部のOB会に参加しました。
OB会は、現役大学生とOBチームでバスケットボールの試合をした後に、東京都港区の居酒屋で懇親会が開催されます。
OB会には、女子マネージャーも含めて多くのOB,OGが参加していました。
Aさんもバスケットボールの試合に参加し、その後の懇親会にも同級生らと参加しました。
その宴席で、たまたまAさんの隣に座った現役チームの女子マネージャーと意気投合したAさんは、この女子マネージャーに次々とお酒をついで飲ませました。
Aさんは、女子マネージャーが自分に気があると思い込んで、懇親会の後にカラオケに誘おうと思っていたのですが、途中で女子マネージャーが酔いつぶれて眠り始めたのです。
その様子を見ていた仲間から、責任をもって女子マネージャーを自宅に送り届けるように指示されたAさんは、親睦会の後に女子マネージャーをタクシーに乗せて、自分が宿泊している、東京都港区のビジネスホテルに連れ込んだのです。
移動の途中、何度か目を覚ました女子マネージャーに「一緒にホテルに行こう」と声をかけましたが、女子マネージャーが明確に拒否しなかったので、Aさんは了承を得たものだと思い込んでいました。
タクシーを降りたAさんは、女子マネージャーを抱えるようにして自分の部屋に連れて行き、ベッドに寝かせました。
そしてAさんは女子マネージャーにキスをしましたが、全く嫌がる様子がなかったので、そのま服を脱がし性交渉に及んだのです。
その翌日、目を覚ますと女子マネージャーを部屋におらず、Aさんもホテルをチェックアウトしました。
しかし後日、Aさんは、警視庁愛宕警察署に準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
◇準強制性交等罪◇
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をすることで、起訴されて有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ、5年以上の有期懲役が科せられます。
通常の強制性交等罪が、性交等を行う手段として「暴行又は脅迫」と定めているのに対して、準強制性交等罪については
①心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ
②心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせる
ことによるものとしています。
「心神喪失」とは、精神的または生理的な障害によって正常な判断能力を失っている状態といい、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病等により被害者が行為の意味を理解できない場合がこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しつつも医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などがあります。
心神喪失・抗拒不能の程度についてですが、完全に不可能であることを必要とせず、反抗が著しく困難であればよいとされます。
①心神喪失・抗拒不能に乗じて
既に被害者が心神喪失・抗拒不能にある状況を利用することを指します。
例えば、被害者の高度の精神沈滞状況を利用した場合、睡眠中や泥酔状態の利用などがあげられます。
②心神喪失・抗拒不能にさせる
被害者にお酒を飲ませて泥酔させたり、医師の医療行為を装い治療と誤信した被害者に性交等を行う場合などです。
被害者の無知、困惑、驚愕等や、加害者との関係などといった被害者のおかれた特別の状況を利用して行為が行われた場合にも本罪が成立する可能性があります。
◇故意◇
準強制性交等罪の成立には、故意がなければなりません。
つまり、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあることを認識して行為に及んでいること、そして被害者の同意がないことの認識が必要となるのです。
被害者が心神喪失・抗拒不能の状態であったことが明らかであっても、それを加害者が認識していない場合や、被害者が同意していないことを加害者が認識していない場合には、準強制性交等罪が成立しない可能性があります。
ただ、これらは内心の問題となるので、単に「知らなかった。」「同意があったと思っていた。」と主張するだけは足りず、客観的な証拠によって証明する必要があるでしょう。
準強制性交等罪等の性犯罪でお困りの方や、ご家族、ご友人が警視庁愛宕警察署に逮捕されてしまった方は、お盆期間中も営業している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
痴漢事件の警察捜査
痴漢事件の警察捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは通勤で電車を利用していますが、昨夜、帰宅のために利用した電車は満員でした。
そして自宅の最寄り駅で電車を降りようとしたところ、Aさんは、前に立っていた女性に「あなた痴漢したでしょう。」と言われて手を掴まれ、駅長室に連れていかれました。
Aさんは「やっていない。」と言っていますが、駅長が呼んだ警視庁三田警察署の警察官によって、警察署に連行されました。
Aさんは警察署で、刑事さんの取調べを受けましたが、痴漢の容疑を否認しています。
取調べを終えたAさんは、刑事さんから「今後も警察署に呼び出すので出頭するように。」と言われました。
Aさんは、今後、どのような捜査が行われるか不安で、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇警察の捜査◇
~取調べ~
痴漢事件のような刑事事件において、犯人(被疑者)が警察署で受ける捜査は、警察官の取調べがメインとなります。
基本的に取調べは、取調べと言われる密室で、取調官と一対一で行われます。(補助官が同席して一対二の場合もある。)
法律的な根拠はありませんが、捜査情報の漏洩を防止するという観点から、取調べを録音することは許可されません。(一定の重い犯罪の被疑者として取調べを受ける場合は、専用の機材を用いて録音録画される。)
取調べにおいて供述した内容は、取調官が「供述調書」という司法書類に記載して文章になります。
そして、完成した供述調書を読み聞かせられた上、実際に供述者本人が内容を確認して、署名、指印(押印)することによって、供述調書が完成します。
当然、内容を確認した時に訂正を申し出ることができますし、納得ができなければ署名、指印(押印)を拒否することもできます。
~再現見分~
事件の内容にもよりますが、取調べによって犯行状況が明らかになれば、犯行状況の再現見分が行われます。
警察官が被害者役をして、どの様に犯行に及んだのかを再現し、その状況を警察官が写真撮影するのです。
再現見分の目的は、犯行状況を明らかにすることですので、普通は、犯行時の状況が細かく再現された場所で再現見分は行われますが、実際の犯行場所において、再現見分が行われる場合もあります。
~引き当たり捜査~
警察官を犯行場所や、事件関係先に案内することを、引き当たり捜査と言います。
再現見分と同じように、警察官を案内している状況などを写真撮影されます。
~その他~
被疑者指紋やDNAを採取されたり、被疑者写真を撮影される他、否認している場合は、ポリグラフ検査をされることもあります。
ポリグラフ検査とは、俗に言われる「うそ発見器」のことですが、この検査は、強制ではなく任意ですので、拒否することができます。
◇注意点◇
上記したような警察で行われる捜査は決して強制されるものではなく、拒否することもできます。
そこで、取調べにおいて被疑者(捜査を受ける人)に与えられている権利をいくつか紹介します。
~黙秘権~
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
~増減変更申立権~
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
~署名押印拒否権~
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。
ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。
取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
~出頭拒否権、退去権~
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。
また、取調べ中は、いつでも取調べ室から退去することができます。
本日紹介させていただいた警察の捜査はごく一部で、警察がどのような捜査をするのかは事件によって異なります。
しかし、どんな事件にも共通して行われるのは被疑者に対する取調べです。
取調べの内容は、その後、有罪か無罪かを判断する大きな証拠となりますので、警察の捜査に対して不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を無料で承っておりますので、刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
児童買春事件に強い弁護士を探す
児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、今朝、出勤しようと自宅を出たところ、自宅前で待ち構えていた警視庁昭島警察署の警察官に約1年前にに起こした児童買春事件で逮捕されました。
確かにAさんは、約1年前に、インターネットのSNSで知り合った女性に現金3万円を渡して性交渉していました。
当時、相手の女性からは18歳だと聞いていたので、その様な行為に及んだのですが、警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、警視庁昭島警察署に連行された際に、その事を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)
◇児童買春事件◇
児童買春とは、18歳に満たない児童(性別を問わない)等に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対して性交等することをいいます。
~「対償」とは~
児童が性交等することに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額は問われません。
現金以外では、プレゼントを渡すことは当然のこと、食事をご馳走したり、児童やその親の雇用を約束した場合でも、その価値や、経済的な利益などによっては対償と認められる場合があります。
ちなみに、対償は性交に先立って供与又は供与の約束がなされていることが必要です。
性交後に初めて児童から請求があって供与した場合は、児童買春に当たらない可能性が高いです。
~「性交等」とは~
性交若しくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることです。
性交や性交類似行為については、それ自体が、行為者の性欲を満足させるこういであるので「性的好奇心を満たす目的」は必要とされませんが、性器を触ったり、触らせる行為については「性的好奇心を満たす目的」が必要となります。
~年齢の不知~
児童買春を規制している児童買春・児童ポルノ処罰法では「児童の年齢を知らないことを理由として児童買春行為の処罰を免れることはできないが、過失がない時は、この限りではない。」ことが明記されています。
これは、年齢の不知の過失を処罰する趣旨を規定したものです。
つまり、買春行為に際して、相手方の年齢を可能な限り調査して年齢を確認する義務を尽くしたにもかかわらず、児童であることを知り得なかったことを立証しない限り、処罰を免れない旨を規定しているのです。
買春行為の相手方の、具体的な年齢調査の程度や方法については、事件ごとに検討されるでしょうが、一般的には児童に年齢を確認したり、身体の外形的な発育状態によって18歳以上であると信じたとしても調査義務を尽くしたとはいえないでしょう。
例えば運転免許証など、年齢が確認できる身分証で年齢を確認するまでしていれば、例え相手が18歳未満であっても、年齢の不知で児童買春罪の適用を免れる可能性があります。
◇弁護士を要請する方法◇
急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。
①知っている弁護士がいる方
事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。
②知っている弁護士がいない方
知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。
・当番弁護士を要請する
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。
・国選弁護人を要請する
勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。
警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件で、ある朝急に逮捕される場合もあります。
どの様方でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
東京都昭島市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が警視庁昭島警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁昭島警察署までの初回接見費用:37,900円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
交通事故で歩行者が書類送検(重過失致死罪)
歩行者が加害者となった交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、武蔵野市の自宅近くにある居酒屋でお酒を飲んで、相当酔払ってしまい、徒歩で帰宅している途中の交差点の横断歩道を、信号無視で横断してしまいました。
そして、青信号で交差点に進入してきたバイクに衝突される事故にあったのです。
この事故でAさんは首の骨を折る重傷を負いましたが、バイクを運転していた男性は、転倒して地面に叩きつけられた衝撃で後頭部を強打し、死亡してしまいました。
Aさんは、事故から約2カ月もの間、病院に入院していましたが、退院後に警視庁武蔵野警察署に呼び出されて取調べを受けました。
そしてその後、「重過失致死罪」によって書類送検されたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)
◇交通事故◇
一般的に交通事故と言えば、車やバイクといった乗り物同士の事故や、そういった乗り物と歩行者の事故ですが、乗り物と歩行者の交通事故の場合は、一般的に交通弱者と呼ばれる歩行者が被害者となり、オートバイ(50CC原付バイクを含む)や車などのが加害者となって、過失運転致死傷罪が適用される場合がほとんどですが、最近は自転車による交通事故についても刑事事件化される事故が目立つようになり、その場合、自転車の運転手に対しては、過失傷害罪や、重過失致死罪が適用されています。
しかし今回の事件のように、歩行者が被疑者として扱われる事故は極めて異例ではないでしょうか。
◇重過失致死傷罪◇
重過失致死傷罪とは、刑法第211条に、業務上過失致死傷罪と共に規定されている法律です。
この条文によると、重過失致死傷罪は「重大な過失によって人を死傷させる」ことで、その法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~「過失」とは~
この法律でいう「過失」とは、行為当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為若しくは不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることを意味します。
ちなみに注意義務の有無は、通常人を標準として決すべきだというのが司法の判断です。
~「重過失」とは~
重過失の「重」は、結果の発生にかかるものではなく、注意義務違反にかかる言葉です。
つまり、相手に重傷を負わせたり、相手を死亡させたりといった重大な結果が生じた事件であっても、注意義務違反が軽微であった場合ですと、重過失致死傷罪ではなく、過失傷害罪(刑法第209条)や、過失致死罪(刑法第210条)が適用されます。
~因果関係~
因果関係とは、原因と結果の関係のことですので、重過失致死傷罪でいう因果関係は、行為者の重大な注意義務違反の行為が原因となって、相手に致死傷を負わせるといった結果が生じなければ、重過失致死傷罪は成立しないことになります。
行為者は、この因果関係まで具体的に予見する必要はなく、少なくとも行為者に、結果発生の予見の可能性が認められれば、過失犯としての刑事責任が問われることになります。
◇重過失傷害罪は非親告罪◇
過失傷害罪は、親告罪ですので、被害者等の告訴権者による告訴がなければ、検察官は起訴して、被疑者に刑事罰を追及することはできません。
しかし、過失致死罪や重過失致死傷罪は、非親告罪です。
つまり被害者等の告訴権者による告訴がなくても、警察等の捜査機関が捜査をした結果によっては、検察官は、被疑者を起訴して刑事責任を追及することができます。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故に関するご相談も無料で承っております。
武蔵野市内の刑事事件でお困りの方、交通事故を起こして検察庁に書類送検されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
星野昌季弁護士のコメントが朝日新聞に掲載されました
朝日新聞に、マイナンバーサイトのサーバー利用率に関する星野昌季弁護士のコメントが掲載されました。
参照
https://www.asahi.com/articles/ASM7F3TKPM7FUUPI002.html
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
横領罪で刑事告訴されたら
横領罪で刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、数ヶ月前に東大和市内のレンタカー会社で乗用車を一台レンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せずに、レンタカー会社に何の連絡もせずに無断で、そのまま乗り続けていました。
レンタカー会社から、横領罪で警視庁東大和警察署に刑事告訴した旨の連絡を受けたAさんは、今後のことが不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇横領罪◇
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件で、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、そのレンタカーは、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」となります。
このレンタカーを、レンタカー会社の許可なく、自分の都合で使用し続けているAさんの行為は、「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
また、仮に契約時から、Aさんに、レンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙して契約をしてレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べにおいての供述内容などによって決定するので、横領罪等の刑事事件を起こしてしまった方は、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
◇刑事告訴◇
告訴とは刑事訴訟法第230条に定められている刑事手続きの一種です。
告訴とは、被害者等が捜査機関に対して、犯罪被害を申告し、犯人の刑事処分を求めることで、通常は、警察署や検察庁に告訴状を提出する方法によって行われています。
告訴を受けた警察は、速やかに告訴された事件を捜査して、証拠品と共に検察官に送致しなければなりません。(刑事訴訟法第242条)
告訴できるのは、被害者だけではありません。
被害者の法定代理人や、被害者が死亡している場合は、被害者の配偶者や、直系の親族や兄弟も告訴権があるので、告訴することができるのです。
~被害届を警察に提出するのと何が違うの?~
犯罪の被害者等が、事件の捜査と犯人の処罰を望んで、警察等の捜査機関に対して被害を届け出るという意味では、捜査機関が犯罪捜査を開始する端緒となるので、告訴は、被害届を警察に提出するのと大きな違いはありません。
しかし、上記のように警察等の捜査機関は、告訴事件に関しては、犯罪を捜査して検察庁に送致する義務を負います。つまり、被害届によって認知した事件に関しては、警察が捜査を開始し、犯罪事実を立証できない場合や、早期に被害者と犯人が示談した場合など、早期に捜査が終結してしまえば、検察庁に事件が送致されない可能性があります。しかし告訴された事件については必ず検察庁に送致されるということです。
また刑事告訴には、親告罪(器物損壊罪、過失傷害罪、名誉毀損罪等)に当たる事件に限りますが、犯人を知った日から6カ月間と、告訴できる期間が定められていたり(刑事訴訟法第235条)、一度告訴を取消すと再び同じ犯罪事実で告訴をすることはできない(刑事訴訟法第239条1項)といったルールがあります。
◇刑事告訴されたら◇
刑事弁護活動には様々な内容がありますが、軽減を求めるうえで最も有効的な活動は、被害者との示談です。
当然、被害者の存在する事件でしか示談できませんが、刑事告訴される事件は、必ず被害者の存在する事件ですので、示談によって刑事罰を軽減させることが可能です。
そして、その示談の内容に「告訴を取り下げる」内容を含むことができれば、絶対的に、刑事罰を免れることができるのです。(起訴後に示談した場合はこの限りでない。)
ですから刑事告訴された場合は、早期に弁護士を通じて被害者と示談することをお勧めします。
東大和市内の刑事事件でお困りの方、横領罪で刑事告訴された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
処分保留で釈放
処分保留の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都小平市に住む主婦のAさんには、小学校2年生と4年生の子供がいます。
子供が言うことを聞かないことに腹を立てたAさんは、日常的に子供たちに対して手を上げて躾(しつけ)をしていました。
そして、その躾(しつけ)がいき過ぎてしまい、ある日Aさんは、兄弟喧嘩を止めに入った際に、子どもたちを殴りつけてしまい、二人の子供の顔にアザができるほどの怪我を負わせてしまったのです。
翌日、子供たちの顔にアザができていることに気付いた小学校の先生が、児童相談所に通告し、子供たちは児童相談所に保護されてしまいました。
そして、1週間ほどして、Aさんは子供たちに対する傷害容疑で警視庁小平警察署に逮捕されてしまったのです。
Aさんは20日間勾留された後に、処分保留で釈放されました。
(フィクションです。)
◇躾(しつけ)のつもりが刑事事件に発展◇
躾(しつけ)として子供に対して手をあげることが、昔であれば、親として当然の行為だと肯定される場合がありましたが、最近は、虐待として刑事事件化されるケースが増えているようです。
特に、学校等から児童相談所に報告された場合は、児童相談所の職員が被害者となる子供から聞き取りを行い、暴行の事実が確認されれば管轄警察署に報告されるようです。
そしてその間、子供は児童相談所に保護されるケースがほとんどで、親御さんは、子供が帰宅しない不安の中で、警察の捜査を受けることとなり、Aさんのように逮捕されることも珍しくありません。
逮捕されるかどうかは、警察等の捜査当局が、裁判官に対して逮捕状を請求する否かによりますが、その判断は、逮捕の要件や必要性に加えて、子供に対する暴行の頻度や程度、子供の傷害の程度によって検討されているようです。親子という何より身近な関係であるが故に、罪証隠滅におそれが強いと判断されて逮捕されることもあるようです。
◇暴行・傷害事件◇
親の子供に対する暴力は「虐待」と表現され、教師の生徒に対する暴力は「体罰」と、そして上司から部下に対しる暴力は「パワハラ」と表現されていますが、何れのケースであっても、基本的に人に対する暴力は、刑事手続き上「暴行罪(刑法第208条)」が適用され、それによって相手が怪我をすれば「傷害罪(刑法第204条)」が適用されます。
※行為態様によっては、暴力行為等処罰に関する法律違反や、逮捕、監禁罪など別の法律が適用される場合もありますので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士に相談してください。
~暴行罪(刑法第208条)~
人を暴行すれば「暴行罪」の適用を受けます。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
躾(しつけ)のつもりでも、刑事事件化されて暴行罪の適用を受けた場合は、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなり、前科が付いてしまいます。
~傷害罪(刑法第204条)~
暴行によって相手に傷害を負わせてしまえば「傷害罪」の適用を受けます。
「躾(しつけ)のつもりで手を上げた。怪我をさせるつもりはなかった。」と言いましても、故意的な暴行行為がある場合は傷害罪に抵触する可能性が非常に高いでしょう。
なお、傷害罪の法定刑は「15年以下の罰金又は50万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなり、前科が付いてしまいます。
◇処分保留◇
警察等の捜査機関から事件(被疑者)の送致を受けた検察官は、起訴するかどうかを判断します。
~起訴~
起訴された場合は、公開される裁判(公判)で刑事処分が決定する場合と、罰金を支払えば裁判は行われずに、全ての刑事手続きが終了する略式起訴(罰金)の場合があります。
~不起訴~
検察官が起訴しないことを「不起訴」といいます。
不起訴の理由は様々ですが、不起訴は、刑事罰が科せられないことを意味しますので前科は付きません。
~「処分保留」とは?~
被疑者が、勾留によって身体拘束を受けている場合、その勾留期間は10日~20日と法律で決まっています。
そして検察官は、この勾留の満期時に起訴するか否かを決定しなければなりません。
しかし、様々な事情(主に起訴するだけの証拠が揃っていない)があって検察官が勾留の期間内に、起訴するかどうかの決定ができない場合に「処分保留」となって、勾留されていた被疑者は釈放されます。
「処分保留」となった場合は、その後も引き続き捜査が継続されて、新たな証拠が出てきた場合には、起訴されることもありますが、既に被疑者が釈放されていることもあり、捜査を尽くしても、新たな証拠が出てくる可能性は低く、最終的には不起訴処分になるケースがほとんどのようです。
小平市で、子供に対する躾(しつけ)が刑事事件化されてしまった方、警察に逮捕、勾留されている方の、処分保留による釈放を希望される方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
タバコの火の不始末が火災に(失火罪)
失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
東京都赤坂の雑居ビルに入っている飲食店で働いているAさんは愛煙家で、職場でも休憩時間や仕事終わりに喫煙しています。
いつも厨房の奥にあるスペースで喫煙して、灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電の時間が迫っていたので急いでおり、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思い、ゴミ箱に灰皿の吸い殻を捨ててしまいました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、飲食店の厨房と店舗の一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、警視庁港警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
本日は、Aさんが起こした失火事件を検討します。
◇失火罪~刑法第116条~◇
失火罪は
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。
~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。
◇重過失失火罪~刑法第117条の2後段~◇
失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。
◇事件を検討◇
一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消化するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば作業に従事することができます。
東京都港区の失火事件でお困りの方、失火罪や重過失失火罪でお悩みの方は、刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
被害者との示談に強い弁護士
刑事事件の被害者との示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
窃盗事件や、暴行・傷害事件、盗撮や痴漢・強制わいせつ罪等の性犯罪など、被害者の存在する刑事事件を起こしてしまった方で、その後の刑事処分の軽減を求めている方は、被害者と「示談」することで、その後の刑事処分が軽減される可能性があります。
被害者との示談を希望している方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
示談に関する法律相談のご予約は
0120-631-881(24時間・年中無休)
までお気軽にお電話ください。
◇示談とは◇
刑事弁護活動の一つに被害者との示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」ですが、刑事事件の弁護活動における示談とは、主に、被害者等に対する謝罪の意思、被害者とへの被害弁償に関する内容、その他の条件を明確にし、その内容を示談書にまとめて約束することです。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。
◇示談の効果◇
~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、警察官の職務質問等によって捜査機関が独自に事件を認知する場合や、被害者の届出や告訴・告発によって認知する場合など様々です。
捜査機関が独自に事件を認知した場合は、当然のこと弁護士が介入して事件の認知を阻むことはできませんが、被害者の届出等による場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者等に被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する必要がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰を受けることはありません。
~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことが可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は非常に高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に略式罰金や起訴の決定をする検察官もいます。
~起訴後~
起訴され後の、刑事裁判の最中に示談が成立した場合でも、その示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になるのです。
起訴後に成立した示談であっても、その内容によっては、執行猶予判決を獲得できたり、刑の減軽につながります。
◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇
~示談できない事件~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、薬物事件等の被害者の存在しない事件では、そもそも示談という概念がありません。
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。
~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできませんし、被害額が高額になる財産犯事件や、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど、被害者感情が強くなるので、示談が成立する可能性は低くなるでしょう。
東京都内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談に関する法律相談:初回無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
(DV防止法)保護命令違反で逮捕
DV防止法の保護命令違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都豊島区に住む会社員のAさんは、仕事のストレスから日常的に妻に対して暴力を振るっていました。
妻の顔に傷があるのに気付いた近所の住民が、警視庁巣鴨警察署に届け出たことから、Aさんの妻は警察で事情聴取を受けることになりました。
Aさんの妻は警察官から傷害罪の被害届を出すように勧められましたが、Aさんが逮捕されてしまうことを危惧した妻は被害届を出さずに、DV防止法による保護を申立てました。
その結果Aさんに対して退去命令が発せられました。
しばらくは命令に従って妻と住んでいた家を出て実家に戻ったAさんでしたが、妻が浮気をしているのではないかと不安になり、無断で妻が住んでいる家の周りを徘徊しました。
徘徊しているのを近所の住民に目撃されたAさんは、通報で駆け付けた警視庁巣鴨警察署の警察官に、保護命令違反で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇DV防止法◇
DV防止法が施行されるまで、配偶者に対する暴力行為については、刑法の暴行罪や傷害罪を適用して取締るしか方法がない故に、そのような配偶者に対する暴行、傷害事件は、被害が潜在化しやすく、十分に法的な対応ができていませんでした。
そうした状況から、DV被害の防止と、被害者の保護を図ることを目的に施行されたのが「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」です。
◇「DV」とは◇
DV防止法でいう「DV(ドメスティックバイオレンス)」とは、配偶者からの身体に対する暴力又は、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。
ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」も含まれ、男性、女性の別を問いません。
また離婚後も引き続き暴力を受ける場合も、配偶者の概念に含まれますし、生活の本拠を共にする交際する相手からの暴力及びその被害についても、DV防止法の対象となります。
「身体に対する暴力」とは、いわゆる刑法でいうところの暴行、傷害罪に当たる行為です。「~準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とは、脅迫に当たるような言動の他、いわゆる精神的暴力や性的暴力が該当します。
◇保護命令◇
DV防止法でいうところの保護命令には以下のものがあります。
~接近禁止命令(同法第10条1項1号)~
接近禁止命令は、加害者が被害者の住居や、その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他、その通常所在する場所の付近を徘徊することを6カ月間禁止する命令です。
~退去命令(同法第10条1項2号)~
退去命令は、加害者に2カ月間、被害者と共に生活の拠点としている住居から退去すること及び、その住居の周辺を徘徊することを禁止する命令です。
~電話等禁止命令(同法第10条2項)~
加害者から被害者に対して、面会を要求したり、深夜の電話やファックス送信、メール送信などの一定の迷惑行為を禁止する命令です。
~子供への接近禁止命令(同法第10条3項)~
被害者が加害者に会わざるをえなくなる状態を防ぐために、必要があると認められる場合に、被害者と同居している子供の身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつく事を禁止する命令です。
~親族等への接近禁止命令(同法第10条4項)~
被害者が加害者に会わざるをえなくなる状態を防ぐために、必要があると認められる場合に、その親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をうろつく事を禁止する命令です。
◇保護命令違反◇
裁判所から、上記した保護命令の何れかが発せられたにもかかわらず、この命令に違反した場合は保護命令違反となり、有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
DV防止法が、被害者の保護を目的にしている点から、保護命令違反が明らかになった場合は、被害者の安全を優先するために、加害者は逮捕される可能性が十分に考えられるでしょう。
東京都豊島区の刑事事件でお困りの方、DV防止法の保護命令に違反してしまった方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、東京の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。