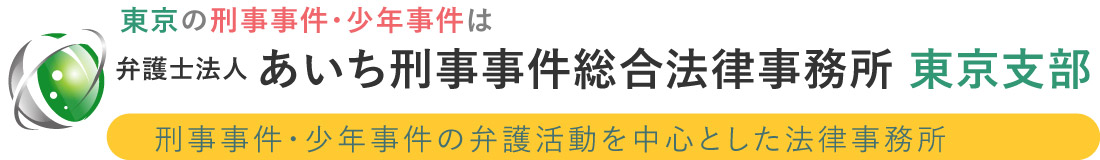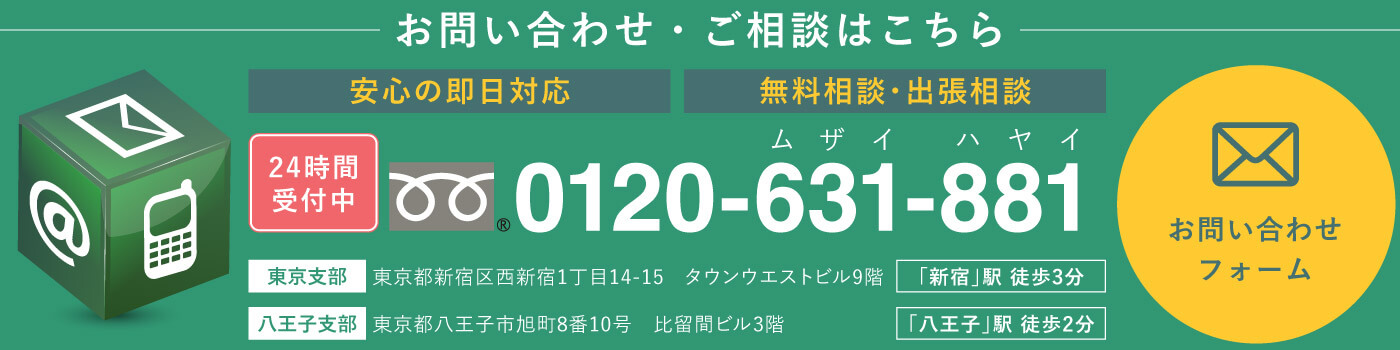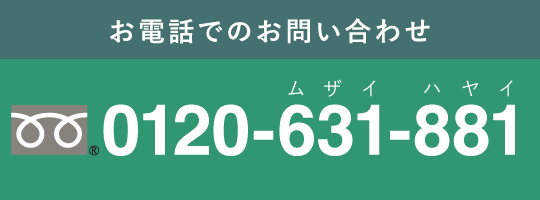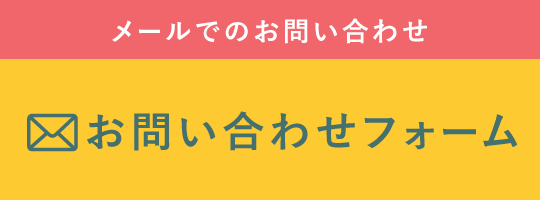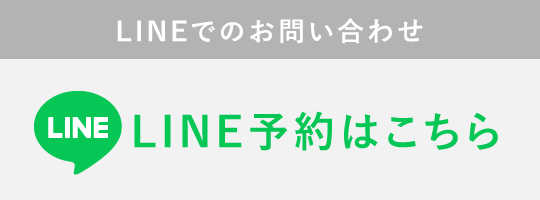Author Archive
公務員による暴行事件 被害者と示談を目指す
公務員が起こした暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
公務員のAさんは、東京都昭島市の繁華街の居酒屋において、隣席で飲んでいた男性と些細なことから口論になり、男性の左肩を右こぶしで一回殴ってしまいました。
店員の通報で駆け付けた警察官によって、警視庁昭島警察署に任意同行されたAさんは、取調べを受けましたが、その日のうちに帰宅することができました。
2回目の取調べがあるとのことなので、Aさんはその前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇暴行罪◇
今回の事件では被害者を傷害するに至らなかったので、Aさんは暴行罪の嫌疑をかけられていると思われます。
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」としており、人を殴った以上、怪我をさせなかった場合であっても、罪に問われることになります。
「暴行」とは、人の身体に対し不法に有形力を行使することを意味し、殴る、蹴る、突くはその典型例です。
また、通行人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、狭い四畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為なども、暴行にあたるとした判例があります。
◇Aさんの今後◇
Aさんは現在、逮捕されずに在宅で捜査されているので、警察から呼び出しを受け、取調べを受ける、という期間が続くと思われます。
最終的には検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めるので、検察から呼び出しを受けることもあります。
呼出しを正当な理由なく拒否すると、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうことがあります。
逮捕、勾留されると、最長23日間もの間身体拘束を受けるので、Aさんの社会生活に対する悪影響は計り知れません。
逮捕されるリスクを考えると、呼出しには応じた方がよいでしょう。
◇起訴された場合◇
起訴され、有罪が確定すると、刑罰を受けることになり、前科にもなります。
ケースにおいて無罪判決を獲得するのは極めて困難でしょう。
Aさんは公務員なので、有罪判決を受けると、勤務先からの評価にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
禁錮以上の刑を受けた場合、当然に失職します(地方公務員法28条4項・16条2号、国家公務員法76条・38条2号)。
では、前科がつかないようにするには、どうすればよいでしょうか。
◇被害者と示談◇
事件を有利に解決するためには、被害者と示談することをおすすめします。
示談とは、当事者間における、事件解決に向けた合意のことをいいます。
通常、加害者が被害者に賠償金を支払うことを内容とします。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものと判断され、逮捕されるリスクを低減させることができます。
さらに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断する際に、Aさんに有利な事情として考慮されることが期待できます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
◇示談交渉◇
示談契約は民事上の合意なので、Aさんが直接被害者と交渉し、示談を成立させることもできます。
ですが、Aさんが直接被害者と交渉することはおすすめできません。
そもそも、被害者の情報がわからないので接触しようがない、ということもありますし、警察は通常被害者さんの情報を当事者であるAさんには教えてくれません。
また、接触できたとしても、被害者に不当な示談金を要求されることも考えられます。
第三者が関わると、法律上有効でない示談となる可能性もあります。
お金を払うことで事件が解決できるならば…と、安易に示談を成立させるのは、Aさんにとっても利益ではありません。
そこで、法律の専門家である弁護士に、被害者との間に立ってもらい、示談交渉を任せることをおすすめします。
示談を成立させる場合は、弁護士が法的な観点から示談の条件が有効かつ妥当であるかをチェックします。
また、弁護士はそうした手続きの専門家であり、示談交渉に熟練していることから、Aさんにより有利な条件を引きだすことができる可能性が高まります。
是非、弁護士を通じた示談交渉をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、示談交渉の実績も豊富です。
暴行事件を起こし、お困りの公務員の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警察に逮捕される?
刑事事件を起こして警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、お客様からの法律相談を初回無料で承っています。
そんなお客様からのご相談でよくあるのが「警察に逮捕されますか?」という質問です。
そこで本日は「逮捕されるか?」という皆様の疑問に刑事事件専門の弁護士がお答えします。
逮捕
逮捕とは、刑事事件を犯した疑いある方が、警察に身体拘束を受けて取調べを受けることです。ここで注意しないといけないのは、「犯罪を犯した=逮捕」ではありませんし、「逮捕された=犯罪者」でもありません。
何かの犯罪を犯しても、逮捕されずに不拘束で取調べを受ける場合もありますし、逆に逮捕されたとしても、有罪が確定するわけではなく、その後の捜査で誤認逮捕が判明したり、刑事裁判で無罪が確定することもあります。
そもそも逮捕とは、身体拘束を受けて取調べをしなければ、容疑者が証拠を隠滅したり、逃走する可能性があって、事件の真相を解明することが困難になる事を避けるために行われる、刑事手続きの一つに過ぎないのです。
逮捕されると
逮捕されて一番困るのが、身体拘束を受ける事です。
身体拘束を受ける期間は人それぞれで、逮捕されてすぐに釈放される場合もあれば、その翌日や、2日後といった短期間で釈放される場合もあります。
法律的には、警察等の捜査当局が容疑者を逮捕した場合に与えられている時間は逮捕から48時間です。この時間内に警察は、逮捕した容疑者を釈放するか、検察庁に送致するかを検討します。
そして検察庁に送致された場合、送致を受けた検察官に与えられた時間は24時間です。この時間内に検察官は、容疑者を釈放するか、裁判所に勾留を請求するかどうかを検討するのです。
裁判所に勾留を請求された容疑者に勾留が決定すれば、10日~20日間の身体拘束を受けることになります。
つまり逮捕によって受ける身体拘束は最長で、逮捕から23日間にも及ぶので、仕事をされている方や、学校に通う学生の方にとっては非常に大きな不利益を被ることになるのです。
逮捕されるの?
それでは本題の「逮捕されるのか?」という疑問にお答えしようと思いますが、実は逮捕されるかどうかの判断は、刑事事件専門の弁護士であっても判断が難しく、絶対という答えはありません。
それは、ほとんどの刑事事件において、容疑者を逮捕するかどうかの判断は、捜査を担当する捜査当局に任されているからです。
法律上、現行犯逮捕以外は、容疑者の逮捕には裁判官の発する「逮捕状」が必要とされていますが、裁判官に対して逮捕状を請求するかどうかは、捜査を担当する捜査当局に任されているので、実質は、容疑者を逮捕するかどうかは、捜査を担当する捜査当局が判断すると言っても過言ではありません。
逮捕の要件
それでは、捜査を担当する捜査当局は何を基準に容疑者を逮捕するかどうかを判断しているのでしょうか?
法律的に、容疑者を逮捕するには逮捕の要件が必要となり、この要件となるのが、逮捕する「理由」と「必要性」です。
逮捕の理由は刑事訴訟法で定められているとおりで、それは「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」です。つまり、犯人である相当な理由が、逮捕の理由となります。
そして逮捕の必要性とは、これも刑事訴訟法に定められているとおりで、大きく分けると
・逃亡のおそれがある
・証拠隠滅のおそれがある
の何れかが認められると、逮捕の必要性が認められます。
逮捕の必要性
それでは、捜査当局は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」といった逮捕の必要性をどのように判断するのでしょうか。
逮捕の必要性があると判断されがちなケースをいくつかご紹介します。
逃亡のおそれがあると判断されやすいケース
①家族がいない
②仕事をしていない
③定まった住居がない
④執行猶予中である
①~③については、よく「単身身軽」という表現がされる状況で、客観的にみて逃走のおそれが認められやすい傾向にあります。また④については、その後の裁判で有罪となった場合に刑務所に服役する可能性が高く、そういった事を恐れて、逃亡する可能性があると判断されるようです。
証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいケース
①証拠品などが未発見、未押収である
②共犯者がいる
②については、共犯者と通謀(口裏を合わせ)して事実を歪曲する可能性があると判断されがちです。
逮捕されないために
それでは警察に逮捕されないために事前に何ができるのか?
正直なところ、確実に逮捕を回避できる弁護活動がるのかと聞かれれば、その答えは「ノー(ありません。)」です。
ただ逮捕のリスクを回避するための活動はその事件ごとに存在します。
例えば、窃盗罪や傷害罪などのように被害者が存在する事件に関してですと、警察に逮捕されるまでに被害者に謝罪し賠償することで逮捕を回避できる可能性が高くなりますし、器物損壊罪のような親告罪の場合ですと、被害者に告訴を取り下げてもらうことによって逮捕は回避できるでしょう。
また被害者の存在しない事件であっても、警察に自首することによって逮捕を回避できる可能性が高まります。
刑事事件に強い弁護士に相談
「警察に逮捕されるか不安です。」という方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
鉄パイプで頭部を殴打 殺人未遂事件で逮捕されたら
殺人未遂事件で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇殺人未遂事件◇
建設会社に勤めているAさんは、板橋区のビル建設現場に派遣されて働いています。
この現場には他の建設会社の社員も派遣されているのですが、先日、作業工程を巡って他の会社の社員とトラブルになったAさんは、口論の末に、足場用の鉄パイプで口論相手の頭部を殴打してしまいました。
すぐに周囲にいた作業員に制止されましたが、Aさんは、通報で駆け付けた警視庁志村警察署の警察官によって、殺人未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇殺人未遂罪【刑法第203条】◇
人を殺害しようと、殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合、殺人未遂罪となります。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人罪は、人の死という結果の重大性から、刑事裁判では厳しい判決が言い渡されることがほとんどですが、殺人未遂罪の場合は、刑法第43条(未遂減免)の適用を受けたり、傷害罪に罪名が変わるなどして、執行猶予付の判決が言い渡されることが珍しくありません。
◇殺人未遂罪か傷害罪か◇
殺人未遂罪の刑事裁判で、よく争点となるのは「殺意」の有無です。
「殺意」は、殺人罪の「故意」のことで、加害者の、相手を殺そうとする意思です。
同じ暴行行為でも、殺意があって行為に及べば殺人罪や、相手が死亡していなければ殺人未遂罪が適用される可能性が高くなります。逆に殺意が認められなければ、相手が死亡しても傷害致死罪や、相手が死亡していない場合は、傷害罪が適用される可能性が高くなるでしょう。
~殺意の立証~
「殺意」は加害者の心の声ですので、殺意の有無は加害者の供述に頼るしかありません。しかし、それだけで殺意の有無が認定されるわけではなく、殺意の有無は、暴行の程度や、犯行の計画性、被害者の傷害の程度等を総合的に判断されます。
・暴行の程度
急所を狙っている暴行や執拗な暴行、凶器を用いた暴行等の場合は殺意が認定されやすい。
・犯行の計画性
事前に被害者の行動パターンを下見している場合や、凶器を準備している場合等は計画性が認められて、殺意が認定されやすい。
・被害者の傷害程度
被害者が急所に傷害を負っている場合や、重傷を負っている場合等は殺意が認定されやすい。
・加害者の意思
殺そうと思って犯行に及んでいる場合は当然のこと、死ぬかもしれない、死んでもかまわないといったように、結果を認識し、それを容認した場合も故意があるとして、殺意が認められやすい。
◇殺人未遂罪の弁護活動◇
殺人未遂罪で警察に逮捕されたとしても、その後の対応によっては、罪名が傷害罪と認定されたり、被害者との示談することによって不起訴になったりして、処分の軽減が望めます。
上記したように、殺意の有無というのは、加害者の供述に大きく左右されるので、逮捕後の取調べで、どのように供述するのかが今後に大きく影響するため、弁護士は、取調べの対応についてアドバイスを行います。
また、被害者との示談も今後の処分に大きく影響します。
起訴までに被害者との示談が成立し、その示談に宥恕条項が含まれていれば、不起訴の可能性もあるでしょう。
殺人未遂罪は、罰金刑の規定のない非常に厳しい法定刑が定められている法律です。起訴された場合は、初犯であっても実刑判決の可能性が高い事件ですので、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕された方は、早めに刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
板橋区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
強制わいせつ事件で誤認逮捕されたら
強制わいせつ罪の誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都江東区に住む会社員のAさんは、10年前に痴漢事件で略式罰金の刑事罰を受けています。
Aさんは、自宅近所の月極駐車場を契約して自家用車をこの駐車場にとめています。
先日、この駐車場で女子高生が男から乱暴される強制わいせつ事件が発生しました。
事件が発生した直後に、Aさんが駐車場から車を出庫した記録があるということで、犯行を疑われたAさんは警視庁城東警察署に呼び出されました。
最初からAさんは、関与を全面否認していましたが、出頭した日の夕方に、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇誤認逮捕◇
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年100人以上もの方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、Aさんのように、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。
◇誤認逮捕が起こる理由◇
~虚偽の申告~
警察等の捜査当局が取り扱う事件のほとんどは、被害者や目撃者からの通報が犯罪捜査の端緒となります。
当然、故意的に虚偽の被害申告をした方は刑事罰の対象となりますが、捜査当局が虚偽の申告に気付くことなく捜査が進んだ場合、誤認逮捕が発生する可能性があります。
~不十分な裏付け捜査~
誤認逮捕が起こる可能性が一番高いのが通常逮捕です。
通常逮捕は、裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されるのですが、この逮捕状を請求するのは警察等の捜査当局です。
捜査当局は、それまでの捜査経過から、犯人を割り出した理由や、逮捕の必要性を明らかにした疎明資料をもとに裁判官に逮捕状を請求します。
疎明資料のほとんどは、警察官等によって作成されるので、捜査員の先入観にとらわれた主観的な内容になりがちです。
そのため、捜査当局にとって都合の悪い証拠は排除されてしまって逮捕状が請求されるので、誤認逮捕が起こってしまう可能性が生じます。
~自白の強要~
Aさんのように、逮捕前に不拘束による取調べが行われることがあります。
上記したような不適切な取調べに屈して、身に覚えのない犯行を自白してしまえば、その内容が記載された供述調書によって逮捕状が発付され、誤認逮捕につながる場合があります。
ご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都江東区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁城東警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
暴行の相手が死亡 同時傷害の特例
暴行した相手が死亡してしまった同時傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇暴行の相手が死亡◇
土木作業員のAさんは、同じ工事現場で作業をしている同僚と仲が悪く、普段からトラブルを繰り返しています。
その同僚と、先日偶然、豊島区にある行きつけの居酒屋で出くわしてしまい、口論になった後に、Aさんは同僚の顔面を複数回殴りつけてしまいました。
そして同僚は、Aさんに殴られて転倒する際に、偶然、そばにいた酔っ払いの服を掴んでしまい、酔っ払いの服を血で汚してしまいました。
服に血が付いたことに怒った酔っ払いは、Aさんに殴られて転倒した同僚の顔面を足で踏みつける暴行を加えました。
Aさんと、酔っ払いの暴行によって傷害を負った同僚は、救急搬送されましたが、頭部に重傷を負っており、その後死亡が確認されました。
通報によって駆け付けた警視庁池袋警察署の警察官によって傷害罪で現行犯逮捕されていたAさんは、その後、傷害致死罪で取調べを受ける事になりましたが、Aさんは、同僚が死亡した原因は、酔っ払いによる暴行が原因だと思っており、この罪名に納得ができません。
(フィクションです。)
~傷害致死罪と同時傷害の特例(刑法207条)~
本件では、Aさんに同時傷害の特例が適用され、傷害致死罪が適用されています。
同時傷害の特例とは、耳慣れない方も多いかもしれませんが、刑法207条によって規定されています。
刑法207条は、
・「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において」
・「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは」
・「共同して実行した者でなくても、共犯の例による」
という、非常に特殊な規定になります。
刑法60条は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と、共犯の中でも共同正犯について定めていますが、本来本条が適用されるには、2人以上の間に共謀が必要とされています。
刑法207条はこのような共謀がない場合にも、共同正犯が成立することを認める特殊な規定なのです。
さらに、本条は本来は検察官が負うはずの挙証責任を、被告人側に転換する(行為と結果の因果関係の不存在を被告人側に負わせる)点においても、特異な規定であり、学説上も批判が根強く主張されているところでもあります。
このような特例が置かれた趣旨については、傷害の結果が明らかであるにもかかわらず、当該傷害について誰も刑事責任を負う者がいなくなってしまう事態を回避するための特例との考え方が通説とされています。
この点、近年の判は、本条の適用に関し、まず「共犯関係にない2人以上」の「各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するもの」であり、「同一の機会に行われたものである」場合には「各行為者において、自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない」としました。
さらに上記判例は、「共犯関係にない2人以上の暴行による……刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には、いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、各行為者について同条の適用は妨げられない」としています。
これは、207条は暴行と死亡結果の因果関係を問題とするものではなく、あくまで暴行と「傷害」結果の因果関係が不明な場合に適用される規定であることを示したものと考えられます(上述のとおり207条では、「その傷害を生じさせた者を知ることができないとき」という文言が使われています。)。
したがって、本件Aさんが「当該傷害を惹起する危険性」を有する暴行を、「同一の機会」に行ったと認められば、207条の適用を介して、傷害致死罪(刑法205条)の罪責を負う可能性が生じることになるのです。
~同時傷害の特例における弁護活動~
弁護士としては、本条の適用について、Aさんの暴行が本当に「同一の機会」によるものであるのかを検討する必要があるでしょう。
さらに、刑法第207条が因果関係の挙証責任を被告人側に転換している規定である以上、Aさんによる暴行と、同僚の傷害との結果の間に因果関係がないということを積極的に立証するという特殊な立証活動が求められることになります。
仮に、因果関係がないことが証明されれば、Aさんが負う刑事責任は傷害罪の程度にとどまることになり、その法定刑に大きな差が生じることになるため、弁護士の立証活動が重要になることは言うまでもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、傷害致死(同時傷害の特例)事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
豊島区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
偽計業務妨害事件で控訴
控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
Aさんは、インターネットの動画投稿サイトにオリジナル動画投稿し、再生回数に応じて支払われる広告収入で生計を立てています。
先日Aさんは、覚せい剤に似せた白色粉末を入れた袋を、東京都北区にある、警視庁赤羽警察署の交番前に立っている警察官の前に落とし、そこから逃走するというドッキリ動画を撮影し、その動画をサイトに投稿しました。
再生回数は、これまでの3倍以上に増えましたが、悪質な悪戯だと事態を重く見た警視庁赤羽警察署が捜査を開始し、Aさんは警視庁赤羽警察署に偽計業務妨害罪で逮捕されてしまいました。
その後Aさんは起訴されて、先日、Aさんが略式起訴を拒否したために開かれた刑事裁判によって有罪が認定されて、罰金刑が言い渡されたのですが、Aさんは判決に納得ができず、控訴を検討しています。(実話を基にしたフィクションです。)
◇偽計業務妨害罪~刑法第233条~◇
偽計を用いて人の業務を妨害した場合には、偽計業務妨害罪が成立します。
「偽計」とは、人をだましたり、あるいは人の無知・錯誤を利用したりなどすることをいい、例えば虚偽の通報をすることが「偽計」に当たります。
Aさんの行為は、覚せい剤に見せかけた白色粉末白入りの袋を落とし、警察官をだまそうとしているため、「偽計」を用いているといえるでしょう。
では、警察官の捜査やパトロールなどといった公務は、偽計業務妨害罪のいう「業務」に当たるでしょうか。
公務への妨害行為については公務執行妨害罪が規定されており、公務執行妨害罪は公務への「偽計」を禁止していないことから問題になります。
判例は、強制力を排除する権力的公務か否かを基準としており、これに当たらない場合に公務が「業務」に当たるとしています。
そして、虚偽通報のような妨害行為に対しては警察官が強制力を行使しうる段階にないとして、公務が「業務」に含まれると判断しました。
そうすると、Aさんの行為は「業務」に対して「偽計」を用いたといえるでしょう。
なお、偽計業務妨害罪の条文には「妨害した」とありますが、これは現実に妨害が発生している必要はなく、業務を妨害しうるような行為がなされていれば「妨害した」といえます。
このような点を考慮すれば、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
ちなみに偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪等の刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に早めに初回接見を依頼することをお勧めします。
◇刑事裁判の流れ~控訴~◇
刑事事件を起こして起訴されれば、略式起訴での罰金刑を除いて、刑事裁判によって、その刑事罰が決定します。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aさんの起こした偽計業務妨害罪のような刑事事件の刑事裁判は、最初(第一審)東京地方裁判所(支部を含む)で行われます。
~控訴~
そして第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国8カ所にある高等裁判所又は全国6カ所にある高等裁判所の支部で行われることとなります。
東京都北区の刑事事件でお困りの方、偽計業務妨害罪の一審判決が不服で控訴を考えている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:36,400円
※弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お正月も休まず営業いたしております。※
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
青梅市の性犯罪 小学生女児に対する強制性交等事件
青梅市で発生した小学生女児に対する強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~強制性交等事件~
Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、青梅市の実家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族が激怒し、警視庁青梅警察署に通報したことからAさんは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇強制性交等罪◇
強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。
◇不能犯◇
今回の事件を検討すると、Aさんは、被害者の陰部が未成熟であったことが原因で、犯行(性交)を成しえなかったとされています。
一見、強制性交等罪は不能犯となり、Aさんはその刑責を免れることができ、強制わいせつ罪の成立にとどまるように思いますが、Aさんが、被害者に性交を試みている行為は、強制わいせつ罪の範囲を超えており、姦淫の実行に着手したものと認められるでしょう。
また不能犯について、判例では「不能犯とは、犯罪行為の性質上結果発生の危険を絶対に不能ならしめるものを指す」と判示しています。
このような観点から、Aさんの行為に対して不能犯が認められる可能性は非常に低いでしょう。
◇性犯罪の刑事弁護活動◇
強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。
身内に対する強制性交等罪でお困りの方、年末年始の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
青梅市の刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間)で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
年末年始の営業に関するお知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部)は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
葛飾区の冤罪事件 窃盗事件の無罪を争う弁護士
窃盗事件の無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事例~
ある日、Aさんの携帯電話に警視庁葛飾警察署の刑事さんから「葛飾区のスーパーで起こった窃盗事件で話が聞きたいので警察署に出頭してください。」という電話がかかってきました。
指定された日時に警察署に出頭したAさんは、刑事から「万引きしただろう。防犯カメラに映っているぞ。」と言われて、窃盗の容疑をかけられましたが、Aさんは全く身に覚えがありません。
確かに刑事に言われた日に、Aさんは、そのスーパーには買い物に行ってお弁当等を購入しているのですが、きちんとレジで会計を済ませて帰宅しています。
刑事から厳しく追及を受けたAさんは、どう対処していいか分からず困惑しています。
(フィクションです。)
~無罪を争う~
冤罪とは、事件とは無関係の者が窃盗事件の犯人として罪を着せられることをいいます。
窃盗罪は、「人の物を盗む」ことによって成立するような犯罪ですが、窃盗罪ような単純な事件でも、誤認逮捕されたり、その後の刑事裁判で無罪判決が言い渡されるなど、冤罪事件が発生しています。
数ある刑事事件の中でも、特に窃盗事件は他の犯罪に比べて件数も多く、身近な所で起こりやすいと考えられるため、その分冤罪に巻き込まれる可能性は大きいといえるでしょう。
万が一、身に覚えのない窃盗事件の容疑をかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、窃盗事件における無実・無罪を証明して冤罪を撲滅するための刑事弁護活動に力を入れています。
~どうして冤罪が発生するの?~
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取り調べで集められた証拠が原因で発生することが大半です。
窃盗事件で無実無罪を主張するためにはこのような証拠と戦っていく必要があります。
~アリバイの立証~
窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
検察官は、裁判で犯人と被疑者の同一性を立証します。
これに対抗する手段の一つとしてアリバイの立証があります。
アリバイとは、被疑者とされる者が窃盗事件当時犯行現場にいなかったことを主張することです。
アリバイが立証されることで窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、窃盗事件と被疑者の関係が否定されることになります。
~有罪の根拠となる証拠の弾劾~
窃盗事件の証拠には被害者、目撃者、被疑者の供述や被疑者自身の自白といったものがあります。
このような証拠で被疑者に不利なものは、その信用性を争うことが大切です。
具体的には、被害者や目撃者の供述・自白はその内容が不自然、不合理であるので信用できないということを主張します。
供述の信用性がないということになれば裁判の証拠とすることはできません。
~違法捜査による証拠の弾劾~
捜査機関は時として窃盗事件の立証に有利な証拠を収集するために違法な捜査を行う場合があります。
違法に収集された証拠は裁判で証拠とすることはできません。
例えば、捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は裁判上の証拠になりえません。
また、長時間にわたる取調べの末にとられた自白などは証拠とならない可能性があります。
~大切なのは~
誰もが、ある日突然、身に覚えのない窃盗事件の被疑者になってしまう可能性があります。
そんな時に大切なのは、刑事事件に強い弁護士に頼ることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することによって、一日でも早く冤罪の苦しみから解放されて、あなたの無罪を証明することができます。
葛飾区の冤罪事件でお困りの方、窃盗事件の無罪を争う弁護士をお探しの方は、窃盗事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
窃盗事件の刑事裁判(公判)
窃盗事件の刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
Aさんは、東京都渋谷区にある閉店後の衣料品店に、勝手口のカギを壊して忍び込み、レジに入っていた売上金30万円を盗みました。
忍び込んだ衣料品店までは、レンタカーで行っており、そのナンバーから被疑者として割り出されたAさんは、その後、建造物侵入罪と窃盗罪で、警視庁渋谷警察署に逮捕されました。
20日間の勾留を経て起訴されたAさんは、今後開かれる刑事裁判(公判)の流れや、処分の見通しが知りたくて、保釈後に、渋谷区の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
◇刑事裁判(公判)の概要◇
公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。
◇公判手続きの流れ~冒頭手続き~◇
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。
③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。
④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。
◇公判手続きの流れ~証拠調べ~◇
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
◇公判手続きの流れ~判決~◇
公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
◇公判手続きの特例~即決裁判手続~◇
上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。
渋谷区の刑事事件や、東京地方裁判所での刑事裁判(公判)でお困りの方は、これまで多くの刑事裁判において弁護人を務めてきた実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事裁判(公判)に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。