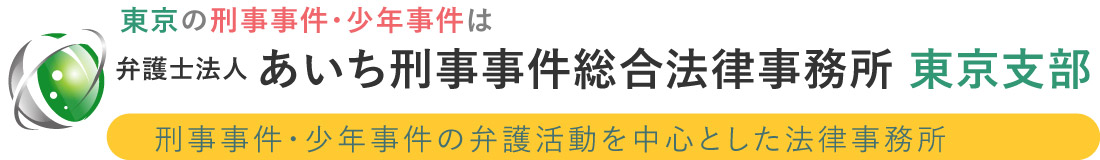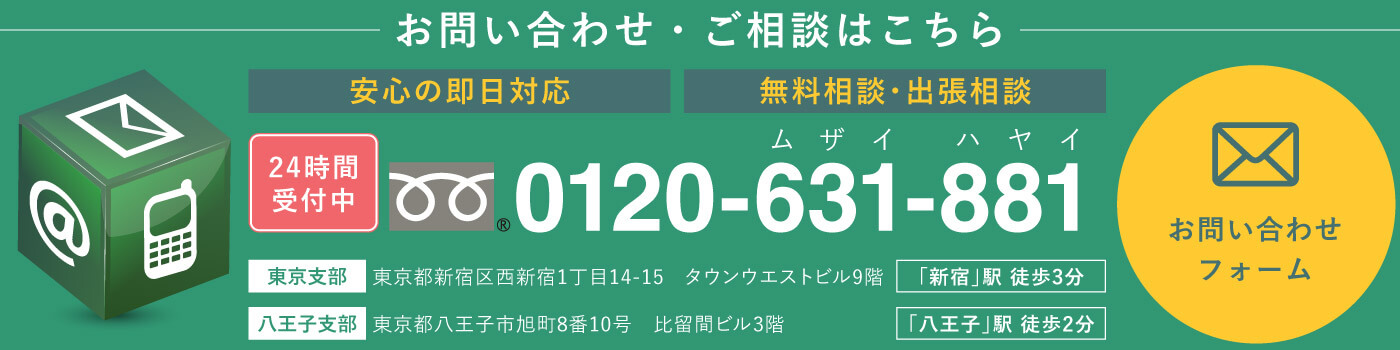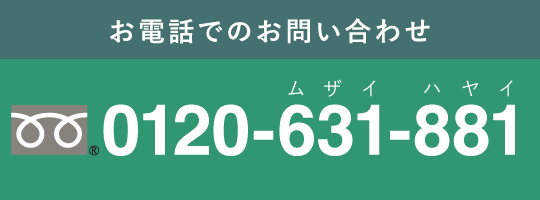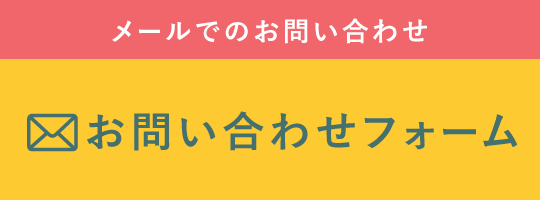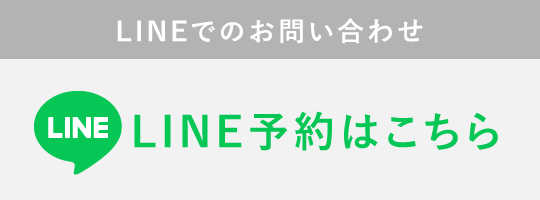Author Archive
傷害罪の前科を回避
傷害事件の前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学4年生のAさんはお酒に酔った勢いで、一緒に飲んでいた後輩の顔面を殴打して鼻を骨折させてしまいました。
事件を知った後輩の両親は激怒し、警視庁中野警察署に、Aさんを傷害罪で訴えました。
そのためAさんは、警視庁中野警察署に呼び出されて取調べを受けています。
すでに就職先から内定をもらっているAさんは、今回の事件によって前科が付く事を避けたいと思っていますが、どの様にしたらよいのか全く分かりません。
(フィクションです。)
◇前科とは◇
前科とは、一般に刑事事件として起訴され、刑罰が科せられた経歴のことをいいます。
これに対して、前歴というのは、捜査機関によって一定の捜査の対象になった経歴のことを意味します。
その他にも交通違反で反則金を支払ったなどの経歴である交通違反前歴というものもあります。ちなみに、過去に警察に補導されたり指導を受けたりしても、前科・前歴には残りません。
◇前科による不利益◇
~刑事手続き上の不利益~
刑事事件を起こしてしまい、罪に問われる場合、捜査機関は必ず容疑者の犯罪歴を調査します。
そして、容疑者に前科が付いていれば、その内容や犯罪歴の個数にも関係しますが、重い処分につながりやすくなります。
たとえば、万引きを繰り返し行ってしまった場合、同じような態様で行われたとしても、罰金処分、執行猶予付き判決、実刑判決とより重い処分へとつながりやすくなります。
~その他の不利益~
前科があることによって、一定の職業に就くことができなくなったり、資格の取得が制限される場合があります。
前科の有無や内容は、通常、一般には公開されませんし、本人であっても調査して確認することはできません。
しかし、報道機関などにより、一旦実名報道がなされてしまうと、ネット上に記事などが残っていることがあります。
履歴書などに前科を記載すると、当然就職活動は困難になるでしょうし、かといって企業が要求している場合に虚偽の記載をしてしまうと経歴詐称になってしまいます。
後にネット記事などによって犯罪歴を知られてしまうと解雇されてしまう場合もあるでしょう。
◇前科を回避するために◇
前科を避けるためには、捜査機関による事件化を防止するか、検察官に起訴しないで(不起訴処分)事件を終結してもらうことが必要です。
軽微な事件では、被害者との示談が成立し、被害届が出されないような場合では事件化を防ぐことが可能です。
しかし、事件が捜査機関により捜査の対象となってしまった場合には、検察官が起訴するかどうかの秤にかけられることになります。
検察官が起訴した場合の有罪率は、約99%ですから、無罪判決を勝ち取ることは非常に困難です。
その反面、送致事件のうち検察官の起訴率は40%程度ですので、約60%は不起訴処分で処理されているということになります。
ちなみに不起訴処分のうちの約90%は、起訴猶予となっています。
起訴猶予処分とは、犯罪の嫌疑はあるものの、訴追するまでの必要はないと検察官が判断した場合に下される処理のことです。
◇不起訴処分を得るための弁護活動◇
不起訴処分には、実際には罪を犯していないのに犯罪の嫌疑が欠けられてしまった場合にもなされますし、犯罪の嫌疑があっても訴追を必要としないと判断されてなされる場合(起訴猶予)もあります。
起訴猶予を理由とする不起訴処分の場合には、起訴・不起訴処分がなされるまでの限られた時間の中で、検察官に対して不起訴処分が相当であるということを説得的に主張しなければなりません。
そこで、捜査の早い段階から弁護士が積極的に弁護活動に取り組むことが非常に有用なのです。
具体的には、刑事裁判で有罪を勝ち取るには証拠が不十分であるとか、容疑者にアリバイがあること、すでに示談が済んでいること、被害弁償が終わっていること、被害届・告訴状の取下げがなされていることなど容疑者に有利な事情を示して検察官に不起訴処分にしてもらえるよう交渉していきます。
特に被害者がいる場合に示談が成立していることは、不起訴処分を勝ち取るためにも、刑罰を軽くするためにも非常に有利に働く事情です。
被害者が処罰を求めない以上、検察官としても刑罰をもって処罰するまでの必要性は乏しいのではないかと考えさせる契機になるというわけです。
また、親告罪の場合には、被害者と示談をして、告訴を取り下げてもらうことにより、確実に不起訴処分を得ることができます。
東京都中野区の刑事事件でお困りの方、傷害事件を起こしてしまって前科を回避したい方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中) までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
殺人事件の裁判員裁判
殺人事件の裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、かねてから金銭トラブルのあった友人を、話し合いをするために自宅に呼び出しました。
そこで友人と口論になってしまい、Aさんは、テーブルの上にあった灰皿で思わず友人の頭部を殴打してしました。
そして更に転倒した友人に馬乗りになって頭部を連続して殴りつけて友人を殺害しました。
我に返ったAさんは、自ら110番通報し現場に臨場した警視庁原宿警察署の警察官に殺人罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、逮捕から起訴まで一貫して犯行を認めており、裁判員裁判が開かれることになりました。
(フィクションです。)
◇裁判員裁判◇
裁判員裁判とは
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
②短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件
については、通常の裁判官だけの裁判ではなく、裁判員も含めた裁判員裁判で審理が行われる刑事裁判です。
今回、Aさんが起訴された殺人罪の法定刑は「死刑若しくは無期若しくは5年以上の懲役」ですので、上記①に当たります。
裁判員裁判は、殺人事件や強盗致死傷事件だけでなく、通貨偽造事件や営利目的での薬物輸入事件、危険運転致死事件などの、基本的に国民の関心の高い事件が対象となっています。
◇裁判員裁判の特徴◇
通常の刑事裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われますが、裁判員裁判は、国民の中から選任された裁判員が裁判官ととともに、刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を課すべきかを決めることとなります。
裁判員裁判は、原則として、裁判官3人と裁判員6人の合議体で行われることとなります。
裁判員裁判は、一般人が裁判に参加することもあり、通常の刑事裁判とは異なり短期間に集中して行われ、第一回公判から判決の言い渡しまでは2週間もかかりません。
そのため、裁判員裁判が開始されるまでに、裁判の争点や証拠を整理する公判前整理手続が、必ず行われます。
公判前整理手続とは、第一回公判前に検察官・弁護人双方の主張すなわち事件の争点や証拠を整理する手続きのことで、この手続きには被告人も出頭することもできます。
公判前整理手続で、裁判の争点と証拠が整理され、被告人にとっては、検察官の手持ちの証拠を開示させることができるという利点があります。
裁判員裁判は、法律家以外がその審査に参加することから、法律的な要素だけでなく、裁判員の印象も、その後の判決に大きく影響すると言われています。
そのため、従来は証人尋問をせずに被害者や目撃者、被告人の調書を読み上げるだけで済まされていたのが、裁判員の前で証人として尋問するようになり、これまで調書で問題となっていた、供述者の供述の信用性についてしっかり尋問できるようになりました。
◇裁判員裁判の上訴◇
法律家の視点だけで裁かれる従来の刑事裁判では、杓子定規に当てはめたような量刑が言い渡されることがほとんどですが、裁判員裁判では、想定外の判決は言い渡されることも珍しくありません。
(実際の裁判員裁判では、薬物輸入事件で故意が認められないとして無罪判決が言い渡されたり、検察官の求刑意見よりも重い従来の量刑基準を逸脱した判決が言い渡されたりしている。)
当然、その様な想定外の判決に対しては、検察官側も、被告人側も控訴することができますが、裁判員裁判は一審だけであり、控訴・上告すれば裁判官のみで構成される裁判所により裁判されます。
一審の判決が重すぎるとして、量刑不当により刑が軽くなるケースがある一方で、検察官側が控訴して一審が無罪判決だったものが控訴審で有罪判決を下される可能性もあるのです。
裁判員裁判の刑事弁護は、従来の刑事裁判とは異なり、卓越した刑事事件専門の知識と、豊富な経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績と、豊富な経験がございます。
殺人事件を起こした方のご家族、ご友人の刑事弁護をご希望の方、殺人事件の裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881(24時間)にて受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
覚せい剤所持事件で控訴を検討
覚せい剤所持事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
覚せい剤取締法違反で執行猶予中のAさんは、約2ヶ月前に、東京都江戸川区を自動車で走行中に、交通違反をしてしまいパトロール中の警察官に停止を求められました。
この時Aさんは、数日前に友人から購入した覚せい剤を隠し持っており、それが発覚する事をおそれて逃走しましたが、結局、追跡してきたパトカーに捕まってしまい、その後の所持品検査で覚せい剤も見つかってしまいました。
覚せい剤の所持罪で現行犯逮捕されたAさんは、10日間の勾留期間を経て起訴されて、先日、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。
Aさんは、この判決に納得できず控訴を検討しています。
(フィクションです。)
◇控訴◇
控訴とは、地方裁判所や簡易裁判所といった第一審裁判所が下した判決に不服がある場合に、第一審裁判所の上級裁判所(簡易裁判所が第一審の場合は地方裁判所、地方裁判所が第一審の場合は高等裁判所)に不服申し立てを行うことです。
控訴は、法律で定められた控訴理由がある場合に限って行うことができます。
その控訴理由とは、主に事実誤認、量刑不当、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反などです。
◇控訴手続きの流れ◇
第 一 審 判 決
↓≪※14日以内≫
公 訴 申 立
↓ ↓
勾 留 ⇒ 保 釈 請 求 ⇒ 在 宅
↓ ↓
控 訴 記 録 送 付
↓
控 訴 趣 意 書 の 提 出
↓
控訴裁判所の控訴記録の検討
↓
公 判
↓
判 決
※第一審判決から控訴申立までの期間は14日以内ですが、判決日は算入しません。また控訴期間の末日が日曜日、土曜日、祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日である場合は、それらの日の次の日が控訴期間の最終日となります。
~控訴審の判決~
控訴審は、途中で控訴を取り下げない限り、判決により終了します。
控訴審の終局判決には「控訴棄却判決」と「原判決破棄判決」の2種類です。
「控訴棄却判決」とは、控訴裁判所が第一審判決の判断を妥当として維持する判決のことです。
「原判決破棄判決」とは、控訴裁判所が第一審判決の判断に誤りがあったことを認め、第一審判決を破棄する判決です。
原判決破棄判決はさらに、控訴裁判所が自ら新たな判断を下す破棄自判と、改めて第一審裁判所で審理し直す破棄差戻しの2種類に分かれます。
~控訴は検察官もできる~
告訴できるのは被告人だけではありません、検察官も第一審の判決に不服があれば控訴することができます。
被告人だけしか控訴しなかった場合は、第一審で言い渡された刑よりも重い刑になることはありません。
これは、被告人が、第一審よりも不利益な結果になることをおそれて、控訴権の行使を差し控えることのないようにとの配慮から定められた「不利益変更禁止の原則」といいます。
しかし上記したように検察官側も控訴した場合はこの限りではありません。
◇控訴審までの弁護活動◇
~保釈請求~
上記した「控訴手続きの流れ」のように、第一審判決後に収監された場合でも、控訴を申立ててから控訴審で判決が言い渡されるまでの間、改めて保釈請求することができます。
控訴審での保釈を請求を請求した場合、保釈金は、第一審の際の保釈金よりも高くなることがほとんどです。
~事件を再検証~
控訴審は、第一審判決に誤りがなかったかについて、第一審判決時の事情を基礎として審理するものです。
したがって、原則としては、第一審裁判所において取調べられた証拠を前提としなければなりません。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由に控訴する場合は、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に請求できなかった証拠については、証拠調べができます。
また、第一審で調べられた証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、裁判所の裁量により証拠調べをすることもあります。
さらに、量刑に影響を及ぼし得る情状に関する証拠は、第一審判決後に生じた事情に関する証拠であっても裁判所の裁量により調べることが可能ですので、弁護士は改めて事件を検証し、証拠収集することとなります。
~控訴趣意書の作成~
控訴審は、第一審の事後審です。基本的には、第一審の裁判を後から検討して、第一審裁判所の判断に問題があるか否かという判断をします。
控訴趣意書を作成するにあたっては、第一審判決とその判決の基となった事件記録を読み込み、不服がある第一審判決の論理の弱点を見つけ出した上で、説得的な論述をしなければなりません。
東京都江戸川区の覚せい剤事件で控訴を考えている方や、そのご家族の方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
準強制わいせつ事件に強い弁護士
準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区に住むAさんの旦那(40歳、会社員)は、職場の懇親会において、酔払った女性新入社員を介抱する目的で、女性が一人暮らしする社宅に連れて帰った際に、ムラムラしてしまい、この女性新入社員の服を脱がせ、下着の中に手を入れる等のわいせつな行為に及んでしまいました。
目を覚ました女性に抵抗されたことから、それ以上の行為には及ばなかったようですが、女性が警察に訴えたことから、Aさんの旦那は、準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、旦那さんに弁護士を付けてあげたいと思っていますが、どうすればよいか分からず悩んでいます。(フィクションです)
◇準強制わいせつ罪◇
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)※刑法抜粋
刑法第176条に規定されている「強制わいせつ罪」は、暴行や脅迫を手段としてわいせつ行為に及ぶことによって成立しますが、準強制わいせつ罪の成立には、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。
しかし、被害者が「心神喪失」若しくは「抗拒不能」にある必要があります。
~心神喪失とは~
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。
~抗拒不能とは~
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。
◇刑事弁護人の選任方法◇
刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。
~私選弁護人の選任~
確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
準強制わいせつ罪で逮捕されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」となります。
執行猶予付の判決を得なければ刑務所に服役しなければなりませんが、起訴されるまで被害者と示談することによって不起訴処分が望めます。
不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれず、前科を回避することができます。
~国選弁護人の選任~
国選弁護人を選任できるのは
①勾留された被疑者
②起訴された被告人
の何れかですので、何れのタイミングでも選任することができる私選弁護人のように逮捕前に選任することはできません。
国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制わいせつ罪で警察に逮捕されてしまって、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
飲酒検知を拒否して逮捕
飲酒検知拒否罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
タクシー運転手のAさんは、夜勤明けに、会社近所の居酒屋でお酒を飲みました。
それから電車で東京都江戸川区の自宅に帰宅したのですが、帰宅後に、家族から近所の駅まで迎えに来て欲しいと電話で頼まれました。
お酒を飲んでいたので断ろうと思いましたが、大雨が降っていたので、Aさんは家族にお酒を飲んでいることを告げずに、車で迎えに行くことにしました。
しかし、自宅を出発してからすぐに信号無視をしてしまい、偶然通りかかった警視庁小松川警察署のパトカーに停止を求められました。
車を停止させて免許証を提示したAさんでしたが、その際に、警察官から酒臭がするので呼気検査を求められました。
しかし飲酒運転が発覚すれば仕事を失ってしまうことを懸念したAさんは飲酒検知のための呼気検査を拒否し、再三にわたる警察官の説得にも応じませんでした。
すると、Aさんはその場で飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
◇飲酒検知拒否罪◇
飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証されますが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知を妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と飲酒検知拒否罪を規定しているのです。
それでは具体的にどのような行為が、飲酒検知拒否罪となるのでしょうか?
~ケース1~
Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。
~ケース2~
一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。
~ケース3~
警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。
◇逮捕されるの?◇
飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は基本的に現行犯逮捕されると考えられます。
◇逮捕後は?◇
飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されると、現場を管轄する警察署に引致されます。
そこで取調べを受けると共に、再度警察官から飲酒検知のための呼気検査を求められるでしょう。
そこでもなお飲酒検知を拒否した場合、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうのです。
◇勾留されるの?◇
飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されたとして、検知を拒否した理由が明らかで、逃走や、罪証隠滅のおそれがない場合は、勾留までされる可能性は低いと考えて問題ないでしょう。
◇刑事処分はどうなるの?◇
飲酒検知拒否罪の法定刑は、上記したように「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、この法定刑内の刑事罰が言い渡されることになります
◇飲酒検知拒否罪で無罪判決◇
平成27年9月に、横浜地方裁判所で飲酒検知拒否罪で起訴された男性に無罪判決が言い渡されています。
この裁判で争点となったのが、警察官が被告人に対して明確に飲酒検知のための呼気検査を求めて、その事を被告人が認識した上で呼気検査を拒否したかどうかであったが、裁判所は「飲酒検知拒否罪は、警察官による呼気検査の要求を前提として、被告人の拒否の意思が客観的に明らかになったことを認定する必要があるが、今回の事件では、警察官が具体的な言動で呼気検査を要求し、被告人が警察官による呼気検査の要求を意識したう上でこれを拒絶する意思を明確にしたと認定することは困難。」という判断で無罪判決を言い渡したようです。
この事件では、被告人の男性が携帯電話によって動画を撮影しており、その録画内容が有力な証拠となって無罪判決が言い渡されたようです。
飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
飲酒検知拒否罪で警察に逮捕された場合であっても、後の刑事裁判で無罪判決を得ることは不可能ではありませんので、東京都江戸川区の飲酒検知拒否罪でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
不正なチケット転売の規制が開始されました
新設される「チケット不正転売禁止法」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
今日から、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「チケット不正転売禁止法」)が施行され
・チケットの不正転売
・不正転売を目的とするチケットの譲受け
が禁止されているのをご存知でしょうか。
◇特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)◇
~目的~
この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。(同法第1条から抜粋)
人気アーティストのコンサートやスポーツ観戦のチケットをインターネットのオークションサイトや、掲示板において高額で取り引きされているのをご覧になった方もいるのではないでしょうか。
高額で人気チケットを転売して利益を得ることを目的にした、チケットの買い占め等によって、正規ルートでのチケットの購入が困難になって困った方もいるかと思います。
また、この様な買い占め行為が、集客にも影響を及ぼし、主催者側に大きな不利益をもたらすだけでなく、競技や文化の振興の妨げになっているとも言われています。
この様な状況を打開することを目的に施行されたのがチケット不正転売禁止法で、不正転売や、不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合には罰則規定も定められています。
~禁止事項~
チケット不正転売禁止法で禁止されている主な行為は
①チケットの不正転売
②不正転売を目的としたチケットの譲り受け
です。
①チケットの不正転売
同法第3条
何人も、特定興行入場券(チケット)の不正転売をしてはならない。
この法律でいう「不正転売」については、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(第2条4項抜粋)です。
簡単に言うと「コンサートやスポーツ観戦等の興行主催者(チケットの販売者)の許可を得ないで、その興業のチケットを、定価以上の値段で転売してはいけません。」ということです。
ここでポイントとなるが「業として」という内容ですが、これは利益を得ることを目的として、反復継続して行う転売だという解釈でしょう。
例えば、一つのコンサートや、スポーツ観戦のチケットを複数枚正規購入して、そのチケットを購入後すぐに、定価以上の値段で転売する場合などは「業として不正転売している」と認定される可能性が高いでしょう。
②不正転売を目的としたチケットの譲受け
同法第4条
何人も、特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない。
上記した第3条は不正転売行為を禁止する条文になりますが、この条文は、不正転売を目的としてチケットを購入する行為自体を禁止する内容になります。
つまり、実際に購入したチケットを不正転売していなくても、不正転売する目的でチケットを購入した時点で第4条違反となる可能性があるので注意しなければなりません。
~罰則~
上記した違反行為の有罪が確定すれば、違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」が科せられます。
これまではチケットの不正転売を規制する際は、各都道府県の迷惑防止条例が適用されていましたが、インターネット上の取引等では適用が難しく、実情は野放しになっていたと言わざるを得ません。
しかしチケット不正転売禁止法が施行されたことによって、警察等の捜査当局の取締りは厳しくなることが予想されますので、コンサートやスポーツ観戦等のチケットを転売する際は十分に注意してください。
東京都内の刑事事件でお困りの方や、チケット不正転売禁止法に関する法律相談は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
振り込め詐欺の受け子事件で執行猶予付きの判決を得ました
振り込め詐欺の受け子事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇弁護依頼までの流れ◇
本件のご依頼者様は、ご子息様が詐欺で逮捕されたとのことで、弊所に初回の接見をご依頼されました。ご依頼者は遠方にお住まいだったため、ご子息様から直接事件のことを何も聞いておらず、警察からも事件の詳細は教えてもらえなかったことから、大変心配されていました。
弁護士が警察署でご子息様と接見したところ、振り込め詐欺の受け子をしてしまったとのことで逮捕されていたことが分かりました。
振り込め詐欺の事案では余罪が多数に及ぶことが多く、身体拘束が長期化すること、被害額によっては実刑判決を受ける可能性が高く、本件でもそれらのリスクがあり、捜査の初期から慎重な弁護活動を行う必要がありました。
初回接見の後、ご依頼者様に、事件の概要や今後予想される手続き、行うべき弁護活動等について弁護士から説明の上、正式に依頼を頂き、弁護活動に着手することとなりました。
◇捜査段階の弁護活動◇
逮捕後からご子息様に対しては複数回の取調べが行われていたため、捜査機関の取調べにどのように対応すべきかを決めなければなりませんでした。
特に、振り込め詐欺については捜査機関も余罪の有無を、徹底的に捜査を尽くしますので、ともすれば、本当は関わっていない事件について関与を疑われることがあります。
本件については、複数回の接見の上、ご子息様から自分の関与した事件とそうでない事件を聞き取り、取調べの前に弁護士と打ち合わせを行いました。警察からの取調べに対してどのように答えるべきなのか、一つ一つ弁護士と確認をしながら打合せし、実際の取調べに臨みました。
取調べの後には再び弁護士と接見し、どのようなことを聞かれたのか聴取し、次回の取調べに対する打合せの課題としました。
その結果、ご子息様が関わったとされる事件についてのみ起訴がなされ、手続きの間延びによる身体拘束の無用な延長や、被害額の拡大を避けることが出来ました。
~示談交渉~
振り込め詐欺事件は被害者のいる犯罪ですので、裁判が始まる前から被害者の方と連絡を取り始め、示談交渉に着手しました。ご子息様の反省の状況を踏まえて、弁護士が誠意をもって対応し、謝罪と被害の弁償を行いました。被害者の方々からは「社会の中で更生してほしい」とのありがたいお言葉と、加害者であるご子息様を許すとの一筆を頂けました。被害者の方の中には、ご子息様の反省状況や置かれた状況等を考慮して、被害額の約3分の2程度の弁償額で許していただけた方もいました。これらの示談交渉の経緯は、裁判の場でも証拠を提出して主張、立証を行いました。
◇起訴後の弁護活動(公判弁護)◇
また、ご子息様が今回の事件について関わってしまった経緯や今後の社会内での生活を行う環境について、同情すべき点があったため、裁判の場でもその点が明らかにすることを弁護側の目標としました。本件に関与し始めたときの状況を、裁判官にしっかりとアピールできるよう、弁護士とご子息様とで打合せを行いました。また、検察官からの反対尋問についても事前に打ち合わせを行い、裁判の場で動揺することがないよう準備を行いました。
裁判当日には、ご依頼者様とご子息様に法廷に立ってお話しいただきました。当日は、お二人とも緊張のためか、お話しに詰まる部分もありましたが、事前に打ち合わせに基づいて弁護士からも助け船を出すことで、ご自身の主張を過不足なく裁判所に対して伝えることが出来ました。
~判決~
本件については被害額267万5千円の詐欺、窃盗事件として有罪の判決が言い渡されましたが、懲役3年執行猶予5年という判決を得られました。
◇事件後の感想◇
本件については当初から実刑の可能性がある事件でした。
逮捕直後から弁護人として選任されたことで、一貫した取調べの対応ができ、被害者の方にも時間をかけて交渉を行うことができました。
また、本件のご依頼者様の資金的な問題もあり、当初は示談交渉がまとまるかどうか心配な部分もありましたが、交渉の結果、被害弁償を受けていただき、被害者の方からご子息様、ご依頼者様に対しては今後一切の請求を行わず、かつ、「親のために社会できちんと働く生活をしてほしい」とまで仰っていただけました。
判決の量刑の理由に関する記載では、振り込め詐欺の事案は社会的に大変問題となっていることや、被害額が百万円を超えて高額であることを指摘して、「基本的には実刑を科すべき」と判断しました。しかし、公判での弁護側の立証、特に情状証人が出廷して監督を誓約していることや、示談交渉の経緯・結果等を踏まえると、「社会内で更生する機会を与えるのが相当」との結論が出されました。
近年、特殊詐欺の事案については重い刑が科される傾向にあり、本件の判決からも、振り込め詐欺については「基本的に実刑で臨む」という、裁判所の厳しい姿勢が見て取れます。
いずれの弁護活動についても、裁判手続きを見越して行った結果、懲役3年執行猶予5年という、ギリギリの判決を得られたのだと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
少年事件の処分
少年事件の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
前回のコラムでは少年事件の流れを解説いたしました。
刑事事件を起こした少年は、家庭裁判所で開かれる審判において、その処分が決定するのですが、本日は、刑事事件を起こした少年の処分について解説します。
審判で裁判官が決定する処分は大きく分けて①不処分②保護処分③検察官送致の3種類です。
①不処分
家庭裁判所は、審判の結果、少年を保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めた場合は「不処分」となります。
「保護処分に付することができない」とは、少年が犯罪を犯していないと判断されることで、成人の刑事事件における「無罪」に相当します。
「保護処分に付する必要がない」とは、少年に要保護性がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要性も認められないことを意味します。
②保護処分
~保護観察~
保護観察とは、少年を施設に収容させることなく、日常生活を送らせながら、保護観察所の指導監督や、補導援護という社会内処遇によって、少年の更生を目的とする保護処分です。
保護観察は、他の保護処分と異なり、施設に収容されることなく日常生活を送ることができるので、少年の不利益は少ないと考えられますが、逆に、これまでと同じ日常生活を送れるために、再犯を起こしてしまったり、別件の非行行為を起こしてしまう可能性があるので、保護観察中は、少年だけでなく、ご家族など少年の周りの人々の監督も必要となります。
保護観察には、一般保護観察、一般短期保護観察、交通保護観察、交通短期保護観察の4種類があり、それぞれに期間が定められています。
一般保護観察の場合は、おおむね1年で、この間に3ヶ月以上連続して成績良好であれば保護観察が解除されます。
一般短期保護観察の場合は、おおむね6ヶ月~7ヶ月で保護観察が解除されますが、10ヶ月以内に解除できなかった場合は、一般保護観察に切り替えられる可能性があります。
交通保護観察は、おおむね6ヶ月以内に解除される場合がほとんどです。
交通短期保護観察は、3ヶ月~4ヶ月以内に解除される場合がほとんどですが、6ヶ月を過ぎても解除されない場合は、交通保護観察に切り替えられる可能性があります。
~児童自立支援施設又は児童養護施設送致~
「児童自立支援施設」とは、かつて「教護院」と呼ばれていた施設で、全国に58施設あるといわれています。
不良行為をしたり、するおそれのある児童や、家庭環境等の理由により生活指導が必要な児童が収容される施設ですが、完全に収容される児童ばかりでなく、保護者のもとから通う児童もいます。
「児童養護施設」とは、かつて「養護施設」と呼ばれていた施設で、全国に569施設が存在するといわれています。
児童養護施設は、保護者のいない児童や、虐待されている児童等を養護するための施設ですので、非行性のある児童に対する処遇を行うことが困難だとされているため、実際に、家庭裁判所の審判で児童養護施設送致の決定がなされることは滅多にありません。
~少年院送致~
少年院は、少年の非行を防止するために、基本的に外出が許されず、被開放的な施設で厳しい規律の中で日常生活を強いられる、生活訓練施設です。
上記した保護処分と異なり、非常に厳しい処遇であるといえるでしょう。
少年院には、初等、中等、特別、医療の4種類の少年があり、少年の年齢等によって区別されています。
初等少年院・・・心身に著しい支障のない、おおむね12歳~16歳未満の少年
中等少年院・・・心身に著しい支障のない、おおむね16歳~20歳未満の少年
特別少年院・・・心身に著しい支障はないが犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳~23歳未満の者
医療少年院・・・心身に著しい支障のある者
少年院に収容される期間は、大きく分けて「短期」と「長期」があり、短期は4ヶ月以内の特修短期と、6ヶ月以内の一般短期に分かれています。
また長期は、10ヶ月程度の比較的短期、おおむね1年の単なる長期、1年より長く2年以内の比較的長期、2年を超える相当長期の4種類があります。
少年院では、少年院の種類や収容期間によって収容中のカリキュラムが異なりますが、基本的には生活訓練が主となり、それに加えて、教科教育や職業能力開発、特殊教育等が行われます。
③検察官送致(逆送)
家庭裁判所は
①審判時に少年が成人に達した場合
②死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件において、調査の結果、罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認める場合
の何れかは、事件を検察官に送致しなければなりません。
これを「逆送」といいます。
~原則逆送~
犯行時に16歳以上で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件を起こした少年については、原則的に逆送しなければならないとされています。(少年法第20条2項)
ただし、犯行の動機や態様、犯行後の情況や少年の性格、年齢、環境等に事情を考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合は、逆送されないこともあります。
お子様が刑事事件を起こしてお悩みの親御様、刑事事件を起こしてしまったお子様の処分が心配な方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承るだけでなく、逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービス(有料)を用意し、皆様からのご予約をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
少年による窃盗事件
少年による窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、人気アーケードゲーム「太鼓の達人」の太鼓を盗んだとして、東京都目黒区の私立高校に通う男子生徒(16歳)が、窃盗罪で警視庁少年課に逮捕されました。
この事件では、すでに別の少年が逮捕されており、この他にも事件に関わった少年がいるとして捜査が進められています。
逮捕された少年は仲間と共に、他の店舗から盗んだ基盤などと組み合わせて、自宅に太鼓の達人の器具を再現し、遊んでいる様子を動画投稿サイトに投稿するのが目的だったようです。(令和元年6月3日付の産経新聞から抜粋)
◇窃盗罪◇
人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
◇少年事件の流れ◇
①逮 捕
↓(48時間以内)
②検察庁に送致
↓(24時間以内)
③裁判所に勾留(勾留に代わる観護措置)請求
↓ ↓
④勾 留(10日間~20日間) ⑤勾留に代わる観護措置(10日間)
↓ ↓
⑥家庭裁判所に送致 ↓
↓(24時間以内) ↓
⑦ 観 護 措 置
↓ ↓
⑧審 判 ⑨審判不開始
①逮捕
逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類があります。
少年であっても、何れの逮捕手続きの対象となり、成人被疑者と同様の扱いを受けます。
②検察庁に送致
少年を逮捕した警察等の捜査当局に与えられている時間は48時間です。
この間に、逮捕した少年の取調べ等を行われ、事件内容や少年の素行等を考慮して、引き続き身体拘束を続けて捜査するのか、釈放するのかが決定します。
引続き身体拘束が必要だと判断された場合は、検察庁に送致されます。
釈放された場合でも、取調べ等の捜査は続けられますので、少年は、警察から呼び出されるごとに警察署に出頭し取調べを受けなければなりません。
③裁判所に勾留(勾留に代わる観護措置)請求
警察からの送致を受けた検察官は、それまでの捜査結果を踏まえて、裁判所に勾留(勾留に代わる観護措置)請求するのか釈放するのかを判断します。
少年法では、やむを得ない場合でなければ勾留請求できないと規定されているので、法律的には、成人被疑者と比べれば勾留請求される可能性は低い事になりますが、勾留に代わる観護措置が請求される可能性があります。
④勾留
裁判官が、勾留の必要性を認めれば勾留されることになります。
勾留期間は10日~20日で、勾留場所は警察署の留置場か、少年鑑別所となります。
裁判官が勾留を認めなかった場合は釈放となります。
⑤勾留に代わる観護措置
裁判官が、勾留に代わる観護措置の必要性を認めれば鑑別所に勾留されることになります。
勾留の場合は、必要に応じて、その期間が20日間まで延長されますが、勾留に代わる観護措置の場合は、その期間が10日間と法律で定められているので延長はありません。
しかし、その期間を終えると、改めて裁判官の審査を経ることなく自動的に観護措置が開始されます。
⑥家庭裁判所に送致
勾留、勾留に代わる観護措置の期間が終了すれば、家庭裁判所に事件が送致されます。
勾留によって身体拘束を受けていた少年については、ここで観護措置を決定するかどうかが裁判官によって判断されます。
⑦観護措置
観護措置が決定すれば通常で4週間(最長で8週間)、少年鑑別所に収容されて調査を受けることになります。
鑑別所に収容されずに在宅観護となる場合もありますが、実務上あまり目にすることはありません。
⑧審判
少年が本当に刑事事件を起こしたかどうかが判断されます。
犯罪事実を争う場合は、検察官が審判に参加し、刑事裁判でいうところの有罪、無罪の判断がなされた上で、少年の処分が決定します。
審判によって決定する処分は、不処分、保護処分、検察官送致の何れかです。
それぞれの処分については次回のブログでご紹介します。
お子様が刑事事件を起こしてお悩みの親御様、東京都目黒区の窃盗事件でお子様が警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承るだけでなく、逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービス(有料)を用意し、皆様からのご予約をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都水上安全条例違反が初適用
東京都水上安全条例の新設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
昨年、それまでの東京都水上取締条例の全部が改正されて「東京都水上安全条例」が施行したのをご存知でしょうか?
この条例の改正によって、これまで取締られることのなかった、プレジャーボート等の飲酒及び酒気帯び操縦が厳しく取り締まられるようになり、先日、初の摘発があり、お酒を飲んでプレジャーボートを操縦した男性が書類送検されました。
◇事件◇
先月、男性は、東京都江東区の運河において、知人10数名を同乗させたプレジャーボートを操縦しながら、ハイボール等のアルコール飲料を飲酒しました。
この日、警視庁湾岸警察署が、運河の岸で取締りを行っており、呼気検査によって基準値を超えるアルコール濃度が検出されて検挙されたようです。
(令和元年6月4日付け「TBSNEWS」を参考)
◇東京都水上安全条例◇
冒頭に記載したように、昨年に東京都水上安全条例が施行されるまで、お酒を飲んでプレジャーボート等の小型船舶を操縦した行為を取り締まるための法律は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の小型船舶操縦者の遵守事項でしか規制がありませんでした。
とはいうものの、この遵守事項に違反した場合でも、罰金等の刑事罰の規定はなく、船舶免許に関する行政処分の対象にしかなりませんでした。
お酒を飲んで車を運転した場合ですと、道路交通法違反が適用されて刑事罰の対象となるのに対して、小型船舶の飲酒操縦は、何の法律でも取締りがなされていなかったという実態だったのです。
しかし、2016年の夏に、警視庁が実施した実態調査において、水上オートバイの47%、プレジャーボートの11%で飲酒操縦が確認されたことに裏付けられるように、一部の水上バイク等の小型船舶利用者による、危険な航行や、迷惑行為が社会問題となりつつあり、一部のメディア等でも取り上げられたことによって社会の注目を集めたことや、2020年に東京オリンピックが開催されることを背景に、小型船舶の飲酒運転を厳しく取り締まるための東京都水上安全条例を施行したようです。
~適用条文~
第12条
何人も、水上において、酒気を帯びて小型船舶を操縦してはならない。
~罰則規定~
第26条1項1号(酒酔い操縦)
第12条の規定に違反して小型船舶を操縦した者で、その操縦をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な操縦ができないおそれのある状態をいう。)にあったもの。
「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
第26条3項1号(酒気帯び操縦)
第12条の規定に違反して小型船舶を操縦した者で、その操縦をした場合において身体に公安委員会規則で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
「30万円以下の罰金」
※罰則の対象となるアルコール濃度は、呼気濃度0.15ミリグラム以上です。
ちなみに、警察官によりアルコール検知を拒否したり、検知を妨害した場合は20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(第26条4項1号)
◇東京都水上安全条例違反で検挙されたら◇
自動車の飲酒運転と同様に、東京都水上安全条例違反が発覚すれば、逮捕される可能性がありますが、飲酒検知に応じて、取調べ等の必要な捜査に応じていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし、警察官による検知を免れようとしたり、現場から逃走や、飲酒事実を隠蔽しようとした場合は逮捕されることも考えられます。
何れにしても、取調べ等、警察において必要な捜査を終えると、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官によって起訴されるか否かが決定するのですが、初犯であれば略式罰金となる可能性が非常に高いと考えられます。
~前科になるの?~
起訴された場合、通常であればその後の刑事裁判で刑事罰が決定するのですが、略式罰金の場合は、略式起訴という手続きによって刑事裁判は行われず、指定された罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了します。
略式罰金も「前科」となります。
前科は一般に公表されるものではありませんが、その後の社会生活において不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。
また、前科は捜査機関に記録として残りますので、その後、何らかの犯罪を犯してしまった場合、量刑が重くなる原因にもなりかねません。
東京都水上安全条例違反で検挙されてしまった方、東京都内の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。