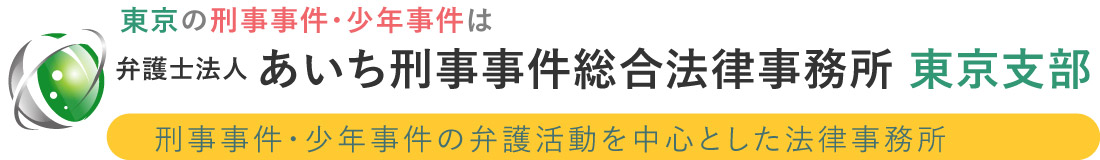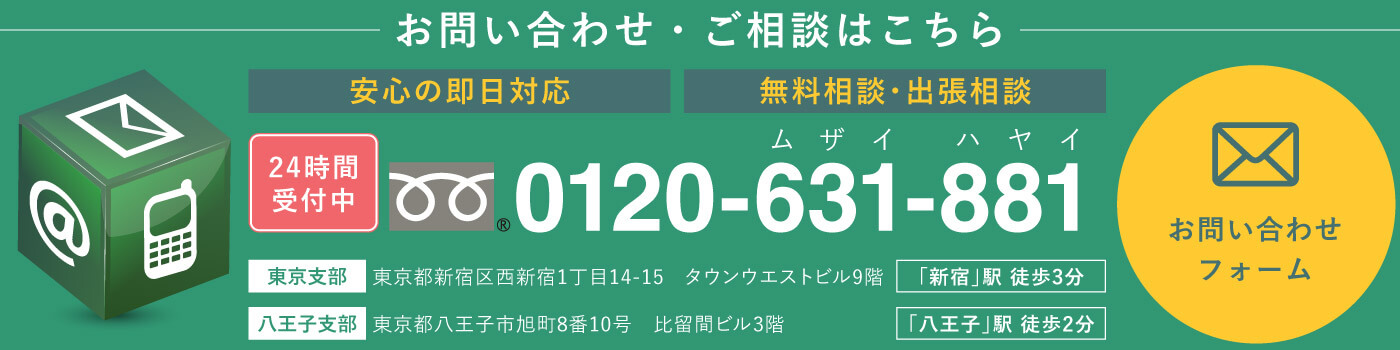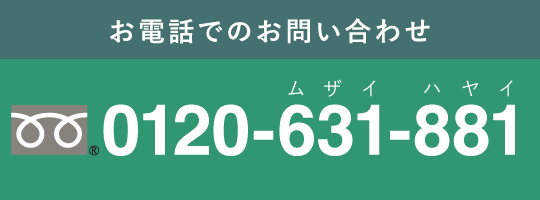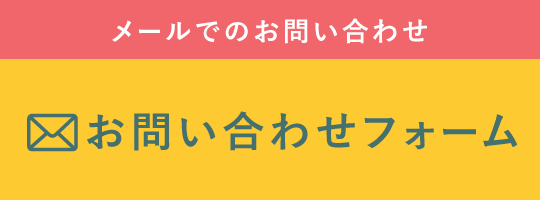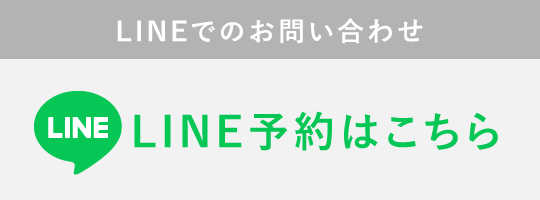先日、警視庁は年末に向けて飲酒運転の取締りを強化する旨を発表しました。
今年も、交通事故による死亡者数は増加傾向にあり、特に東京都内では、飲酒運転による死亡事故が増えているということです。(平成30年11月3日のFNNニュースを参考にしています。)
本日は、飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士が警察の飲酒運転について解説します。
~飲酒運転の発覚~
飲酒運転の検挙は、主に検問によるものですが、それ以外に交通違反や、交通事故など別件の取り扱いが端緒となって飲酒運転が発覚することも少なくありません。
何れにしても、警察官に飲酒を疑われた場合は、飲酒検知によって飲酒量を確認されます。
この検知結果によって飲酒運転かどうかを確かめられるのですが、飲酒量が基準値に満たない場合でも、酒に酔っている状態だと判断されれば「酒酔い運転」になることもあります。
~酒気帯び運転~
飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.15グラム以上のアルコールが検出された場合「酒気帯び運転」となって、免許停止、免許取消の行政処分の他に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
~酒酔い運転~
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に関係なく、酒に酔った状態で車を運転することです。
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に加えて、警察官が違反者に対して質問(名前・年齢・飲酒状況等)したりして、その回答内容や、対応、その他、正常に歩行できるか等によって認定されます。
酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が定められています。