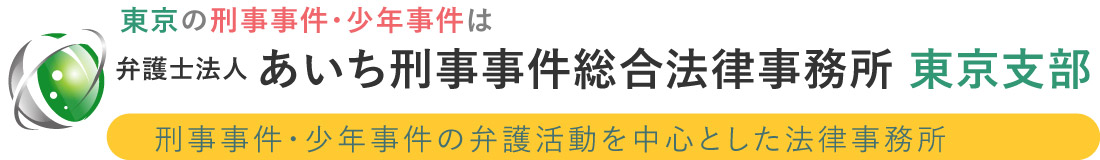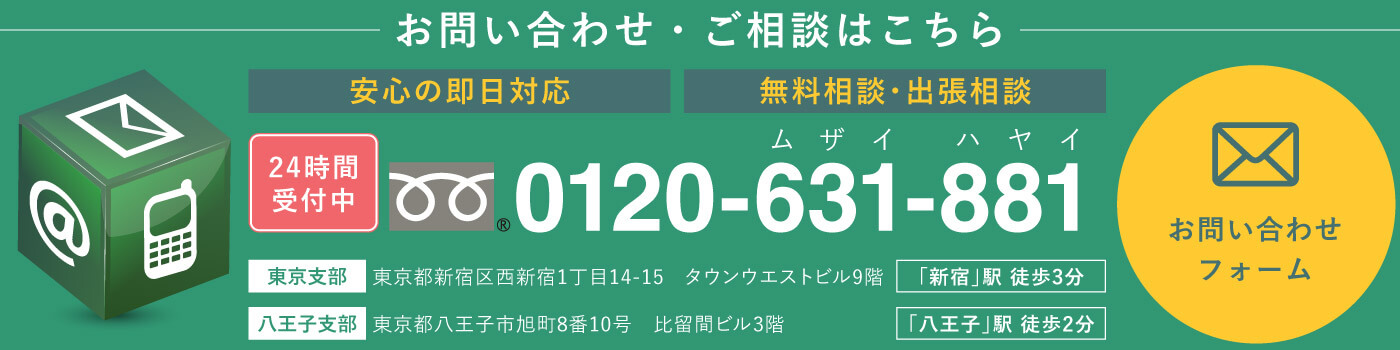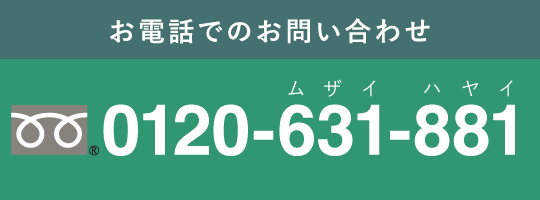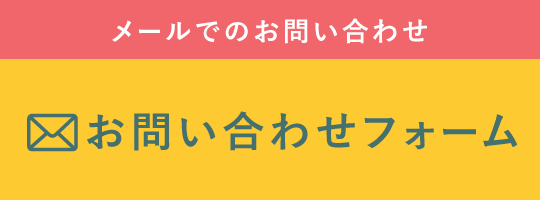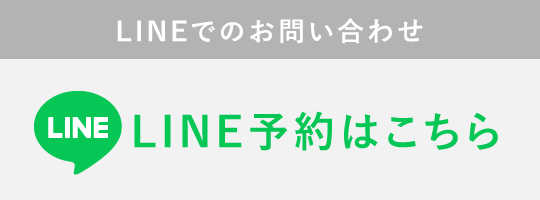Author Archive
男性が痴漢の被害者に
男性が痴漢の被害者に
痴漢事件で男性が被害に遭った場合に問題となる罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都足立区千住在住のAは、足立区内の会社に勤める女性会社員です。
満員電車に乗っていたAは、同じ車両に乗っていた会社員男性Vに対し、ズボンの上から陰部を触るなどのいわゆる痴漢行為をしてしまいました。
被害者であるVが声を上げ、次の駅で降ろされたAは、駅員の通報により臨場した足立区内を管轄する千住警察署の警察官に促され、任意で取調べを受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【男性が痴漢の被害に遭うことも】
痴漢事件というと、加害者側が男性、被害者側が女性という印象が強いと思います。
実際の事件でもそれが大半であることは事実ですが、男性が被害に遭う痴漢事件というものも実在します。
ケースは加害者を女性、被害者を男性としましたが、加害者も被害者も男性、あるいは女性ということも考えられます。
ケースは東京都足立区での痴漢事件を想定していますので、東京都が定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
【示談交渉について】
痴漢事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するかたちで、その内容は示談書・合意書といった書面で締結されることが一般的です。
その内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。
示談交渉は必ず弁護士が行わなければならない事項ではなく、例えば当事者間で示談交渉を行うことは可能です。(第三者が関与した場合、非弁行為にあたるため注意が必要です。)
しかし、性犯罪や暴力事件等において、被害者が加害者と直接連絡をとることは心理的負担が大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません。
そこで、加害者側が代理人を立てるか、被害者側が代理人をたてる必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側は代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて、示談交渉に臨む必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件についての無料相談・弁護活動に対応してきました。
痴漢と呼ばれる事件に対して、軽微な犯罪であると思っている方も居られるようですが、被害者にとっては忘れられない傷にもなり得る事件であり、加害者側としては誠実な対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができますので、まずは御相談を受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
他人に体液をかけた場合の罪
他人に体液をかけた場合の罪
他人に体液をかけた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都世田谷区在住のAは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは職場での上司との対立からストレスが溜まり、そのストレス発散のため、自分の体液(尿)をフィルムキャップに入れ、世田谷区内を深夜歩いている異性めがけて顔面に掛け、逃走するという事件を繰り返し起こしていました。
ある日、Aの自宅に世田谷区を管轄する世田谷警察署の警察官が来て、家宅捜索を行い、Aを他人に体液をかけた嫌疑で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【体液をかけて器物損壊罪?】
事例でAが行った体液をかけるという事件で成立しうる犯罪の1つが、器物損壊罪です。
刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
一般に、器物損壊罪の「損壊」とは、広く物本来の効用を失わせしめる行為を含むものをされています。
例えば硫酸を服に掛けるなどして服を溶かすようなかたちで物理的に破壊してしまうことは、いわずもがな「損壊」に当たると言えます。
ケースの場合、被害者はAの体液をかけられているので、このように物理的な破壊行為は行われていません。
しかし、他人の体液をかけられた衣服やカバンなどの持ち物をまた着用しようと考える人は多くないでしょう。
このような場合、物理的な破壊はありませんが、体液がかかった洋服や持ち物は「効用を害された」として、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪は、「親告罪」いって、被害者等からの刑事告訴がなければ検察官は起訴できない罪です。
つまり、起訴される前に告訴を取り下げてもらったり告訴をしないという合意を交わすことができれば、不起訴処分を獲得できることになります。
しかし、特に今回のAのような体液をかけるようなかたちで行われた器物損壊事件では、被疑者(加害者)やその家族が被害者の連絡先を教えてもらえる可能性は極めて少ないと言えます。
そのため、被疑者は第三者である弁護士に依頼をして、示談交渉を進めていくことになります。
【体液をかけて暴行罪?】
Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体にかかった場合には、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対して不法な有形力の行使をすることを指します。
一般によくイメージされる、他人を殴ったり蹴ったりして直接的に暴力を振るうことももちろん暴行罪の「暴行」に当たります。
これに加えて、他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭和46.10.11)。
このように暴行罪の「暴行」を考えると、体液を他人にかけるという行為でも暴行罪が成立する可能性があることがお分かりいただけると思います。
暴行罪は、器物損壊罪とは異なり親告罪ではありません。
そのため、被害者と示談ができたからといって必ずしも不起訴処分を獲得できるとは限りません。
しかし、被害者への謝罪・弁償ができているかどうか、被害者の処罰感情のおさまりがあるのかどうかといった事情は、起訴・不起訴を大きく左右します。
また、逮捕されてしまっているような場合には、釈放を求める弁護活動の際にも(被疑者にとって)有利な事情となりますから、器物損壊事件の際と同様に、刑事事件を専門とする弁護士に相談・依頼することが効果的でしょう。
東京都世田谷区にて、御自身が他人に体液をかけて捜査を受けている、あるいは家族が体液をかけた嫌疑で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
電話を受けた担当事務員が、無料相談等の手続きについて御案内します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
万引き事件で現行犯逮捕
万引き事件で現行犯逮捕
陳列されている商品などを盗む、いわゆる万引き事件で問題となる罪と現行犯逮捕という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都世田谷区在住のAは、いわゆる専業主婦(主夫)として生活をしていました。
Aは世帯主から厳格に生活費の制限を受けていましたが、事件当日は月末であまりお金がありませんでした。
しかし、前から欲しいと思っていた商品が偶然入荷されていることに気付き、我慢が出来ずに万引きしてしまいました。
Aの万引き行為に気付いた店の店員は、Aが店を出たタイミングで声掛けし、Aが万引きを認めたため、警察署に通報し、臨場した世田谷区内を管轄する成城警察署の警察官に引き渡されました。
成城警察署の警察官は、Aを万引き事件を起こした嫌疑で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引き事件について】
ご案内のとおり、お店に陳列している商品などを購入せずに持ち出す行為は万引きと呼ばれ、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
万引きを軽視している方も居られるようですが、初犯であっても罰金刑などの刑事罰が科せられる可能性が高く、前科がある場合には罰金額が上がるだけではなく懲役刑が科せられる場合もあります。
また、万引き事件の特徴の一つとして、店舗側が示談交渉を拒否する、あるいは商品の買取のみ行う、といった場合が多い点が挙げられます。
店舗側も万引き被害は死活問題で、店によっては防犯カメラやゲートの設置、店員・万引きGメンによる監視活動の強化など、対策に費用をかけています。
一般の方が直接示談交渉することが難しいことは言わずもがな、弁護士が代理人となって示談交渉を行った場合でも、示談等を拒否される場合は少なくありません。
【現行犯逮捕とは】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。
一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ケースのように被疑者とされる方が現行犯逮捕などで身柄拘束されている場合、弁護士が警察署に赴いて弁護士接見を行い、状況や見通しについて依頼者に御報告する初回接見を行っています。
東京都世田谷区にて、御家族が万引き等の刑事事件を起こしてしまい現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
闇バイト―初犯でも実刑判決?
闇バイト―初犯でも実刑判決?
いわゆる闇バイトに手を染めてしまったという場合に問題となる罪と、初犯か否かという点と実刑判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都杉並区在住のAは、都内の専門学校に通う21歳の学生です。
Aは浪費家で家族に言っていない借金が増え、返済が滞っていました。
そこで、「高額バイト」「闇バイト」などと書かれているツイートを探し、投稿主とやりとりして内容を聞きました。
その内容は、受け取ったキャッシュカードで現金を引き出し、紙袋に入れて駅のコインロッカーに入れるというものでした。
Aは予めその内容を調べていわゆる特殊詐欺の出し子としての作業であることに気付きましたが、指示に従い指定されたコインロッカーを開けてキャッシュカードを取り出し、近くのATMで残高を全て引き出したうえで元のコインロッカーに金を入れ、キャッシュカードは駅のゴミ箱に捨てました。
数ヶ月後、杉並区を管轄する杉並警察署の警察官がAの自宅に来て、特殊詐欺の受け子をした嫌疑で逮捕しました。
Aの家族は、Aの接見をした弁護士から「前科はないようですが金額次第で実刑判決も考えられます。」と説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【高額バイト・闇バイトに注意】
「オレオレ詐欺」「お母さん助けて詐欺」「振り込め詐欺」など、これまで様々な言葉で紹介されている特殊詐欺ですが、未だにその被害は後を絶ちません。
昨年(2020年―令和2年)に発生した特殊詐欺の認知件数は1万3526件で、被害総額は約277億8000万円でした。
あくまで認知件数であり、実際に被害に遭われた方はそれ以上に居られる可能性もあります。
特殊詐欺は、その多くが「架け子」「受け子」「出し子」といった役割に分かれます。
架け子は最初に電話を架けて被害者が受け子に現金やキャッシュカードなどを渡すよう要求し、受け子が被害者宅などに行って現金やキャッシュカードを受け取ります。
出し子は、受け取ったキャッシュカードを使ってATM等で現金を引き出すか、別の口座に送金するという役割を担います。
後者については、いくつかの口座を転々とさせることで実際に金を受け取る者が分からないようにする目的があります。
ケースのように「高額バイト」「闇バイト」などと称して募集される人員は、多くが受け子や出し子といった検挙されやすい役割を任されます。
受け子や出し子については、事前に言われていた金額を受け取ることができたという場合があるようですが、実際にはお金を受け取れなかったという場合も少なくないようです。
出し子の場合、現金を引き出した場合には窃盗罪が、口座から口座に送金をするなどした場合には電子計算機使用詐欺罪が、それぞれ成立します。
罰条は以下のとおりです。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)
電子計算機使用詐欺罪:10年以下の懲役(刑法246条の2)
【前科がなくても実刑判決に?】
前科、あるいは前歴というのは、法律上の言葉ではなく、その定義があるわけではありませんが、その多くが
前科:刑事事件で有罪判決を受けた場合を指します(執行猶予付有罪判決や略式手続による罰金刑・科料を含む)
前歴:逮捕された、あるいは在宅で捜査を受けたものの不起訴になるなどして刑事罰が科せられなかった場合を指します。
刑事裁判では、裁判官が被告人の有罪/無罪と、有罪だった場合の量刑を決めます。
その際、被告人に前科があるのかないのかという点は重要視されます。
一般に、前科があればより厳しい刑事罰を科せられます。
ケースの場合、Aには前科がないことを前提としています。
しかし、前科がないからといって必ずしも執行猶予付の判決が科せられる、という訳ではありません。
とりわけ特殊詐欺は社会問題であり、刑事裁判では厳罰化の傾向にある犯罪です。
特殊詐欺事件の場合、被害金額や役割次第では、前科がなくても実刑判決を受ける可能性が十分にあります。
東京都杉並区にて、高額バイトや裏バイトなどといって特殊詐欺の出し子や受け子に加担してしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、事件の内容と前科の有無を確認した上で、実刑判決など厳しい
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
侮辱罪で略式手続を回避
侮辱罪で略式手続を回避
名誉毀損罪や侮辱罪などに当たる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区在住のAは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aは、近隣住民のVが犬の散歩をする際に、Aの家の塀に小便をかける行為を気にかけていて、再三注意していましたが、その後もVの犬はAの家の塀に小便を掛け続けていました。
我慢ができなくなったAは、防犯カメラの映像を用いて小便をしている犬とそのリードを持つVの画像を抽出し、「台東区の小便掛けババア」という文言を加えてポスターにし、それを路上から他人が見られるような状態でAの家の塀に複数枚、貼り付けました。
Vからの告訴状を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aに「このままでは罰金などの刑事罰になる可能性がありますよ」と説明しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【名誉毀損罪・侮辱罪について】
ケースのAは、自分の家の塀とはいえ、不特定且つ多数の者が見られるような状態で、Vを揶揄するようなポスターを貼っています。
このような行為をした場合、名誉に対する罪が問題となります。
今回は、名誉毀損罪又は侮辱罪の適用が考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
今回の場合、Aの言動(ポスター記載の文言)は「台東区の小便掛けババア」というもので、事実を摘示しているとは言えず、名誉毀損罪は成立しません。
しかし、Vの飼い犬が小便を掛けている画像と共に上記のような文言を書き加えて他人に見えるようにする行為は、Vを侮辱する行為と言えますので、侮辱罪は成立すると考えられます。
【略式手続について】
法治国家である我が国では、原則として公開の裁判で有罪判決を受けた場合にのみ刑罰を科せられます。
ただし、比較的軽微な刑事事件については、公開の法廷での裁判になしに刑罰を科すことができます。
これを、略式手続と呼びます。
略式手続は、通常の裁判と同様に警察官や検察官が証拠を収集したり取調べを行うなどして、通常の公判請求と同様の捜査を行います。
その後、担当検察官は略式手続が適当と判断した場合には、被疑者に対して略受けと呼ばれる書類を作成するよう伝えます。
被疑者は、事件について認めていて、略式手続に納得した場合には、略受けの書類に署名・捺印します。
最終的に、検察官は簡易裁判所に対して略式起訴をすると同時に「百万円以下の罰金又は科料」の範囲で求刑を行い、簡易裁判所は書類だけで判断をして被告人に対して判決文と納付書を交付します。
略式手続は書面のみでのやり取りという点で、公開の法廷で行われる通常の裁判と比べて被疑者の負担は少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金・科料という刑罰もいわゆる前科の一種ですので、できる限り避けたいとお思いの方もおられるでしょう。
刑事事件の場合、手続きが進むにつれてできる弁護活動が少なくなるという恐れがあります。
身柄拘束されている事件はもとより、ケースのような在宅事件の場合でも、すぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都台東区にて、張り紙などにより侮辱罪や名誉毀損罪に問われていて、略式手続により前科が付く可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
逮捕されたらすぐに初回接見を
逮捕されたらすぐに初回接見を
痴漢事件で逮捕された場合に問題となる罪と、初回接見のシステムについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都新宿区在住のAは、新宿区内の会社に勤める会社員です。
Aは深夜の新宿区内の路上にて自分のタイプの相手を見つけては、小走りで駆け寄って臀部(お尻)を触り、走ってその場から逃走する、という行為を繰り返していました。
ある日、Aの自宅に新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官が来て、Aは痴漢の嫌疑で通常逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【痴漢について】
痴漢というと電車内での痴漢を想起しがちですが、路上やエレベーターの中など、いろいろな場所での痴漢事件が考えられます。
痴漢は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースの場合は東京都新宿区を想定した痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
【初回接見について】
刑事事件を起こした場合、捜査機関は一定の要件を満たしている場合に、必要に応じて被疑者(加害者)を逮捕することができます。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
そして、勾留請求をされた場合、裁判所の勾留裁判官は勾留質問を行い、被疑者に勾留が必要であると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り延長することが出来るため最大で20日間の身柄拘束がなされます。
逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
弁護士が接見する場合については、私選弁護人と当番弁護士、勾留決定後に要請できる国選弁護人がいます。
このうち当番弁護士は、逮捕後すぐに要請できる弁護士ですが、その接見は一度限りです。
国選弁護人は、被疑者の資力が50万円未満の場合に要請できます。
基本的に被疑者はこの当番弁護士と国選弁護人のみ要請することが出来る一方、私選弁護人は被疑者の御家族の方などしか依頼することができません。
そこで弊所では、初回接見サービスという有料サービスを行っています。
初回接見は、1度に限り、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている被疑者のもとに接見に赴き、①事件の概要を被疑者から聞き、②被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、③ご依頼者様に説明をする、というシステムです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、24時間電話対応事務を設置し、初回接見費用のお振込みをお願いしてから原則として24時間以内に初回接見を行っています。
昨年(2020年)だけで、全国500件以上の初回接見に対応しており、それらの経験に基づいた経験と知識から、的確なアドバイスを行うとともに見通しなどについて説明致します。
東京都新宿区にて、御家族が痴漢などの刑事事件を起こしてしまい逮捕されたという知らせを受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
相談電話担当者により、初回接見の金額や手続きの御案内を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
交通事故を起こしたら刑事?民事?
交通事故を起こしたら刑事?民事?
交通事故を起こしてしまった場合に問題となる刑事・民事の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江東区在住のAは、江東区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、江東区内の路上は朝の渋滞で混雑していたため、バイクに乗っていたAはいわゆるすり抜けを行うかたちで前進していました。
その際、歩行者Vが横断歩道ではない場所を渡ろうとしていることに気付かず、Vに衝突してしまいました。
Vは転倒してしまい、救急搬送されました。
Aの通報により臨場した江東区北砂を管轄する城東警察署の警察官は、Aに任意同行を求め、警察署での取調べを行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【人身事故について】
車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。
・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。
罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。
自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。
・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。
また、乍ら運転や一時停止義務違反などの交通違反については、反則金を納付する必要があります。
【保険会社だけでは不十分?】
弊所には、これまで「任意保険に加入しているからと安心していたら刑事罰が科せられることになった」といった相談が数多く寄せられてきました。
しかし、前章で説明したとおり、刑事事件の手続きと民事上の責任は別物ですので、前科を回避したい、刑事罰に処せられたくないという場合には然るべき対応を取る必要があります。
例えば、
・民事上の責任とは別に、被害者に対して謝罪と弁済を行うことで「宥恕」という被害者が加害者を許す旨の約定を盛り込んだ示談書を締結する
・事件後に自車を廃車にした、交通定期券を購入して自動車に極力乗らない環境を整えた、といった事情を盛り込んだ意見書を提出する。
等が考えられます。
検察官から「このままでは罰金などの刑事罰に処せられます。」という説明を受けた方が、弁護士に依頼をして上記のような対応をとったことで不起訴になった、という事案もあります。
東京都江東区内にて、人身事故を起こしてしまい警察官や検察官からの取調べを受けている方、刑事上の責任についてよくわからないという方は、一度刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
食い逃げで刑事事件?民事事件?
食い逃げで刑事事件?民事事件?
食い逃げをした場合に問題となる罪と、刑事事件・民事事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江東区在住のAは、江東区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒を飲んで酔っ払った状態で飲食店に行き、食事をしました。
しかし、Aには支払う金がなかったため、店員がホールに居なくなったところを見計らって席を離れました。
しかし、店員はすぐに気が付き店の近くでAを発見して料金を支払うよう告げたところ、Aが「金を持っていない」と言ったため、江東区を管轄する城東警察署に通報しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【食い逃げで問題となる罪】
食い逃げというと、まず窃盗罪を思い浮かべる方がいるかもしれません。
しかし、窃盗罪は所有者の意に反して物を持ち去る行為を意味します。
食い逃げの場合は店員が食事を提供しているため、窃盗罪には当たりません。
食い逃げで成立する可能性がある罪としては、詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、
⑴Aが店員を欺罔し(騙し)
⑵店員が錯誤に陥り(騙され)
⑶店員がAに料理を提供/店員がAに代金請求を行わない
⑷一連の行為に因果関係が認められる
場合に、成立します。
問題は、⑴が認められるかどうか、という点です。
先ず、料理の注文をする時点でAが自分に所持金がないことを把握していた場合を想定します。
Aに所持金がない場合、店員は当然、料理を提供しません。
よってAが食事を注文した場合、店員はAに所持金があるから注文をしていると誤認して、料理を提供します。
この場合、Aの注文という欺罔行為により⑴、店員は錯誤に陥り⑵食事を提供していて⑶、⑴~⑶に因果関係が認められるため⑷、詐欺罪が成立します。
次に、所持金がないことに気付かずに注文した場合について検討します。
Aは酒に酔っていたという状況から、その前に別の店で飲食をして所持金を使い果たしたところ、酒に酔っていてそれを忘れていたという可能性が考えられます。
所持金がないことに気付かず食事を注文した場合、Aの店員に対する欺罔行為⑴が存在しないため、たとえ店員が食事を提供したとしても詐欺罪は成立しません。
但し、逃走する際に「電話に出てきます。」「タバコを吸ってきます。」などと店員に嘘をついて店を出た場合、それ自体が欺罔行為になり⑴、店員がそれを信じてしまい⑵、代金の支払い請求を行わなかった⑶、ということになり、2項詐欺と呼ばれる財産上の利益を得るかたちでの詐欺罪が成立します。
【刑事事件と民事事件】
上記では、食い逃げが刑事事件に当たるかどうかについて解説致しました。
刑事事件は、刑法などの各種法律に規定されている条文に違反した場合に、捜査機関(警察官、検察官など)による捜査を受けたうえで、刑事裁判を受けて刑事罰を科せられる等の手続きが進められていきます。
裁判になった場合、被告人は死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取といった刑事罰が言い渡されます。
刑事罰のひとつである罰金刑や科料は財産刑ですが、そのお金は被害者等に渡るわけではなく、国庫に帰属します。
前述のとおり、食い逃げは必ず刑事事件(詐欺罪)になるわけではありません。
また、仮にAが刑事事件に発展して刑事罰を受けたとしても、飲食店側には何らメリットがなく、飲食代金が支払われないだけでなく捜査協力により時間を要するなどの負担が増すばかりです。
飲食店側がAに代金や時間・精神的な負担について賠償を求める場合、飲食店側が代金支払請求や損害賠償請求といったかたちで、当事者間(ケースの場合は飲食店とA)の紛争・解決に発展させる必要があります。
これが民事事件です。
刑事事件と民事事件は要件や手続きが異なるため、刑事事件には発展しないが民事事件に発展する、あるいはその逆ということもあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都江東区にて、食い逃げ事件を起こしてしまい、刑事事件に発展する可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
盗撮事件で逃亡した場合
盗撮事件で逃亡した場合
盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、逃亡した場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都練馬区在住のAは、練馬区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは職場に向かうため練馬区内の鉄道駅にいたところ、好みのタイプの女性Vがエスカレーターに向かっていくところを目撃しました。
Aは最初Vの後ろに立ってスカートの中の太股を見ようと考えましたが、それだけでは満足が出来ず、スマートフォンのカメラ機能を使ってスカートの中を撮影しようとしました。
しかし、後ろに立っていた通勤客がAの盗撮行為に気付き、何をやっているんだと声をかけてAの手首を掴みました。
Aは怖くなってその場から逃亡してしまいましたが、数日後、練馬区を管轄する石神井警察署の警察官があの自宅に来て、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮について】
公共の場所でスカートの中などを盗撮する行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては東京都練馬区を想定しているため、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【逃亡した場合の問題点】
Aは盗撮行為をしたうえで、その場から逃亡しています。
刑事事件を起こした場合に被害者や目撃者から声をかけられた場合に、冷静でいられる人は少ないかもしれません。
しかし、冷静さを欠いて逃亡した場合には、様々な問題が生じてしまいます。
・誰かを怪我させる
東京都にある鉄道駅の多くは、乗降客数の多い場合がほとんどです。
そのような場所で走ることで、他人にぶつかってしまい、ともすれば怪我をさせてしまったり死亡させてしまう恐れがあります。
故意ではない場合でも、不注意で誰かを怪我させたり死亡させてしまったりした場合には、過失致死傷罪が適用されます。
(過失傷害罪)
罰条;30万円以下の罰金又は科料
(過失致死罪)
罰条:50万円以下の罰金
・振り払った相手が怪我した場合には更に重い罪に
ケースでは、Aの後ろに立っていた通勤客が目撃者となり、Aの手を掴んでいます。
もし、Aがこの手を振りほどくなどした場合には暴行罪が成立しますし、その結果転倒するなどして怪我したり死亡したりした場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立します。
(暴行罪)
罰条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(傷害罪)
罰条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(傷害致死罪)
罰条:3年以上の有期懲役
・逃亡により身柄拘束のリスクが高まる
刑事事件を起こした被疑者自身が逃亡することについてそれ自体が罪に当たるわけではありません。
しかし、逃亡した場合には、逮捕される可能性が高くなります。
また、逮捕後72時間以内に勾留の手続きが進められるか釈放されることになりますが、実際に現場から逃亡したことを理由に逃亡の恐れがあると評価され、勾留される居可能性が高くなります。
駅構内での事件の場合、防犯カメラの映像や交通系ICの履歴などから、早期に特定される可能性が高いと言えます。
東京都練馬区にて盗撮事件を起こして逃亡してしまった場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
壁への落書きで少年が逮捕される?
壁への落書きで少年が逮捕される?
壁に落書きした場合に問題となる罪と、少年が逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都板橋区在住のAは、板橋区内の会社に勤める19歳の会社員です。
Aは友人と一緒に夜遊びをしていた際、友人から落書きをしないかと言われました。
最初Aは躊躇していましたが、友人から「他の人もやっていて周りには落書きだらけじゃないか」「スプレーは、専用の溶剤で落とせば綺麗に消えるし、壊すわけじゃないんだから」と言われて納得してしまい、閉店後の商店のシャッターや他人の家の塀、公衆トイレの壁、道路のガードレール、他人の車にスプレーで落書きをしました。
ある日、Aやその友人が落書きをしていたところ、板橋区を管轄する志村警察署の警察官がパトロールをしていて落書き行為を現認し、Aらは逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【スプレーでの落書きは刑事事件に】
高架下やガードレール、商店などのシャッターなど、街中の様々な場所で文字やイラストを見かけることがあるでしょう。
そのほとんどが、所有者や管理者の許可なくスプレーなどで行われた落書きであり、刑事事件や民事事件に発展する行為です。
スプレーで行う落書きの刑事事件の側面について、落書きの対象が建物や壁なのか、それ以外の物なのかによって該当する罪が異なります。
まず、建造物を損壊した場合に成立する建造物損壊罪について、罰条は「5年以下の懲役」のみ定められていて、後述する器物損壊罪と比較すると極めて重い刑罰と言えます。
建造物損壊罪は、建造物を損壊した場合にのみ成立します。
他人の家の壁や公衆トイレなどの壁などは建造物に当たりますが、商店のシャッターや住居の塀については、「当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮」して判断されます。
該当するシャッターや壁が、簡単に取り外しできないようなものであり、建造物にとって重要な機能を果たしていると評価された場合には、建造物に当たると評価されます。
次に、ガードレールや他人の車など、建造物(及び文書等毀損罪を除く)に行った落書きの場合には、器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は、刑法261条に違反し、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処されます。
Aは友人から「スプレーは、専用の溶剤で落とせば綺麗に消えるし、壊すわけじゃないんだから」と言われています。
これについて、損壊とは単純に物を破壊したり形を変えたりする場合だけでなく、物の「効用を害する」場合に成立します。
商店のシャッターや自宅の塀に落書きをされた被害者は、恥ずかしい思いをしてすぐに消したいと思うことでしょう。
例えば、水をかければすぐに落ちるような成分のスプレーであれば、損壊にはあたらないと評価される余地があります。
しかし、「専用の溶剤で落とせば綺麗に消える」スプレーで行った落書きであれば、すぐに消すことができないという性質を踏まえ、「損壊」したと評価されます。
なお、我が国でも数年前に海外の有名な画家によるストリートアートと呼ばれるものが話題となりました。
これについては、その建物や物の所有者の捉え方次第と言えます。
所有者が「損壊」を受けたと感じた場合、建造物損壊罪は非親告罪ですので被害届を、器物損壊罪は親告罪ですので刑事告訴をすることで捜査機関による捜査が開始され、被疑者が特定された場合には刑事罰が科せられることがある、という流れになります。
※落書きの内容によって特定の相手を侮辱した場合や名誉を棄損した場合については、建造物損壊罪や器物損壊罪だけでなく、侮辱罪や名誉棄損罪などの罪にもあたります。
(建造物等損壊罪)
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【少年も逮捕される?】
≪次回のブログに続きます。≫
東京都板橋区にて、お子さんが商店のシャッターや公衆トイレの壁、他人の家の塀、道路のガードレール、他人の車などに落書きをして逮捕されてしまった場合、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。