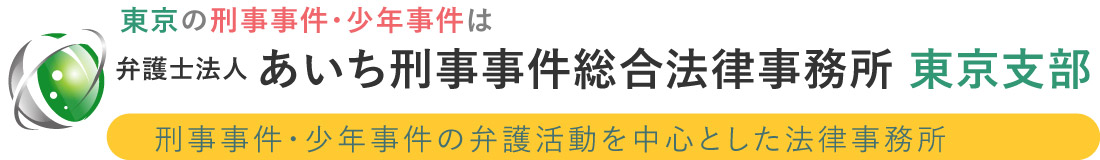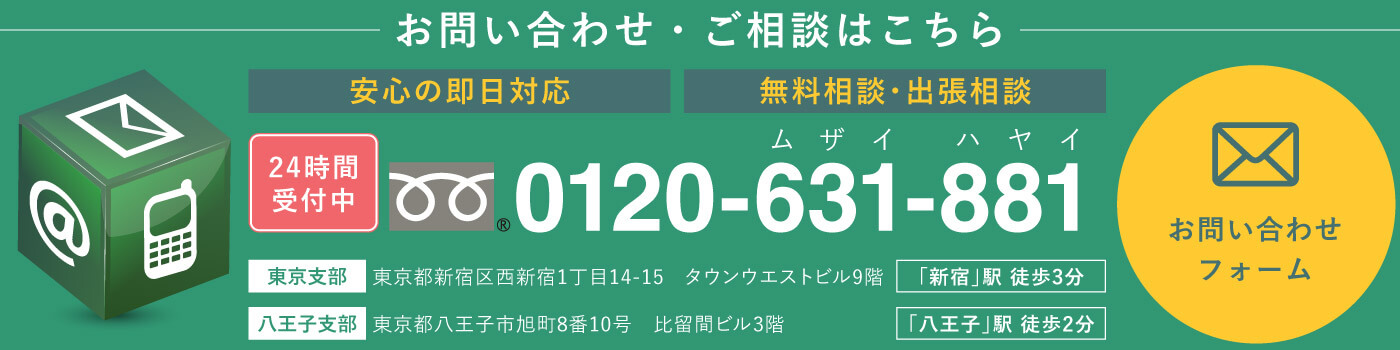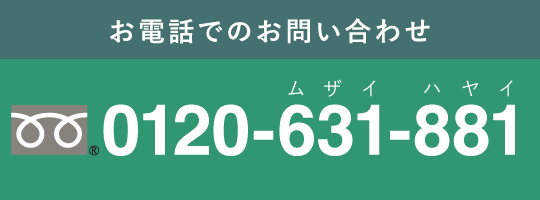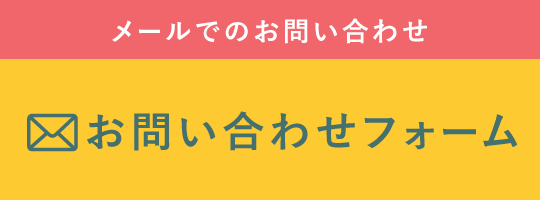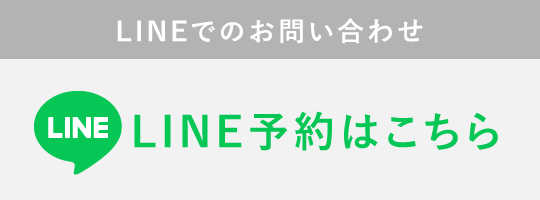Archive for the ‘薬物事件’ Category
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】
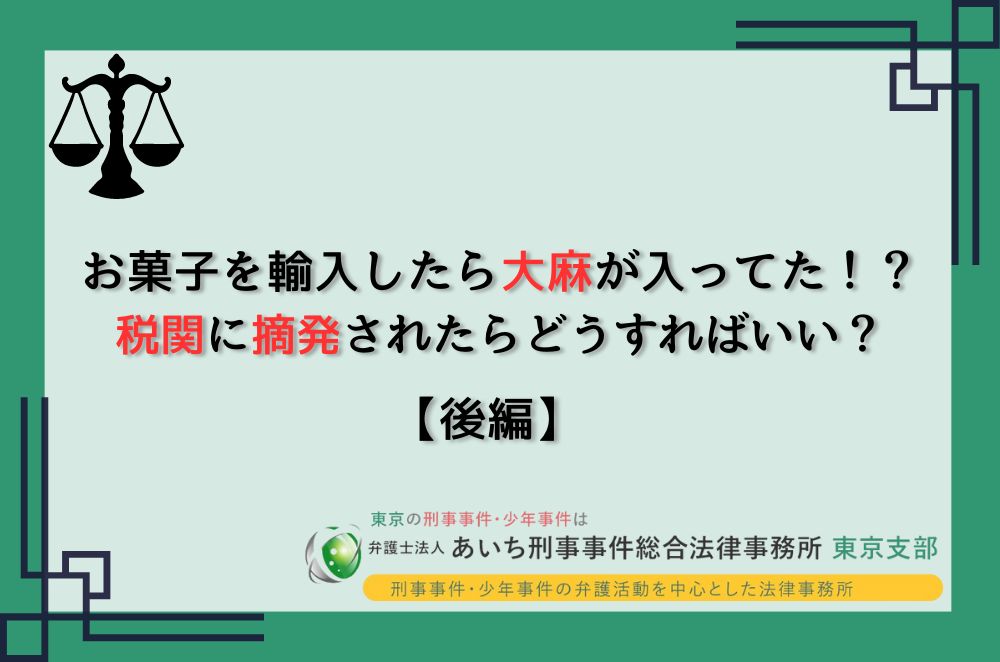
前回記事に引き続き、今回も大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
大麻取締法によって規制されているものを海外から購入して帰国してしまうと、大麻取締法違反だけでなく、関税法にも違反してしまう可能性があります。
後編では、海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について見ていきましょう。
【事例】
事例については前回記事をご覧ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
【お土産を買ったら薬物の輸入?】
Aさんの事例のように、お土産のお菓子だと思って買ったものが大麻や違法薬物だったという事例は少なくありません。
大麻取締法の大麻の輸入に対しては、7年以下の懲役が定められています。
また、大麻のような違法薬物を貨物として日本に持ち込もうとした場合、関税法という法律にも違反する可能性があります。
関税法とは、日本に輸入するものや輸出するものに対する関税という税金について規定をした法律ですが、日本に持ち込んではいけないものについても規定しています。
違法薬物を日本に持ち込もうとした場合には、関税法違反として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。
つまり、「日本の友達に海外の珍しいものをお土産に買ってあげた」つもりが、懲役刑や1000万円近い罰金の対象となってしまうことがありうるのです。
特に、CBDや大麻に関する日本の規制は目まぐるしく変化しており、これまで規制対象ではなかったものがいつの間にか違法なものになっていたというのも珍しくありません。
薬物の輸入事案は、起訴までされてしまうと、前科がない方であったとしても、いきなり実刑判決(刑務所)を受けてしまう可能性が高く、逮捕される可能性も同様に高い事案です。
「どうなるかわからない」、「不安だ」という方は、一刻も早く専門の弁護士に相談しましょう。
【税関から連絡が来たら?】
Aさんの事例のように、税関から連絡が来た場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。
税関というのは、日本に届いた荷物に対してどのような処理をするか/税金をかけるのかということを司る官庁です。
つまり、警察や検察、麻薬取締局のような捜査をメインとした機関ではないということです。
そのため、「税関から連絡が来た」という段階でどのような対応をするのかという点が非常に重要になります。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
税関から通知が来ているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、上の3つに上げたような最良の結果を獲得してきた経験があります。
素人判断で進めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 薬物の輸入だと疑われているが、身に覚えはない
- 税関から厳しく調査されていてこれから不安だ
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して対応を依頼したほうが良いでしょう。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻の輸入を疑われた事案について解説致しました。
特に近年、薬物輸入の件数が増加しているようですが、「CBDは絶対に摘発されない」等といった誤った見識が広まっているのも理由の一つかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都内で、薬物輸入事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京空港警察署までの初回接見は税込33,000円(東京支部の場合)で行っています。
ご相談・ご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
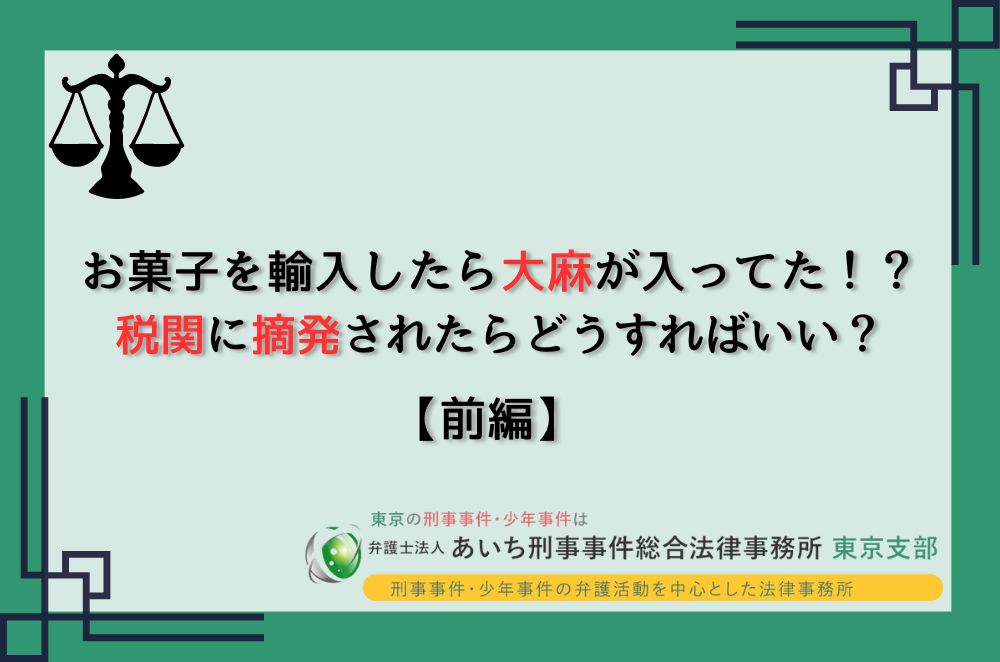
近年、大麻成分が含まれたお菓子が販売されることが増え、度々問題になっています。
今回は、違法なものだと知らずに海外で大麻成分が含まれたお菓子を購入して帰国した事例をもとに、大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
前編では大麻取締法によって規制対象となっているもの、後編では海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について解説していきます。
【事例】
※本記事は違法薬物の所持、使用を推奨するものではなく、大麻取締法違反及び関税法違反に関して令和6年3月時点における法律知識を提供するものです。
違法薬物についてお困りのことがある方は、弁護士までご相談下さい。
(※以下の事例は全てフィクションです。)
Aさんはアメリカへ旅行へ行き、友達へのお土産にとCBD入りのグミを購入しました。
日本へ帰国する際、Aさんはお土産の一切をトランクケースに入れ、飛行機の預け入れ荷物として持ち込むことにしました。
Aさんは羽田空港から帰国し、預けていたトランクを受け取ろうとしたところ、「預け入れたトランクを貨物に載せられなかったので、後日お届けします」と伝えられました。
後日、Aさん宛に羽田空港の税関から「あなたの荷物についてお伺いしたいことがありますので、連絡をください」との手紙が届きました。
Aさんは、「お土産に買ったCBDグミになにか違法なものがあったのでは…」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【CBDと大麻の規制】
近年、CBDショップやベイプショップと呼ばれるような店舗が見られるようになりました。
タバコのような嗜好品の一種と見られているようですが、電子タバコのように見えるものであっても、実際には違法薬物を販売していたという事例があとを立ちません。
(参考記事:『朝日新聞』配信「大麻リキッド販売容疑 自称「国内最大チェーン」20数店を一斉捜索」)
これらは、大麻取締法違反として摘発をされています。
大麻と聞くと、「葉っぱ/葉巻みたいなもの」というイメージを持たれるかもしれませんが、大麻取締法によって規制されているのは、「葉っぱ」に限りません。
大麻取締法によって規制されているものは、大麻草という植物の「茎と種を除いた部分」やそれらに由来する製品をいうものです。
植物のうち「茎と種」を除いたところになりますから、その多くが「葉っぱ」ということになりますが、それ以外にも「根」や「花」の部分も大麻取締法によって規制されている「大麻」ということになります。
法律によって規制されている「大麻」の部分には、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
一方、大麻草には「CBD」という成分も含まれています。
CBD成分は大麻取締法によって規制はされていませんが、「大麻」に含まれるTHCと似た作用があると言われています。
そのため、CBDオイルは「合法ドラッグ」などと言われ、違法薬物に似た成分であるものの規制の対象にならないという理由から、一部で広まりつつあるようです。
世間においても「CBDは違法じゃないから捕まらない」という知識が独り歩きしているようですが、報道にもあるように、実際に販売されている商品にはTHCや、HHC、THC-Oと言われるような大麻取締法より重い麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている「指定薬物」に該当するような成分が含まれているということまであります。
「合法なCBDだと思って買ったら麻薬扱いの製品だった」、つまり合法なものと違法薬物を区別するのは一般人にとっては困難ということです。
CBDは規制の対象外とされているため、電子タバコだけでなく、様々な形状で販売されていることがあります。
海外においては、Aさんの事例のようにお菓子や食品に含まれていたり、バターや食用油のような調味料の一部に含まれているということもあるのです。
THCもCBDも、成分、薬物効果としては似ているものになりますが、大麻取締法の規制となる場合や麻薬及び向精神薬取締法の規制となる場合があり、法律上の扱いが非常に複雑なものになっています。
【事務所紹介】
今回は、大麻取締法によって規制されているものについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
合法と謳っている商品を大麻取締法の規制対象と知らずに購入してしまい、刑事事件に発展してしまったというケースは少なくありません。
大麻取締法違反事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件の弁護活動を担当した実績を持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
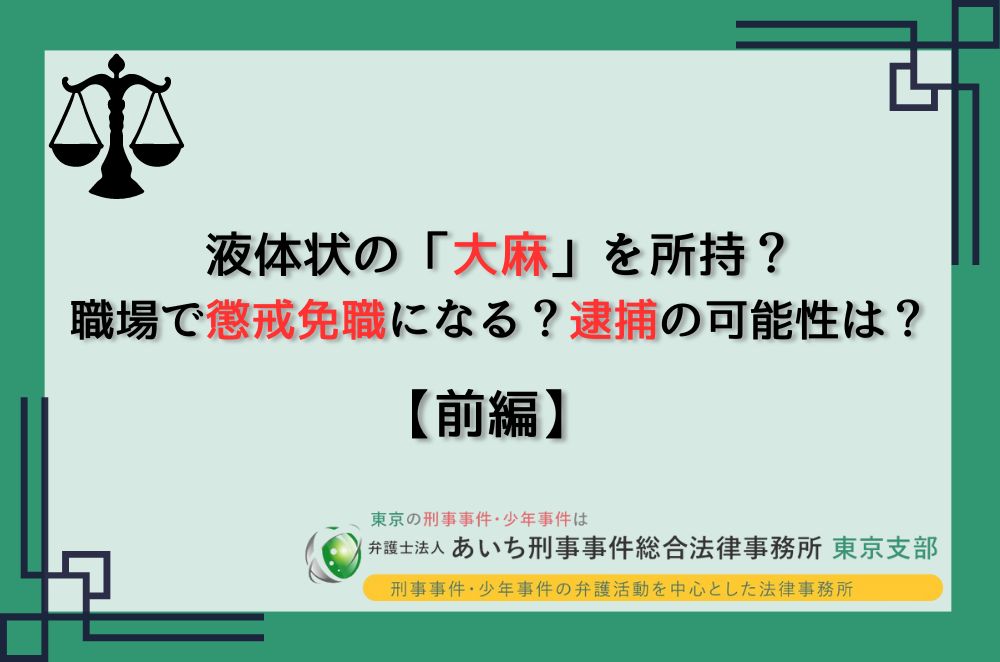
2024年3月29日、海上自衛隊の弾薬整備補給所の海士長が大麻リキッドを使用していたとして懲戒免職処分になったという報道がなされました。
「大麻」は大麻取締法によって規制されており、所持や譲渡については刑事罰が科されます。
今回は、大麻リキッドの所持事案を基に、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説をします。
前編となる本記事では法律上で規定されている大麻の定義や大麻リキッドについて、後編では大麻使用による懲戒免職について解説していきます。
【事例】
※以下の事例はフィクションです。
Aさんは品川区高輪近くにある企業に勤めている会社員(20代・男性)でした。
Aさんには喫煙の趣味がありましたが、ある時ベイプショップという、電子タバコのようなものを売っている雑貨屋でタバコ用のリキッドを購入しました。
店員から聞くと「大麻の成分が入っているが、日本ではまだ合法なものです」と説明を受けたので、Aさんはそれを信じて購入しました。
後日、そのべイプショップが「違法大麻のリキッドを販売して摘発された」というニュースを見たAさんは「自分が持っているリキッドも違法なものなのではないか」と心配になり、弁護士に相談することにしました。
【法理上規制される「大麻」とは】
大麻取締法では、どのようなものが「大麻」として禁止されるのかを定義しています。
法律上大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を指します。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされています。
大麻草という葉っぱの状態だけでなく、収穫した大麻を原料にして生産した製品も法律上の大麻に該当するとしています。
そのため、たとえ葉や草のような状態でなくても、ペーストにしたものやオイルにしたもの、リキッド状にしたものについても大麻として大麻取締法による規制の対象になります。
このような「大麻」はTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれており、このTHCが人の脳に作用して様々な薬物作用を引き起こすため、人体に有害な薬物として規制の対象になっているのです。
大麻草のうち、大麻取締法の規制対象となっていない茎や種子には、違法なTHC成分が含まれていないとされています。
茎や種子にはCBD(カンナビジオール)という成分が含まれていて、CBD自体は未だ大麻取締法の規制の対象になっていません。
そのため、Aさんの事例のように、「大麻の成分を含んでいるけれども合法です」という製品があるのです。
ただし、大麻取締法については2023年12月にも改正があり、今後の法改正次第ではCBD成分についても規制の対象となることもありうるでしょう。
Aさんも、おそらく店員としてはCBDオイルのつもりで販売したのかもしれませんが、THC成分を含むものであった場合、Aさんは大麻の所持をしていたということになります。
【大麻リキッドの所持・使用で逮捕?】
たとえリキッド状であったとしても、Aさんが持っていたものが大麻の葉っぱに由来する製品であれば大麻取締法の違反が成立します。
2024年4月時点では、大麻の所持は大麻取締法違反として扱われ、リキッド等の使用自体は犯罪にならない扱いです。
しかしながら、2023年12月に法改正があったため、2024年のうちに大麻の所持と使用の両方が法律違反になることになっています。
新しい法律が実際に適用されることになると、これまで大麻取締法違反として扱われていたもののほとんどが麻薬及び向精神薬取締法の違反になります。
麻薬及び向精神薬取締法違反として扱われることになると、大麻についても使用罪が新設され、法律上も刑罰が重くなります。
これまでは「5年以下の懲役」とされていたものが「7年以下の懲役」になりますが、今後は、大麻そのものを持っていなかったとしても使用罪によって逮捕される事案が急増することが予想されます。
職務質問をした際に大麻そのものが見つけられなかったとしても、尿検査の結果で大麻を使用したことが分かれば、コカインや覚醒剤と同様にその場で逮捕ということになります。
厚生労働省などの研究によると、一般的に、大麻(THC)を吸引した後、1週間程度は尿から成分が排出されますが、常習的に使用していた場合には3か月程度排出されることもあるようです。
(参考:『厚生労働省』大麻由来製品の使用とTHCによる使用の立証について)
また、法律上も刑罰が重くなったことで逮捕される事案や早期の釈放が認められない事案があり得るでしょう。
大麻をめぐっては今後も法規制の動向を注視していく必要があります。
【大麻取締法違反事件を起こしてお困りの方へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
大麻取締法違反事件についても、弁護活動を担当した実績を多く持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕

【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕
今回は、営利目的で覚醒剤を製造したとして、男女合わせて5人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
松山市内で覚醒剤を販売目的で製造したとして、台湾人の男を含む男女5人が覚醒剤取締法違反の罪で起訴された事件。
愛媛県警はきょう、覚醒剤取締法違反の疑いで千葉県と東京都の男女2人を新たに逮捕し、7月にも松山市の男女2人と東京都の女1人を逮捕していたことを発表しました。
警察によると、容疑者らは共謀の上、今年5月24日から30日の間に、覚醒剤およそ103グラムを製造したいうことです。
(※11/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】覚せい剤を密造 東京と千葉の男女らを逮捕」記事を引用しています。)
【覚醒剤取締法とは】
覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、成就及び使用に関して取締りを行うために作られた法律であると同法第1条で規定されています。
そもそも、覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で以下のように定義付けられています。
- 覚醒剤取締法第2条(用語の意義)
この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
今回の事例では、男女5人が販売目的(=営利目的)で覚醒剤を製造したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的で覚醒剤を製造した場合の覚醒剤取締法による罰則については、覚醒剤取締法第41条第2項で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(罰則)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
単純に覚醒剤を製造した場合(前条第1項)は「1年以上の有期懲役」、営利目的で覚醒剤を製造した場合(前条第2項)は「無期若しくは3年以上の懲役」と、目的で罰則の内容が異なり、営利目的で覚醒剤を製造した場合は非常に重い罰則が規定されています。
これは、営利目的だと他者にも覚醒剤が渡り、社会に対して影響が及ぶ危険性が高いことが大きな理由として挙げられるからです。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
覚醒剤取締法違反は、所持している覚醒剤や販売ルートなどを処分して証拠隠滅をするおそれが高いと捜査機関から判断される場合が多いため、逮捕・勾留されて身体を長期的に拘束される可能性が高いです。
また、身体を拘束されている間も、共犯者と口裏を合わせるおそれがあるとして、家族を含む一切の面会を禁止される可能性も十分にあります。
長期的に身体が拘束され、家族とも全く会えない状況となれば、職場や学校、家庭にも大きな影響を及ぼしかねません。
なので、ご家族が覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった場合は、少しでも早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が接見に向かい、逮捕されている本人から直接事実関係を確認したうえで、今後の取調べ対応などについて具体的なアドバイスをしてくれます。
また、早期の身柄開放を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になった際に少しでも軽い判決を獲得できるための弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で、ご家族が覚醒剤取締法による薬物事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】覚醒剤を営利目的で密輸すると成立する罪は?逮捕される可能性と逮捕後の流れ
【事例解説】覚醒剤を営利目的で密輸すると成立する罪は?逮捕される可能性と逮捕後の流れ
覚醒剤を密輸した場合、どのような問題が生じるかについて、あいち刑事事件総合法律
事務所が解説いたします。
【事例】
外国から覚醒剤約2キロを営利目的で密輸したとして、東京都新宿区に住むAさんは覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されました。
(※事例はフィクションです)
【覚醒剤を密輸するとどうなる?】
覚醒剤の輸出入については、覚醒剤取締法第13条で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第13条(輸入及び輸出の禁止)
何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
条文で規定されているように、覚醒剤の輸入及び輸出は全面的に禁止されています。
これは、自国ないし輸出先の国において、覚醒剤濫用の危険が生じ、又は保健衛生上の危害が生じることを防ぐためです。
覚醒剤を輸入し、覚醒剤取締法違反が成立した場合の処罰内容は、覚醒剤取締法第41条で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(刑罰)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第2項により営利目的が重く処罰される理由としては、所持・使用よりも営利目的の場合の方が薬物が社会に蔓延する危険性が高いからです。
今回の事例では、Aさんは営利目的で覚醒剤を輸入したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的による覚醒剤輸入であるため、Aさんには無期若しくは三年以上の懲役に処される可能性があるということになります。
【覚醒剤取締法違反で逮捕される可能性は?】
警察が被疑者を逮捕する事件の多くは、罪を犯した疑いのある人が証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがあったりする場合です。
上記のような逮捕するかどうかについての判断は、刑事訴訟法第60条第1項の規定をもとに考慮されます。
- 刑事訴訟法第60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
上記条文は勾留についての規定ですが、逮捕をするかどうかもこの事情を考慮して決せられます。
今回のような覚醒剤事犯などの薬物事件は、トイレに流したり、隠したりといった方法により証拠となる覚醒剤などを簡易かつ迅速に処分できてしまうため、その証拠の隠滅がされるおそれが高いと判断され、早いうちに逮捕に踏み切られる可能性があります。
したがって、逮捕される場合が非常に多く、それに引き続く勾留も長期化することが一般的です。
そして、身柄拘束が長期化した場合、職場や学校に出席できず、日常生活に支障がでたり、逮捕されたことが職場等に発覚すれば、退職に追い込まれたりすることが考えられます。
また、事件が報道されれば社会的信用を失い、社会復帰が困難になる可能性もあります。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
ご自身で覚醒剤取締法違反による薬物事件を起こしてしまったり、ご家族が逮捕されてしまった場合、できるだけ早期に刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
覚醒剤取締法違反による逮捕の場合には、身柄拘束が長期化する場合が多いです。
弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することで、早期の身柄解放や不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が覚醒剤取締法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に強い事務所であり、今回のような事例に対しても豊富な弁護経験があります。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
初回無料の法律相談や、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約を承っておりますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京農業大学ボクシング部の21歳の男子部員が、大麻を販売する目的で所持したとして新たに逮捕されました。
このボクシング部の逮捕者は3人目で、警視庁は部内で大麻が広がっていた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。
逮捕されたのは東京農業大学の3年生で、ボクシング部に所属するA(21)です。
警視庁によりますと、先月5日、東京 世田谷区の大学敷地内の駐車場で乾燥大麻およそ59.6グラム、末端の密売価格で29万8000円余りを販売する目的で所持したとして大麻取締法違反の疑いが持たれています。
先月以降、同じボクシング部に所属するいずれも19歳の男子部員2人が大麻を所持した疑いで逮捕されていて、Aは、このうち1人の部員が運動部の寮にあった大麻を外に持ち出そうとした際に手伝ったとみられています。
(※引用:2023年8月10日に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京農業大ボクシング部員を逮捕 大麻所持疑い 逮捕者は3人目」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.大麻取締法違反の処分・刑罰
◆所持・譲受・譲渡
⇒5年以下の懲役
◆営利目的の所持・譲受・譲渡
⇒7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金併科)
◆栽培・輸出・輸入
⇒7年以下の懲役
◆営利目的の栽培・輸出・輸入
⇒10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金併科)
2.犯罪の成立要件
大麻取締法では以下のような4つの行為を犯罪の成立行為としています。
- 所持
- 譲渡・譲受
- 栽培
- 輸出・輸入
ここで、上記の4つの犯罪行為には大麻の「使用」が含まれていないから、「使用」は罪に問われないと理解してはいけません。
大麻の「使用」があるということは、通常、大麻の「所持」が認められるので、最終的には大麻の「所持」で逮捕されてしまう可能性があります。
大麻を使い切っていても大麻所持の痕跡(吸引パイプ・大麻を入れていた小分けのビニール袋など)から、大麻の「所持」で逮捕される可能性もあります。
3.家族が逮捕されたら?
ご家族が大麻事件で逮捕された場合、できるだけ早期に刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
大麻取締法違反による逮捕の場合には、一般的に長期間による身柄拘束が多いです。
弁護士が入ることで長期間による身柄拘束を避けることができる場合もあります。
また、早期に弁護活動を開始することで、不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性もあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について解説致しました。
上述したように、大麻取締法違反で逮捕された場合には長期間による身体拘束が予想される為、刑事事件に強い弁護士による法的サポートが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
大麻取締法違反による刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート
【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート
大麻の所持及び栽培の事案で逮捕・勾留され起訴されたものの執行猶予付きの判決が言い渡され、職場復帰のサポートも功を奏したという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは東京都大田区内の路上で大田区内を管轄する大森警察署の警察官により職務質問を受け、大麻の所持が発覚し逮捕されました。
その後Aさんは起訴されましたが、起訴されて初めて遠方に住むAさんの家族にAさんが起訴された旨の連絡が来たため、Aさんの家族は当事務所の初回接見サービスを利用されました。
当事務所としても、当初は大麻の単純所持で起訴されているとだけ聞いていましたが、初回接見を行ったところ、Aさんは自分で使用する目的で大麻を栽培していたことが発覚しました。
そこで初回接見の報告を行ったうえで弁護の依頼を受けた弁護士が捜査機関と協議したところ、大麻栽培の事案でいわゆる再逮捕する予定であり、その量がなんと5キログラム以上にのぼることが分かりました。
大麻を5キログラム以上も栽培していたとなると、(実際にそのすべてが違法薬物として使用できるわけではありませんが、)Aさんが営利目的で大麻を栽培していたと疑われることは当然であり、事件の規模からして実刑判決が十分に予想される事案でした。
そこで弁護士は、保釈が認められる前からAさんの勤務先に連絡し、Aさんの置かれている立場やAさんが社会復帰した際には職場に戻りたいと考えていることを説明しました。
また、Aさんの保釈が認められたのちはAさんと一緒に職場に行き、Aさんの裁判で執行猶予判決を宣告された場合には雇用し続けてくれると言っていただきました。
裁判では、所持していた大麻がAさんの自己使用目的であり他人に渡したり言わずもがな売ったりはしていなかったこと、Aさんが反省していて家族のサポートが見込まれることに加え、Aさんには以降も雇い続けてくれる会社があることを説明し、社会内処遇で更生が見込まれることを主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻栽培の罪】
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、同法24条1項の単純所持(自己使用目的での所持)が問題となっていました。
しかし、栽培していた量が多かったため、捜査機関からは同条2項の営利目的での大麻栽培を疑われ、厳しい取調べが行われました。
【社会復帰をサポートして執行猶予判決を獲得】
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、報道されたり、捜査機関から身元確認などで連絡が行ったりするほか、勾留のため会社に連絡ができないことで事件の説明をせざるをえなくなる等の理由で、職場に発覚するおそれがあります。
当然、逮捕=解雇ということはあり得ませんが、有罪判決を受けた場合などでは就業規則などに基づき処分される可能性があり、また、同僚に前科があることを知られ自ら職を辞する方もおられます。
しかし、多くの方は裁判後に、あるいは服役を終えたのちに、社会復帰をすることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、裁判での結果はもちろんのこと、裁判の後の生活をも考えての弁護活動を行っています。
今回の事例では、依頼後すぐにAさんの勤務先に連絡して、執行猶予付きの判決を言い渡された場合にはその後も雇用して頂けるよう交渉しました。
また、Aさんが保釈された後は、Aさんと一緒に勤務先に行き謝罪に同席したほか、刑事裁判では法廷に立っていただき情状証人としてAさんの社会復帰をサポートしてくださることを主張しました。
このように、刑事裁判ではただ罪についてのみ話をするのではなく、被告人のその後の社会復帰をサポートし、社会内処遇の可能性を探っていく必要があります。
東京都大田区にて、家族が大麻栽培の嫌疑で逮捕・勾留されていて、社会復帰や執行猶予の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予②
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予②
過去に覚醒剤を使用した罪で有罪判決を受けたものの再犯により逮捕され、実刑判決を受けたものの一部執行猶予が獲得できたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件事件の5年ほど前に覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件で懲役1年6月執行猶予3年という「全部執行猶予付きの有罪判決」を受けていました。
しかし、その後も覚醒剤の使用を止めることができなかったAさんは、覚醒剤を使用し乍ら生活をしていたところ、事件当日の深夜に港区六本木を歩いていたところで港区内を管轄する麻布警察署の警察官による職務質問を受け、その際に採尿を求められ、Aさんが応じたところ尿から覚醒剤の成分が検出されたため逮捕されたという事案でした。
Aさんは執行猶予期間が明けてから2年ほどしか経っていなかったということもあり、Aさんの家族は減刑を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用した後、依頼してくださいました。
弁護士は、Aさんが罪を認めたうえで、現在は反省していること、再犯防止のため家族の監督体制が整っていることや依存症と向き合うため専門医に受診し始めたこと等を主張した結果、Aさんに対しては実刑判決ではあるものの一部執行猶予が付いた判決を言い渡されることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤使用の罪】
【再犯事件の刑事罰】
【一部執行猶予について】
執行猶予という言葉は、多くの方がご存知かと思いますが、改めて検討します。
執行猶予とは、刑事裁判において被告人は有罪ではあるが、事情を踏まえて刑の執行を猶予するというものです。
たとえば懲役3年執行猶予5年の判決が宣告された場合、
・本来であれば被告人は刑事収容施設(いわゆる刑務所)に3年間服役する必要があるが、
・一定以下の刑の宣告については、情状により刑の執行を猶予することができる
とされています。
但し、執行猶予期間中に再犯事件を起こし一定以上の刑に処された場合や、執行猶予と併せて保護観察が言い渡された場合に遵守事項を守らなかった場合等の際は、執行猶予は取り消され、服役することになる場合があります。
そのため、上記例で判決が言い渡された4年後に再犯事件で懲役2年の判決が言い渡された場合、被告人は2年+3年で5年間、刑事収容施設に収容されることになります。
一般的に執行猶予というと、上記のような「刑の全部の執行猶予」を指します。(刑法25条~同27条等)
そのほかに、平成25年6月に改正され、平成28年6月から施行された改正刑法では、「刑の一部執行猶予」という手続きが新設されています。
刑の一部執行猶予とは、実刑判決により服役する必要はあるが、服役する期間の一部についてはその執行を猶予し、執行猶予期間中に再犯等がなければその一部は執行されないというものです。
例えば、「被告人を懲役3年の刑に処する。その刑の一部である懲役6月の失効を4年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。」という判決が言い渡された場合、
・2年6ヶ月は刑事収容施設で服役する
・6ヶ月は刑の執行が猶予されるため、4年間再犯などで執行猶予取消しがなければ服役は不要
ということになります。
なお、覚醒剤を含む薬物使用等の罪で再犯事件を起こし一部執行猶予を宣告された場合、保護観察が付されることになります。
薬物使用等の罪で再犯防止を求めるためには、ただ刑事収容施設で懲役刑や禁錮刑といった刑に服するのでは不十分であり、長期的な医療や保健福祉機関の専門的な支援が必要不可欠です。
一部執行猶予判決を求めることで、少しでも早く社会復帰し、専門的な支援を依頼することが必要です。
但し、上記の手続きはあくまで数字上のものであり、実際の手続きでは未決勾留期間の算入や仮釈放などの手続きが用意されているため、刑期全日を刑事収容施設で生活するというわけではありません。
実際に刑事罰が科された場合にどれほどの期間収容されるのかについては、事件によって異なりますので、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、覚醒剤をはじめとした薬物使用等の罪で再犯した場合の弁護活動に対応しています。
東京都港区にて、覚醒剤使用の前科がある家族が再犯により逮捕・勾留されていて、一部執行猶予判決を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が接見を行い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、一部執行猶予判決の獲得可能性などについて丁寧にご説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予①
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予①
過去に覚醒剤を使用した罪で有罪判決を受けたものの再犯により逮捕され、実刑判決を受けたものの一部執行猶予が獲得できたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件事件の5年ほど前に覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件で懲役1年6月執行猶予3年という「全部執行猶予付きの有罪判決」を受けていました。
しかし、その後も覚醒剤の使用を止めることができなかったAさんは、覚醒剤を使用し乍ら生活をしていたところ、事件当日の深夜に港区六本木を歩いていたところで港区内を管轄する麻布警察署の警察官による職務質問を受け、その際に採尿を求められ、Aさんが応じたところ尿から覚醒剤の成分が検出されたため逮捕されたという事案でした。
Aさんは執行猶予期間が明けてから2年ほどしか経っていなかったということもあり、Aさんの家族は減刑を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用した後、依頼してくださいました。
弁護士は、Aさんが罪を認めたうえで、現在は反省していること、再犯防止のため家族の監督体制が整っていることや依存症と向き合うため専門医に受診し始めたこと等を主張した結果、Aさんに対しては実刑判決ではあるものの一部執行猶予が付いた判決を言い渡されることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤使用の罪】
ご案内のとおり、覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、その所持や使用が制限されています。
使用の罪については覚醒剤取締法19条により、医師により処方された方などでなければ、覚醒剤を使用することが出来ないとされています。
該当する条文は以下のとおりです。
覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
同法41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
【再犯事件の刑事罰】
刑事事件を起こし検察官により起訴された場合、刑事裁判に発展します。
刑事裁判が行われた場合、最終的に裁判官は被告人に対し有罪か無罪か、有罪であればどのような刑事罰を科すか、言い渡します。
有罪判決を受けた場合、俗にいう前科という扱いになります。
前科がある人が再度事件を起こした場合、俗に再犯事件と呼ばれ、前科がない人に比べて厳しい刑事罰が科せられる場合が一般的です。
執行猶予中の再犯事件では、原則として執行猶予が取消され、前回の裁判で受けた判決+今回の判決が科せられることになります。
Aさんの場合、執行猶予中ではなかったとはいえ、5年前に懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けたばかりでした。
前刑の執行猶予が明けてから2年ほどしか経っておらず、同種の事案ということもあり、当初より厳しい刑事罰が言い渡される事案であることは明らかでした。
【一部執行猶予について】
≪次回のブログに続きます≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、覚醒剤をはじめとした薬物使用等の罪で再犯した場合の弁護活動に対応しています。
東京都港区にて、覚醒剤使用の前科がある家族が再犯により逮捕・勾留されていて、一部執行猶予判決を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が接見を行い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、一部執行猶予判決の獲得可能性などについて丁寧にご説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻所持再犯で執行猶予判決
【解決事例】大麻所持再犯で執行猶予判決
大麻所持事件で過去に有罪判決を受けた方が、再犯で逮捕されたものの執行猶予判決を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区西早稲田在住のAさんは、10年近く前に大麻取締法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けたことがありました。
しかし、事件当日、新宿区西早稲田を管轄する警視庁戸塚警察署の警察官による職務質問を受け、Aさんの大麻所持が発覚してしまい、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持の罰条】
我が国では、大麻取扱者を除き大麻を所持することが禁止されています。
大麻を所持していた場合には大麻取締法違反にあたり、
・他人に売るなどして営利を目的としていた場合には「7年以下の懲役/7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」
・上記以外の場合で、自分で使用することを目的としていた場合などには「5年以下の懲役」
に処せられます。(大麻取締法24条の2第1項、同第2項)
【大麻所持事件での弁護活動】
大麻所持事件の場合、大麻を所持している認識があったのか、なかったのかにより、弁護活動が異なります。
今回のAさんの場合は、職務質問とその際の所持品検査で大麻が出てきていて、Aさん自身も所持を認めていたため、事案に争いはありませんでした。
大麻所持事件の場合は量が少なく認めていた場合には執行猶予付有罪判決を受ける場合が少なくありません。
しかし、Aさんの場合、過去に同種事案での前科があり、有罪判決を受けて10年未満での犯行でしたので、厳しい刑事処罰を受ける可能性が否定できませんでした。
~接見禁止の一部解除~
Aさんは勾留された際、家族であっても面会ができない「接見禁止決定」が下されていました。
しかし、Aさんが更生する為には家族の協力が不可欠であり、将来を見据えた話し合いをする必要があることから、弁護人はすぐに接見禁止の一部解除を申立て、証拠隠滅などを手助けする恐れがない家族については、面会が出来るよう求めました。
接見禁止の一部解除はすぐに発動され、依頼を受けた2日後に家族はAさんの面会が許されました。
~保釈請求~
刑事訴訟法上、前科の有無がすぐに刑事手続きに影響を及ぼすわけではありません。
しかし、前科があって今回の事件で実刑判決を受ける恐れがある事件では、実刑判決による収監を恐れて逃亡する恐れが否定できないなどの理由で保釈に慎重になる可能性がありました。
弁護人は、予め家族と打合せをして、Aさんが逃亡する意思がないことを確認するとともに、監督する者としてAさんが逃亡できないような環境づくりに協力して頂きました。
そして、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を裁判所に提出し、裁判官に対して書類・口頭でAさんの逃亡のおそれがないことや証拠隠滅の意思がないことを主張した結果、起訴された次の日には保釈が許可され、即日保釈金を納付しAさんは手続き上最速で拘束を解かれることとなりました。
~刑事裁判~
保釈が認められた場合でも、Aさんは裁判を受けることに変わりありません。
弁護人は、保釈された直後のAさんに、薬物依存症のおそれがあるとして専門家による診断・受診の必要性を説明し、専門の治療施設を紹介しました。
Aさんの保釈後の決意と行動、家族のサポート体制などを踏まえ、弁護人はAさんが反省していて二度とこのような事件を起こさないよう努力している状況について被告人質問や情状証人で証言してもらい、その内容を弁論で主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることに成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに大麻所持などの薬物事件を多数経験してきました。
特に再犯事件の場合、実刑になる恐れがあるだけでなく、社会復帰後も見据えて薬物依存症と向き合うなどの対策は必要不可欠です。
薬物の再犯事件では、薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都新宿区西早稲田にて、過去に大麻所持で有罪判決を受けた方が再犯事件で逮捕されてしまい、執行猶予判決を獲得できるか知りたいという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。