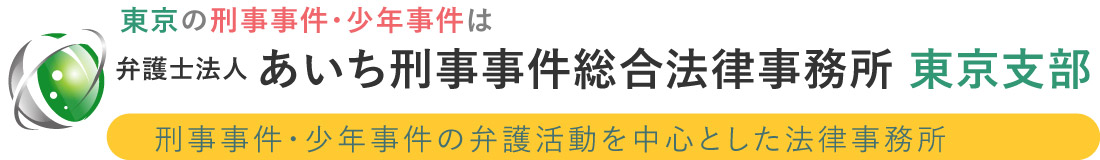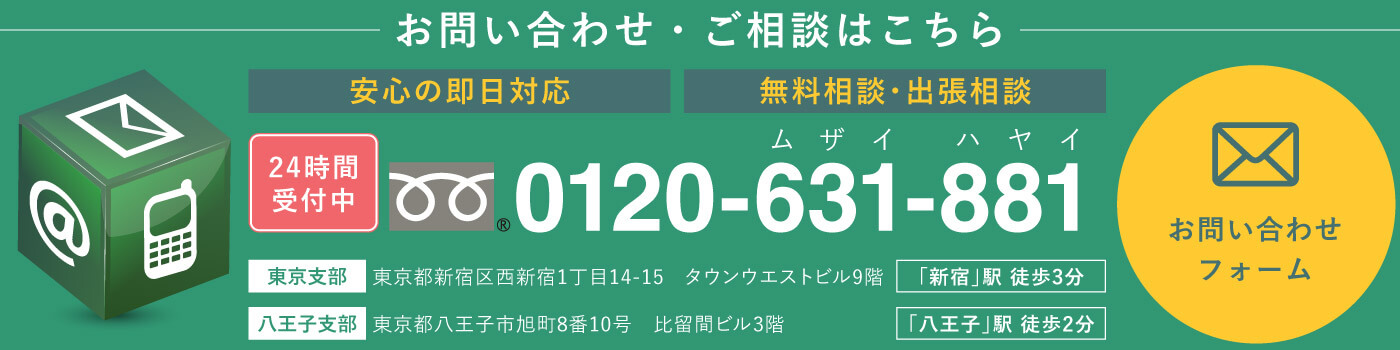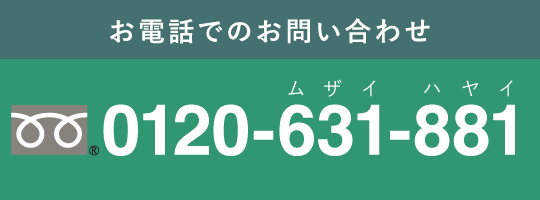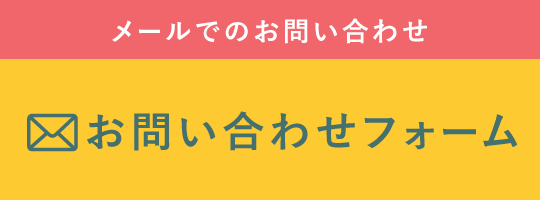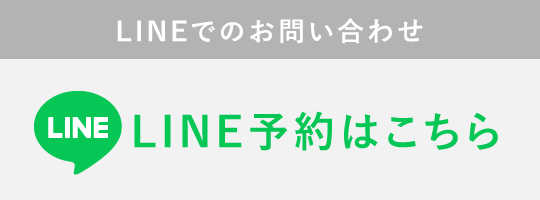Archive for the ‘交通事件’ Category
【事例解説】「殺してやる!」隣人トラブルが脅迫事件に発展|脅迫罪が成立する要件は?
【事例解説】「殺してやる!」隣人トラブルが脅迫事件に発展|脅迫罪が成立する要件は?

同じマンションに住む者同士の隣人トラブルが刑事事件に発展するというケースは珍しくありません。
今回は、隣人トラブルが脅迫事件に発展した事例をもとに、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都新宿区にあるマンションに在住の男性A(52)は、隣の部屋に住んでいる男性V(31)が友人を招いて部屋で連日騒いでいることに苛立っていました。
我慢の限界が来たAは、Vの部屋の扉を叩きながら「何日も騒いでいてうるさい!お前ら殺すぞ!」と語気鋭い口調で繰り返し叫んでいました。
このAの行動に恐怖を覚えたVが新宿警察署に通報し、現場に臨場した警察官からAは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【脅迫罪とは?】
今回、Aは脅迫罪の疑いで逮捕されています。
脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。
- 刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(第2項省略)
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知して人を「脅迫」した場合に成立します。
「脅迫」とは、人を畏怖させることができる程度の害悪の告知を指します。
ただ、脅迫を受けた相手が実際に畏怖したかどうかについては必ずしも必要ではなく、判例では、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知であったことを被害者が認識していればよいと解釈されています。
今回の事例で考えると、AはVの部屋の扉を叩きながら「お前ら殺すぞ!」と語気鋭い口調で叫んでいました。
「殺す」という言葉は、生命に対して害を加える内容に該当します。
また、Aの行為にVは恐怖(畏怖)しているため、Aの行為は人を畏怖させるには十分な程度の害悪の告知であると判断される可能性が高いです。
そのため、Aの行為は脅迫罪に問われる可能性が高いため、警察に逮捕されたと考えられます。
【脅迫事件を起こしてしまったら弁護士へ】
脅迫事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
脅迫罪のような被害者が存在する犯罪の場合、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
被害者との示談を締結させることで、早期釈放や不起訴処分を獲得できる可能性がグッと高まり、起訴された場合でも量刑が軽くなる可能性が高くなります。
ただ、脅迫罪の被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることが多く、当事者同士で示談交渉を行おうとしても連絡を取り合ってくれないことが多いです。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者に示談交渉を行うため、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】実況見分とは?実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて徹底解説
【事例解説】実況見分とは?実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて徹底解説

事故や事件が起きた後は「実況見分」という捜査が行われます。
実況見分という言葉は聞いたことがあるけど、どういった捜査を行うものなのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都練馬区にある会社で勤務している男性A(28)は、毎日自宅から会社まで車で通勤しています。
ある日、仕事が終わったAがいつも通り車で帰っているところ、交差点を右に曲がった際に横断歩道を自転車で渡っていた男性V(32)に気付かずぶつかってしまいました。
Aはすぐに車から降りてVのもとに駆け寄り、救急車を呼び練馬警察署にも連絡しました。
事故現場に臨場した警察官からは「Vの治療が落ち着き次第、実況見分を行うので後日改めて連絡します」と言われました。
実況見分でどういう対応をすればいいか分からなかったAは、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【実況見分とは】
実況見分とは、事故や事件が起きた際に被害者や加害者などの当事者立会いのもと、警察官が事実確認や証拠保全を行う任意捜査を指します。
警察官は、事故・事件現場の状況や事故・事件発生時の状況などを当事者に質問し、「実況見分調書」という実況見分の結果がまとめられた書類を作成します。
適切な過失割合の算定など、後に示談交渉を行う場合に実況見分調書が重要になってきます。
交通事故の場合、物損事故であれば原則として実況見分は行われませんが、今回の事例のような人身事故であれば実況見分が行われることになります。
【実況見分の流れ】
今回の事例のような交通事故を起こした場合の大まかな実況見分の流れは以下の通りです。
①事故発生後、警察に連絡する
②警察が事故現場に臨場して実況見分開始
③実況見分終了後、警察署で聞き取り捜査
④調書類の内容を確認して署名押印
今回の事例では、Vが救急搬送されて立会いができなかったため実況見分は後日行うことになっていますが、救急搬送などがされていない場合は事故現場に警察官が臨場してそのまま実況見分が始まることが多いです。
また、実況見分終了後は警察署で聞き取り捜査が行われることが多いです。
聞き取り捜査の内容については、実況見分調書ではなく「供述調書」として作成されます。
【実況見分の注意点】
実況見分は任意捜査であるため、当事者は立会いを拒否することもできます。
ただ、立会いを拒否してしまうと、警察官は一方の当事者からしか話を聞けなくなるため、偏った実況見分調書が作成される可能性があります。
自分が主張したい内容と全く違う内容の実況見分調書が作成されるおそれがあるので、実況見分には可能な限り立ち会うようにすることをおすすめします。
【実況見分と現場検証の違い】
実況見分に似た捜査で「現場検証」というものがあります。
現場検証も、実況見分と同様に事故・事件現場で行われる捜査を指しますが、これらの大きな違いは「令状の有無」です。
実況見分は令状が必要ない任意捜査ですが、現場検証は裁判所が発付する令状が必要になる強制捜査です。
現場検証は事件性がある場合に行われます。
【人身事故を起こしてしまったら弁護士へ相談】
人身事故を起こして加害者となってしまった場合、罰金刑や懲役刑などの刑事処分を受ける可能性が高くなります。
また、起訴されてしまうと前科がつくことになり、今後の生活に影響が及ぶことになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得することで、前科がつくことを防ぐことができます。
不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、弁護士を代理人として示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で人身事故を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】過失運転致死罪による自動車運転死傷処罰法違反とは?執行猶予の有無や示談の重要性
【報道事例】過失運転致死罪による自動車運転死傷処罰法違反とは?執行猶予の有無や示談の重要性

過失運転致死罪は、誰しもが日常の運転中に起こしてしまう可能性がある重大な犯罪です。
今回は、東京都杉並区の路上で起きた実際の報道をもとに、過失運転致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都杉並区で親子が乗用車にはねられ死亡した事故で、車が時速25キロほどでバックしていたことが分かりました。
整備士の男性A(50)は12月26日、杉並区の路上で、親子2人を車ではね死亡させた過失運転致死の疑いで28日朝、送検されました。
その後の調べで、Aがバックではねた際の車の速度は、25キロから30キロと推定されることが分かりました。
また、母親は衝突の後、約11メートルにわたり引きずられたとみられています。
車の不具合は今のところ確認されていないということで、警視庁が原因を調べています。
(※12/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「親子をはねた車 “時速25km”でバック 母親は11m引きずられたか 整備士の男を送検 東京・杉並区」記事の一部を変更して引用しています。)
【過失運転致死罪とは】
過失運転致死罪は、日常の運転中に誰しもが予期せず起こしてしまう可能性のある重大な犯罪です。
過失運転致死罪については、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
- 自動車運転死傷処罰法第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は、運転者が必要な注意を怠った結果、人の死を引き起こした場合に成立します。
法的には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」に対して、最大7年の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金で処罰されます。
過失運転致死罪の成立には、運転者の過失と死亡事故との因果関係が必要です。
例えば、スピード違反、信号無視、安全確認の怠慢など、様々な運転上の過失が考えられます。
運転者が故意に事故を起こしたわけではなく、不注意や油断などの運転手が「通常必要とされる注意」を怠ったことによる事故で相手を死亡させてしまったということが、過失運転致死罪の成立において重要な点になります。
過失の程度は、事故の状況、運転者の行動、交通環境などによって異なります。
例えば、速度違反や安全確認の怠慢は、明らかな過失と判断されることが多いです。
判例では、過失の程度に応じて、罰金から懲役刑まで様々な刑罰が科されています。
過失運転致死罪の判決は、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転記録など、多くの要因を考慮して決定されています。
【過失運転致死罪で執行猶予はつく?】
過失運転致死罪の刑罰は、その重大性に応じて厳しく定められています。
自動車運転死傷処罰法では、過失運転致死罪に対して7年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金を規定しています。
実際の判決では、事案の具体的な状況や運転者の過去の記録、被害者との関係などが考慮されるため、刑罰の程度には幅があり、場合によっては執行猶予が付与されることもあります。
執行猶予は、一定期間内に罪を犯さずに生活していれば刑の執行が免除される制度です。
過失運転致死罪は、過失による事故であること、運転者の反省の態度、被害者遺族との示談成立などが考慮されることで、執行猶予が付与される可能性もあります。
執行猶予が付与されると、すぐに刑務所に収容されることはありませんが、一定期間、法的な制約を受けることになります。
【過失運転致死罪における示談の重要性】
過失運転致死罪における示談締結は、法的な解決において非常に重要な役割を果たします。
示談は、加害者と被害者(または遺族)間で行われる私的な合意であり、事故による損害の賠償や心情の和解を目的としています。
示談が成立すると、裁判所はこれを量刑の際に考慮し、執行猶予や減刑判決など、より軽い刑罰を科す可能性が高まります。
特に過失運転致死罪の場合、被害者側の感情や損害の大きさが刑罰に大きく影響するため、示談は刑事訴訟において重要な要素となります。
ただ、示談交渉は感情的な問題や法的な複雑さを含むため、専門家である弁護士による介入が推奨されます。
弁護士は、公正かつ効果的な示談の成立を目指し、加害者と被害者双方の利益を考慮した解決策を提案します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で過失運転致死罪による刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕
【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕
道路交通法違反の中でも、車やバイクなどでの暴走行為を指す「共同危険行為」は特に重要な問題です。
そこで、本記事では、実際に共同危険行為による道路交通法違反で逮捕された事例をもとに、共同危険行為の定義や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が詳しく解説します。
【事例】
山梨県小菅村の県道でドリフトや並走などの暴走行為を繰り返したとして埼玉県などの20代の男4人が逮捕されました。
道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いなどで逮捕されたのは、埼玉県の会社員男性A(25)、茨城県の大学生男性B(22)、千葉県の大学生男性C(20)、東京都の会社員男性D(25)です。
警察によりますとAら3人は今年7月の午前1時ごろ、小菅村の県道上野原丹波山線、通称・鶴峠を乗用車3台でドリフトや並走などを繰り返して一般車両の通行を妨害し、Dは乗用車をAに提供した疑いがもたれています。
地元住民や通行人からの情報提供などをもとに捜査し、4人を特定したということです。
4人は県道のおよそ1キロの区間を1時間半にわたり、並走や法定速度を30キロ上回る時速60キロで10往復以上走っていたということです。
調べに対し4人は容疑を認めていて、警察は山道を車でドリフトするなど暴走するローリング族の仲間同士とみて詳しい動機などを調べています。
(※10/16に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京隣接の峠道の県道でドリフトなど暴走行為の疑い “ローリング族”4人を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【共同危険行為とは】
共同危険行為については、道路交通法第68条で以下のように規定されています。
- 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
共同危険行為は、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の車両を連ねて通行または並進させ、交通の危険を生じさせたり他人に迷惑が及ぶ行為を指します。
具体的には、運転者同士が協力して高速で走行したり、危険な運転を行ったりすることが該当します。
このような行為は、他の道路利用者に対しても大きな危険をもたらすため、共同危険行為等禁止違反として道路交通法違反が成立します。
2004年の道路交通法の改正により、被害者がいなくても処罰の対象となるようになりました。
これは、暴走族などの不正行為を抑制するための措置です。
【共同危険行為による道路交通法違反の罰則】
共同危険行為による道路交通法違反の罰則については、道路交通法第117条の3で以下のように規定されています。
- 道路交通法第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文に規定されているように、共同危険行為による道路交通法違反は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑で処罰されます。
【道路交通法違反(共同危険行為)事件を起こしてしまったら】
道路交通法違反事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまい、検察官から勾留請求されて勾留が決定すると、最大で20日間身柄が拘束されるおそれがあります。
長期の身柄拘束は、仕事や学校、家族にも影響を及ぼすこともあるため、早期に釈放されるためには、逮捕後の勾留を阻止することが重要です。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すると、弁護士が検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを主張するなどの早期釈放に向けた弁護活動を行います。
また、公判請求されてしまい、公判が開かれることになった場合は、弁護士が執行猶予付き判決や減刑判決の獲得を目指すための弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件による刑事事件の弁護活動を多数担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が道路交通法違反事件で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談については事前のご予約が必要になるので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
ひき逃げで逮捕されたというニュースをよく目にすることもあると思いますが、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
それでは、ひき逃げで問われる可能性がある罪は、何罪なのでしょうか。
今回は、東京都府中市で起きたひき逃げ事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
30日未明、東京・府中市で女性を車でひいて死亡させ、そのまま逃げたとして、会社員の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、東京・府中市の会社員男性A(26)で、30日午前1時半ごろ、府中市内の路上で乗用車を運転中に、近くに住む会社員女性V(36)をはねて死亡させ、逃走した疑いがもたれています。
警視庁によりますと、通報を受けて駆けつけた警察官が、現場からすぐ近くの駐車場に血のようなものがついた無人の車を発見し、車に戻ってきたAから事情を聞き、逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認めていて、「人をひいたとは思わなかったが、逮捕状に書かれてることは間違いではない」と話しているということです。
(※9/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・府中市でひき逃げ事件 女性はねられ死亡 26歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【ひき逃げで問われる罪】
ひき逃げとは、車などの自動車を運転している際に人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察や救急の連絡といった措置を行わずに現場を逃走する行為を指します。
冒頭でも記載しましたが、「ひき逃げ罪」という罪はありません。
ただ、ひき逃げは立派な犯罪行為であり、以下のような犯罪が成立する可能性が高いです。
- 道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
それぞれどのように規定されているのかについて、見ていきましょう。
【道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)】
通常、自動車などを運転中に交通事故を起こしてしまった場合は、負傷者の救護や警察へ事故が起きたことの報告といった措置を取ることが義務付けられています。(道路交通法第72条)
道路交通法第72条前段が「救護義務」、同法後段が「報告義務」として規定されています。
救護義務があるにも関わらず負傷者を救護しなければ救護義務違反、報告義務があるにも関わらず警察などに報告しなければ報告義務違反となり、処罰されます。
救護義務違反の処罰内容は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)、報告義務違反の処罰内容は3月以下の懲役又は5万円位以下の罰金(道路交通法第119条第1項17号)と規定されています。
【過失運転致死傷罪】
自動車などを運転するにあたって必要な注意を怠り、相手に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
- 自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【危険運転致死傷罪】
前述した過失運転致死傷罪は、運転中の過失(不注意)が原因で相手を死傷させた場合に成立しますが、自身の運転が危険だということを認識していた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪に該当する行為は、自動車運転処罰法第2条で以下のように規定されています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって、相手に怪我を負わせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役で処罰されます。
【ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ】
ひき逃げは、一度事故現場から逃走しているため、逮捕される可能性があり、今回の事例のように、相手が死亡している場合は逮捕される可能性も高まります。
ひき逃げで逮捕されてしまうと、検察官から勾留請求がされる可能性も高く、勾留が決定すれば最大20日間身体が拘束されるおそれがあります。
また、ひき逃げは起訴される可能性も高く、起訴されてしまえば、罰金刑か懲役刑で処罰されることになり、前科もつきます。
ひき逃げで不起訴処分や執行猶予判決、減軽判決を獲得するためには、被害者や被害者が死亡している場合は遺族と示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、とくに被害者が死亡している場合、被害者遺族は処罰感情も強い傾向にあります。
なので、ひき逃げ事件で示談交渉を進めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者や被害者遺族との示談交渉を進めてくれるので、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに進められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまった方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例紹介】電動キックボードで起きた危険運転致傷事件
【事例紹介】電動キックボードで起きた危険運転致傷事件
飲酒した状態で電動キックボードを運転して被害者を怪我させてしまったという危険運転致傷事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【参考事件】
酒を飲んだ状態で運転していた電動キックボードが横転し、同乗の30代女性に重傷を負わせたとして、警視庁目黒署は18日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、東京都目黒区の男性会社員(26)を書類送検した。
警視庁によると、電動ボードの事故で、飲酒による危険運転致傷容疑での立件は全国初とみられる。
署によると、2人は事故当日に飲酒。
男性は「酒を飲んで楽しくなって運転してしまった」と容疑を認めている。
署は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。
書類送検容疑は2月12日午後9時25分ごろ、目黒区の都道で電動ボードを飲酒運転し横転。
同乗の女性に5週間のけがを負わせた疑い。
(共同通信 令和5年5月18日(水)12時01分配信「電動ボードを危険運転の疑い 飲酒で書類送検、全国初か」より引用)
・電動キックボードの法的性質
まず、今回問題となっている「電動キックボード」の法律上の区分について検討します。
※このルールは令和5年7月より変わります≪詳細はこちら≫。
令和5年5月時点で、電動キックボードと言われる乗り物は、モーターとバッテリーを動力としていることから
・0.60kw以下の電動キックボードについては原動機付自転車
・0.60kwを超える電動キックボードは普通自動二輪などのバイク
として扱われています。
よって、参考事例がどちらに当たるにせよ、道路交通法のいう「車両」として扱われますので、自動車やバイクを運転する場合と同じルールに則って運転する必要があります。
・電動キックボードで危険運転致傷罪が成立
参考事件の男性が送致された危険運転致傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)に定められています。
自動車運転処罰法第1条ではこの法律における自動車を「道路交通法第2条第1項」における「第9号に規定する自動車」および「第10号に規定する原動機付自転車」と定めています。
Aさんが運転していた電動キックボードについてもこれに該当します。
今回の参考事例では、男性は危険運転致傷罪で在宅捜査を受けています。
これは酒に酔った状態で車両(電動キックボード)を運転したことに拠ります。
危険運転致傷罪については、以下2条で規定されています。
自動車運転処罰法2条1項
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
自動車運転処罰法3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
自動車運転処罰法2条のいう危険運転は、車両を運転している時点で「正常な運転が困難な状態」とされる場合に該当します。
自動車運転処罰法3条のいう危険運転は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転したのちに「正常な運転が困難な状態」へと変化した場合に該当します。
どちらも飲酒や薬物のほか運転の経験がない無免許運転の場合などの危険な運転をしたことにより、事故を起こしてしまった場合に成立し、「人を負傷させた者」には危険運転致傷罪、「人を死亡させた者」の場合には危険運転致死罪が成立します。
なお、人身事故というと事故を起こした相手方の車両の乗員や歩行者・自転車などが相手方になるイメージですが、単独事故の結果同乗者が怪我をした場合にも人身事故として処理されます。
今回の参考事例では、被害者は電動キックボードに乗車していた方ですが、この場合でも人身事故として危険運転致死傷罪(あるいは過失運転致死傷等)が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、電動キックボードに関する事件など検挙例が少ない交通事故事件にも対応しています。
電動キックボードが関係する事件事故を起こしてしまった方、危険運転致死傷罪で家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現
【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現
飲酒運転で人身事故を起こしてしまい逮捕されたという事件で、早期の釈放を実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、世田谷区内の友人宅で酒を飲み、その直後に車を運転して帰宅しようとしたところ前方に停車していた車にぶつかりました。
事故の被害に遭った車の運転手Vさんは、すぐに警察署に通報し、世田谷区内を管轄する玉川警察署の警察官が臨場しました。
警察官は、Aさんの呼気からアルコールの香りがするため飲酒運転の疑いがあるとして呼気検査を行い、基準値を上回るアルコールが検知されたた酒気帯び運転の嫌疑で逮捕しました。
Vさんはその後病院に行ったところ、全治2週間の診断を受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた翌日朝までに書類を作成し、検察官に勾留が不要である旨を主張したところ、担当検察官は勾留は不要であると判断して勾留請求をしなかったため、早期の釈放を実現することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転での人身事故】
今回の事件では、Aさんが①飲酒運転をしたうえ②人身事故を起こしたことが問題となっています。
①飲酒運転について
ご案内のとおり、いわゆる飲酒運転は道路交通法等で禁止されています。
Aさんの場合、基準値を超えたアルコールが検知されたことから、酒気帯び運転の罪に問われました。
言い換えると、泥酔していた場合などに成立する酒酔い運転の罪には問われていません。
酒気帯び運転についての罰条は以下のとおりです。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等…を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
②人身事故について
車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、今回のAさんの事例では①酒気帯び運転の罪と②過失運転致傷罪で捜査を受けましたが、アルコールの影響がある状態で運転をして結果被害者を死傷させたという人身事故を引き起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪が成立することがあります。
【早期の釈放を求める弁護活動】
刑事事件で捜査を受ける際、原則として在宅での捜査を行う必要がありますが、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがあると認められた場合、逮捕され勾留される可能性があります。
まず逮捕については、緊急逮捕・現行犯逮捕を避ける方法はほぼないと言えますし、通常逮捕についても(警察官に根回しをできる場合はありますが)多くの事件では逮捕の事前連絡はないため、避けることは難しいです。
しかし、逮捕後すぐに弁護活動を行うことで、検察官や裁判官に対して(延長を含め)20日間の勾留が不要である旨を主張し、釈放を求めることができます。
早期の釈放を求めるためには、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、監督できる者がいること、等を積極的に主張していく必要があります。
検察官や裁判官がどのような点で釈放に懸念を示すのかは事件によって異なるため、早期の釈放を求める場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都足立区にて、家族が飲酒運転のうえ人身事故を起こしてしまい、早期の釈放を求める場合、初回接見サービス(有料)が可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
交通トラブルで暴行罪・傷害罪に問われた場合の手続きと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内で会社を経営していました。
事件当日、Aさんは自家用車を運転し港区内のコインパーキングに車を停めようとした際、Vさんの車が本来停めて良い場所ではないところに停まっていたため駐車できず、Aさんは降車して乗車中のVさんに対し「そこ邪魔だからどけろ」と言い詰め寄りました。
しかしVさんが相手にしなかったことから、AさんはVさんの車のエンジンキーを抜き取って外に投げました。
その後Vさんは降車しようとしましたが、AさんはVさんがドアを開けた途端にドアを閉め、Vさんは手を挟む形になりました。
その後Vさんが通報したことで臨場した港区内を管轄する高輪警察署の警察官は、AさんとVさんの双方の主張を高輪警察署で聴くことにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【交通トラブルについて】
今回のAさんの事例は、交通トラブルがそのきっかけとなっての口論でした。
口論自体はすぐに刑事事件に発展するような性質のものではありませんが、その後AさんはVさんの車両のエンジンキーを抜き取って外に投げ、Vさんが降車しようとした際にドアを閉めました。
この時、AさんにはVさんを怪我させてやろうという積極的な加害意思があったとは言えませんが、他人が開けようとしたドアを了解なく閉める行為は暴行罪の言う不法な有形力の行使に該当すると考えられ、結果としてVさんが怪我をしていることから、傷害罪が成立すると考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
Aさんの行動や言動が粗暴であったことは言うまでもありませんが、その理由はAさんが精神疾患を抱えていたことにありました。
そこで弁護士は、Aさんに受診状況などを確認したところ、通院していないことが発覚したためすぐに医師の診断を受け治療を開始するよう伝えました。
示談交渉においては、弁護士がAさんに代わってVさんに対し謝罪を行い、精神疾患の点も含め丁寧に説明を行いました。
Vさんについても粗野な言動・行動が多々あり、示談交渉は難儀しましたが、丁寧な説明を繰り返し行ったところ、最終的に示談書の締結となりました。
最終的に弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが反省していること
・事件にはAさんの精神疾患が影響している可能性があること
・示談交渉の結果示談締結となりVさんがAさんの刑事処罰を望んでいない意向であること
を説明した結果、担当検察官はAさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、交通トラブルから暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合の弁護活動の経験がございます。
交通トラブルの場合、双方が主張を繰り広げることが多く、収集がつきません。
第三者の立場であり法律の専門家である当事務所の弁護士が当事者双方から話を聞き、当時の状況について検討したうえで、謝罪するべき点の確認や示談金額の提示等を行い、示談締結を目指します。
東京都港区にて、交通トラブルの結果暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転で人身事故
【解決事例】飲酒運転で人身事故
酒を飲んだ状態で運転したいわゆる飲酒運転をしてしまい人身事故を起こしたという事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都足立区在住のAさんは、足立区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事故の前日に飲酒した後、当日も運転の3時間前に飲酒をし、その後自動車を運転したところ、追突事故を起こしてしまいました。
目撃者がすぐに通報し、臨場した足立区内を管轄する千住警察署の警察官によってAさんの呼気検査が行われたところ、Aさんの呼気からは0.8mg/Lのアルコールが検知されました。
その後警察官はAさんの受け答えや歩行検査などを総合考慮し、Aさんを酒気帯び運転と人身事故(過失運転致傷)の罪で取調べ等をし、その後検察官送致しました。
Aさんは検察官からの取調べを受けた際、「この事件は酒気帯び運転ではなく酒酔い運転又は危険運転致傷罪の可能性も視野に捜査する」旨の説明と、厳しい口調での取調べを受けたことで、当事務所の弁護士による無料相談をお受けになりました。
なお、追突された乗用車を運転していたVさんは、むち打ち症状が見受けられましたが命に別状はありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転での問題】
まず、お酒を飲んだあとに運転をしたいわゆる飲酒運転での問題について検討します。
飲酒運転の禁止については、以下のとおり規定されています。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
よって、例えば呼気検査で0.01mg/Lのアルコールが検知されたとしても、運転することはできないことになります。
他方で、刑事事件にとしては、以下の「酒気帯び運転」「酒酔い運転」のいずれかに該当する場合となっています。
・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合)
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等…を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転(酩酊状態で、直進歩行ができない、受け答えができない、呼気中のアルコール濃度が極めて高い場合など)
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
今回のAさんの事件では、警察官は「呼気検査は基準値の約5倍の数値が出たが、受け答えや歩行検査に問題がなかったため、酒酔い運転には問えず酒気帯び運転になるだろう」と判断した一方、送致を受けた検察官は「この数値で歩行検査や受け答えに問題がなかったというのは不自然であり酒酔い運転の可能性がある」と判断したと考えられます。
【飲酒運転と人身事故】
更にAさんは、運転している乗用車を別の乗用車に接触させてしまう事故を起こしてしまい、それによりVさんに怪我を負わせています。
人身事故により被害者に怪我を負わせた場合、まずは過失運転致傷罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
一般的な人身事故については、この過失運転致傷罪が成立します。
但し、
今回の事件は飲酒運転での人身事故でした。
アルコールの影響下で運転して事故を起こした場合、より重い危険運転致死傷罪が成立します。
関連条文は以下の2条です。
同法2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
同法3条1項 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
両者は違いが分かりにくいですが、人身事故を起こした際の状態が
正常な運転が困難な状態 :15年以下の懲役(同法2条1号)
正常な運転に支障が生じる恐れがある状態:12年以下の懲役(同法3条1項)
となっています。
とりわけ酒酔い運転と判断されるような状態で運転をして被害者を死傷させるような事故を起こした場合には、過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪の成立が検討されます。
今回のAさんについては、いわゆる酒に強い方で、呼気検査の数値は高いものでしたがそこまでの酩酊状態ではありませんでした。
結果的に、Aさんは過失運転致傷罪と酒気帯び運転の両罪で処分されました。
このうち過失運転致傷罪については、被害者がいる事件ですので、示談交渉を行いました。
Aさんは任意保険に加入していて、今回の事件でもVさんに対し補償がなされましたが、それとは別途謝罪と賠償を行い、刑事事件化を望まない旨の条項(宥恕条項)を設けた示談書を締結して頂きました。
最終的にAさんは、過失運転致傷罪については不起訴となり、酒気帯び運転については略式手続による罰金刑となりました。
東京都足立区にて、飲酒運転の状態で人身事故を起こしてしまい、酒気帯び運転・酒酔い運転・過失運転致傷罪・危険運転致死傷罪などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
【②自転車での人身事故】
【③自転車でのひき逃げ】
ご案内のとおり、車やバイクで事故を起こしたにもかかわらずその場を立ち去るような行為は、俗にひき逃げと呼ばれます。
ひき逃げは、道路交通法の定める「救護義務」又は「報告義務」に違反します。
1 救護義務違反について
道路交通法72条1項【前段】 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
条文の前段では運転手の、救護義務違反を規定しています。
Aさんは、事故を起こしたにもかかわらず、被害者が怪我をしているかどうか確認していません。
しかし、結果として被害者であるVさんは怪我をしていました。
加害者は被害者が怪我をしていた場合に、消防局に119番通報したり、可能な場合には車道から被害者を移動させ止血などの手当てを行わなければいけないところ、それらをしていないAさんは、救護義務に違反する可能性があります。
2 報告義務違反について
もし事例でAさんが事故を起こした結果Vさんは怪我をしていなかったとしても、事故を起こしたことについて警察署や交番に届け出る義務があります。
この義務を怠った場合には、報告義務違反に該当します。
条文は以下のとおりです。
道路交通法72条1項【後段】 この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に…報告しなければならない。
3 救護義務違反と報告義務違反の罰条
救護義務違反と報告義務違反について、罰条については以下のとおり規定されています。
(救護義務違反)
道路交通法117条1項 車両等…の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
道路交通法117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
(報告義務違反)
道路交通法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
17号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
救護義務違反については非常に分かりにくいですが、
・軽車両以外で事故を起こした運転手自身⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・軽車両以外で事故を起こしていない運転手⇒5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・軽車両で事故を起こした運転手(&軽車両以外の同乗者)⇒1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
となっています。
報告義務違反については、軽車両も車・バイクも変わらず3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
ここまで4回に亘り解説しましたが、自転車の事故であっても車やバイクでの事故と同様に、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があるのです。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。